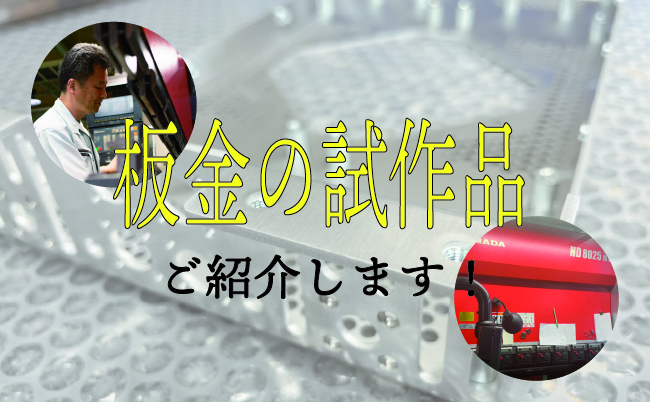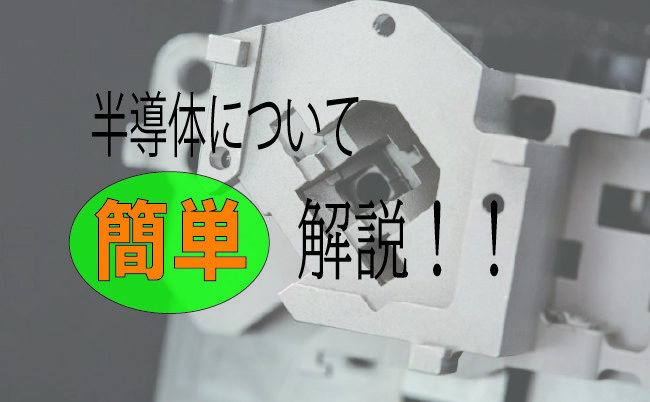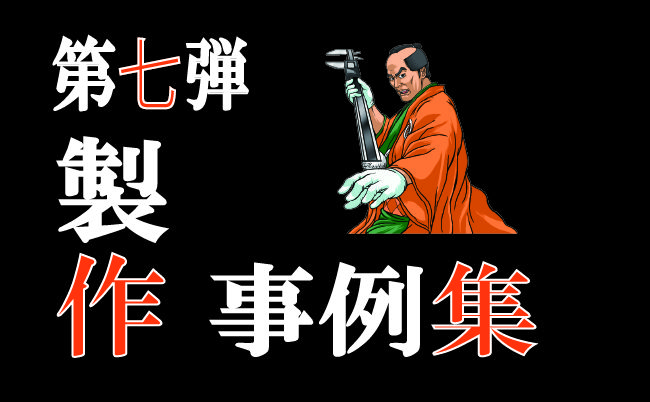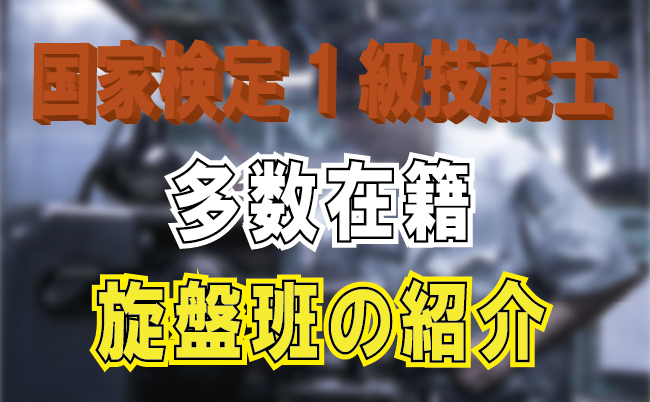複合加工機とは?旋削とマシニングを1台で実現する工作機械の魅力
近年、製造業における生産性向上と工程の効率化が求められる中、複合加工機(ターニングセンタ)はそのニーズに応える革新的な工作機械として注目を集めています。
この機械は、旋削(旋盤)加工とマシニング(フライス)加工を1台で行えるハイブリッド機能を備え、多工程の加工を連続的に実施可能にします。
これにより、段取り替えの手間や精度低下のリスクを抑え、製造現場の生産性を大幅に向上させることができます。
本記事では、複合加工機の基本的な仕組みや特徴、導入によるメリットについて詳しく解説します。
これからの製造現場において、複合加工機がどのように活用されているのか、その実力と可能性を探っていきましょう。
複合加工機とは
複合加工機とは、一台の工作機械で複数の加工工程を同時に、あるいは連続して行うことができる機械を指します。
具体的には、旋削加工、フライス加工、穴あけ、タッピング、ネジ切りなど、従来は異なる機械で行っていた工程を、一台で完結させることが可能です。
従来の加工方法では、部品の製作には旋盤での旋削、フライス盤での切削、ボール盤での穴あけといったように、それぞれの機械を使い分ける必要がありました。
このため、部品の段取り替えや運搬、位置合わせの手間が多く、作業効率が低下し、加工精度にも影響することがありました。
複合加工機ではこれらの問題を解決し、効率的かつ高精度な加工を実現します。
複合加工機の大きな特徴の一つは、「段取り替えの削減」です。
一度ワークを機械に固定すれば、複数工程の加工を連続して行うことができるため、従来必要だった部品の移動や位置合わせが不要になります。
これにより、作業時間の短縮だけでなく、加工誤差の発生リスクも低減できます。
また、複合加工機はCNC(コンピュータ数値制御)を備えているため、加工プログラムに従って自動で工具を動かすことが可能です。
これにより、複雑な形状の加工や高精度の加工も自動化でき、熟練技術者に依存する部分を減らすことができます。
さらに、多軸制御機能も複合加工機の重要な特徴です。
一般的な複合加工機は3軸以上の制御が可能で、5軸以上の機種も存在します。
多軸制御により、ワークを回転させながら複数面を同時に加工することが可能で、従来では不可能だった自由曲面や複雑形状の加工も一度の段取りで完了させることができます。
これにより、航空宇宙部品や医療用インプラント、自動車の精密部品など、高精度かつ複雑な部品の加工に最適です。
また、複合加工機は工具交換やチップ処理、冷却液供給といった加工環境の自動化も特徴です。
自動工具交換機構により、旋削工具やフライス工具、ドリルなどを自動で切り替えられるため、加工中の段取り替えを最小化できます。
さらに、切削中に発生する熱や切りくずを適切に処理する冷却・潤滑システムや自動チップ排出装置を備えており、加工精度を維持しながら工具寿命を延ばすことができます。
総じて、複合加工機は「多機能性」「高精度」「効率性」を兼ね備えた工作機械であり、現代の製造業における生産性向上と品質安定化を支える重要な役割を果たしています。
一台で複数の工程をこなせることから、試作段階から量産段階まで幅広く活用可能であり、多品種少量生産や高精度部品の製造において、従来の工作機械に比べて圧倒的なメリットを発揮するのです。
複合加工機の歴史的背景
複合加工機の誕生と発展は、工作機械の自動化とCNC(コンピュータ数値制御)技術の進化と密接に関わっています。
従来、部品加工は旋盤やフライス盤、ボール盤など、用途ごとに異なる機械を使い分けるのが一般的でした。
この方法では、ワークの段取り替えや移動、位置合わせに多くの時間を要し、作業効率の低さと加工精度のばらつきが課題となっていました。
1950年代から1960年代にかけて、産業の高度化や精密部品需要の増加に伴い、これらの課題を解決するための新しい工作機械の開発が始まりました。
1960年代には、CNC制御技術の登場が複合加工機発展の大きな契機となりました。
CNCにより、機械の各軸の動きや工具の回転をコンピュータで制御できるようになり、従来では人手に頼っていた複雑な加工が自動化されました。
これにより、旋削、フライス加工、穴あけなど複数工程を一台で実現する構想が現実味を帯び、複合加工機の原型となる「複合旋盤」が誕生しました。
当初は、単純な二工程の組み合わせが中心でしたが、次第に多機能化・高精度化が進みました。
1970年代から1980年代にかけては、多軸制御技術の進展とともに、複合加工機の機能は飛躍的に向上しました。
特に、5軸制御やツールタレット自動交換機構の導入により、従来では不可能だった自由曲面や複雑形状の部品加工が可能になりました。
この時期、航空宇宙産業や自動車産業での高精度部品の需要が急増したことも、複合加工機の普及を後押ししました。
従来は熟練技術者に依存していた加工も、CNC制御によって誰でも再現性の高い加工が可能となり、製造現場の効率と品質が大幅に向上しました。
1990年代以降は、ロボットや自動搬送装置との連携が進み、複合加工機は単なる工作機械から生産ラインの中核となる存在へと変貌しました。
ワークの自動供給、工具管理、加工中の状態監視が統合され、無人運転や夜間稼働も可能となりました。
さらに21世紀に入ると、IoTやAI技術が導入され、複合加工機の稼働状況や加工条件をリアルタイムで最適化することが可能となり、より高度な自動化・効率化が進展しています。
現在、複合加工機は試作から量産まで幅広く活用されており、自動車部品、航空宇宙部品、医療機器、精密機械部品など、多種多様な分野で不可欠な存在となっています。
歴史的には、工作機械の自動化技術の発展、CNC制御の導入、多軸加工技術の向上が段階的に積み重なった結果として、現代の複合加工機の高性能化・多機能化が実現しているのです。
複合加工機の構造と機能
主軸と工具機構

複合加工機の加工性能を左右する最も重要な要素の一つが「主軸」と「工具機構」です。
主軸はワークや工具を回転させる中心的な部品であり、加工の正確さや表面品質、加工速度に直結します。
複合加工機では、旋盤機構とマシニングセンタ機構が一体化されているため、主軸はワークの回転だけでなく、工具の回転も制御することがあります。
このため、高い剛性と振動吸収性が求められ、加工中に発生する微小な振動や熱変形を最小限に抑える設計が施されています。
特に高速加工や硬材加工では、主軸の精度が加工精度に直結するため、ベアリング構造や軸受けの配置、冷却方式などが高度に工夫されています。
主軸の制御は、複合加工機のCNCシステムによって精密に行われます。
旋削ではワークを回転させ、フライス加工では工具を回転させる必要があり、それぞれ最適な回転速度やトルクが要求されます。
これらの条件はワーク材質や加工深さ、切削速度に応じて変更されます。
最新の複合加工機では、主軸回転数やトルクをリアルタイムで監視し、自動で最適化する機能を持つものもあり、加工の安定性と精度向上に貢献しています。
工具機構も複合加工機の性能を左右する重要な要素です。
複合加工機は一度の段取りで複数の加工を行うため、旋削工具、フライス工具、ドリル、タップなど、異なる工具を効率的に切り替える必要があります。
このため、ツールタレットやスピンドル自動交換機構(ATC)が備えられています。
ATCは多数の工具を保持し、プログラムに従って必要な工具を迅速かつ正確に切り替えることが可能です。
工具交換速度や位置精度も加工効率に大きく影響するため、高速で正確な切替が可能な設計になっています。
さらに、工具の取り付け精度も重要です。
複合加工機では工具と主軸の間にわずかな隙間や振れが生じるだけで加工精度に影響するため、工具ホルダーやスピンドル端面の精密加工が施されています。
また、工具摩耗や破損を検知するセンサーを搭載する機種もあり、加工中の異常を即座に検出して停止することで、ワークや機械の損傷を防止します。
冷却と潤滑も主軸・工具機構の安定稼働に不可欠です。
加工中に発生する熱は主軸の膨張や工具の摩耗を引き起こすため、主軸冷却機構や工具冷却ノズルを用いて温度管理を行います。
さらに、潤滑油やグリースによる摺動部の摩耗抑制により、精度維持と機械寿命の延長を図ります。
これらの機能により、複合加工機は長時間の高精度加工でも安定した性能を発揮できるのです。
総じて、主軸と工具機構は複合加工機の心臓部であり、加工精度、効率、工具寿命、安定稼働に直結します。
高精度かつ複雑な部品を一度の段取りで加工するためには、主軸の剛性・回転精度・トルク制御と、工具機構の自動交換精度・摩耗管理・冷却潤滑性能が不可欠であり、これらが高度に統合されて初めて複合加工機の真価が発揮されます。
多軸制御と加工範囲
複合加工機の大きな特徴の一つは、多軸制御機能による加工範囲の拡張です。
従来の工作機械では、ワークを一方向からしか加工できず、複雑な形状の部品を仕上げるには複数の段取りや機械の切り替えが必要でした。
しかし、複合加工機は3軸制御を基本とし、5軸制御やそれ以上の多軸制御を備えた機種も存在します。
多軸制御により、ワークを回転させたり傾けたりしながら工具を動かすことができ、従来の方法では難しかった自由曲面や複雑形状の加工も、一度の段取りで完了させることが可能です。
多軸制御は、X・Y・Zの直線方向の移動に加え、回転軸(A軸、B軸、C軸など)を組み合わせることで、ワークや工具の姿勢を自由に制御できる点が特徴です。
例えば、5軸制御の場合、工具を傾けながら加工することで、通常の3軸加工では到達できない凹部や傾斜面を一度で加工できます。
これにより、複雑な形状の航空機部品、医療用インプラント、自動車部品など、高精度かつ難易度の高い部品加工も効率的に行うことができます。
多軸制御によってワークの再セットアップが不要になるため、加工誤差の蓄積も抑制され、部品精度の向上に大きく寄与します。
さらに、多軸制御は加工範囲の柔軟性を飛躍的に向上させます。
従来の単軸や3軸加工では、ワークの位置を変更する必要がある箇所でも、多軸制御では機械が自動でワークや工具の角度を調整するため、段取り替えを減らすことができます。
これにより、生産時間の短縮や作業者の負荷軽減、工具摩耗の均一化が可能となります。
また、CNC制御によって加工プログラムを精密に設定できるため、同一条件での繰り返し加工も容易で、高精度・高品質の量産にも対応できます。
多軸制御により実現されるもう一つの利点は、加工の一体化です。
ワークを一度固定すれば、複数の面や角度の加工を連続して行えるため、工程の削減や製品精度の向上が可能です。
特に航空宇宙部品や精密医療機器、ギアやシャフトなどの自動車部品では、この一体化加工が大きなメリットとなります。
また、多軸制御を活用することで、従来の加工方法では必要だった治具や補助装置の数を減らすことも可能であり、作業効率とコスト削減の両立を実現します。
総じて、多軸制御と広い加工範囲は、複合加工機の最大の強みであり、高精度・高効率・多品種少量生産に対応できる理由の一つです。
従来の単機能工作機械では困難だった複雑部品の加工も、段取り替えなしで行えることにより、製造業における生産性と品質の向上を大きく支えています。
冷却・潤滑・チップ処理機能
CNC旋盤において加工精度と生産効率を高めるためには、主軸や工具と同様に「冷却」「潤滑」「チップ処理」の各機能が欠かせません。
これらは一見補助的な機能のように思われがちですが、実際には工具寿命の延長、加工面品質の安定、さらには機械全体の稼働率維持に直結する重要な役割を担っています。
特に高精度加工や長時間の連続運転を行うCNC旋盤では、これらの機能が十分に整備されているかどうかで製品の品質が大きく左右されます。
以下では、それぞれの機能について詳しく解説します。
1. 冷却機能
切削加工では工具とワークの接触部において摩擦熱が発生し、その温度は数百度に達することがあります。
過剰な熱は工具の摩耗を加速させ、加工精度の低下やワーク材質の変質を引き起こす要因となります。
そのためCNC旋盤には、切削点に切削液(クーラント)を供給して熱を効率的に逃がす冷却機能が組み込まれています。
冷却方式には大きく分けて「外部給油式」と「スルークーラント方式」があります。
外部給油式はノズルから切削液を噴射して冷却する一般的な方法で、広範囲を均等に冷やすのに適しています。
一方でスルークーラント方式は、工具の内部に設けられた穴から切削液を直接切削点に送り込む方式で、高速切削や深穴加工など切りくず排出が難しい場面で特に効果を発揮します。
2. 潤滑機能
潤滑の目的は、摩擦を低減し工具や主軸の寿命を延ばすことにあります。
切削液自体には冷却効果と同時に潤滑効果も含まれており、これにより切削抵抗が低減し、加工面の仕上げ精度が向上します。
また、旋盤本体の摺動面やボールねじ、リニアガイドなどの機械要素には、自動潤滑装置が備えられ、定期的にオイルが供給される仕組みが一般的です。
これにより部品同士の摩耗を防ぎ、機械全体の精度維持と長期稼働が可能になります。
潤滑不足は異音や振動の原因となり、最悪の場合は主軸焼き付きなど重大な故障につながるため、潤滑機能は冷却と並んで重要な役割を担っています。
3. チップ処理機能
切削加工において発生する切りくず(チップ)は、加工の進行を妨げたり、工具破損や表面傷を引き起こす原因となります。
CNC旋盤には、チップコンベアやチップフラッシングといった機能が備えられ、効率的に切りくずを排出・回収できるよう工夫されています。
チップコンベアはベルトやスクリューで切りくずを外部に搬出する仕組みで、大量生産において必須の装置です。
特にアルミや銅のように粘着性の高い切りくずや、ステンレスのように絡みやすい切りくずは、処理を誤るとトラブルの原因となるため、適切な搬送方式を選択することが重要です。
また、クーラントの強力な噴射により切りくずを切削点から押し流す「チップフラッシング」も有効で、工具摩耗の低減と加工精度の安定化につながります。
まとめ
冷却・潤滑・チップ処理機能は、CNC旋盤における「縁の下の力持ち」ともいえる存在です。
これらが適切に機能して初めて、主軸や工具の能力を最大限に発揮でき、高精度で安定した加工が実現します。
逆に言えば、これらの補助機能が不十分であれば、工具寿命の短縮や加工不良、機械故障といった問題が頻発し、生産性の低下を招いてしまいます。
そのためCNC旋盤を運用する際には、定期的なメンテナンスや使用条件に応じた最適化が不可欠です。
制御装置
 /p>
/p>
CNC旋盤における制御装置は、加工全体の「頭脳」にあたる存在であり、旋盤の動作を正確かつ効率的に制御する役割を担います。
制御装置は、コンピュータ数値制御(CNC: Computer Numerical Control)の名の通り、数値データをもとに機械の各部を指令・監視する仕組みで構成されています。
ここでは、CNC旋盤の制御装置の基本構造と機能、操作方法、さらに近年の進化について詳しく見ていきます。
まず、制御装置の中核を担うのが「NC装置」と呼ばれるコンピュータユニットです。
ここにはCPUやメモリ、演算回路が搭載されており、オペレーターが入力したプログラム(GコードやMコードなど)を解釈し、送り速度や主軸回転数、工具の移動経路を具体的な制御信号に変換します。
この数値制御プログラムは、直線補間や円弧補間といった基本的な補間機能を用いて工具経路を正確に導き、ワークに対して高精度な切削を実現します。
制御装置が優秀であるほど、仕上がりの寸法精度や面粗度が向上し、加工効率の最適化も可能となります。
次に、制御装置には「操作パネル」が備わっています。
ここにはディスプレイ、テンキー、操作ボタン、ジョグダイヤルなどが配置され、オペレーターが直感的に機械を扱えるよう工夫されています。
ディスプレイにはプログラム内容や座標値、加工進捗、エラー情報などが表示され、加工状況をリアルタイムに監視できます。
また、最近の装置ではタッチパネル式の大型画面が普及しており、グラフィカルなシミュレーション表示や対話型プログラミング機能によって、初心者でも扱いやすい環境が整えられています。
さらに、制御装置は「サーボ制御システム」と密接に連携しています。
工具台や送り機構を駆動するモーターはサーボモーターが採用されており、その回転角度や位置をフィードバック制御によって常に補正しながら動作します。
この閉ループ制御により、ミクロン単位での位置決めが可能となり、高精度な切削加工が実現できるのです。
また、主軸モーターの制御も同様に行われ、一定回転数だけでなく一定切削速度制御(CSS制御)なども可能となります。
これにより、ワーク径が変化しても常に安定した切削条件を維持でき、工具寿命の延長や加工品質の均一化につながります。
制御装置のもう一つの重要な機能が「安全管理と異常検知」です。
過負荷や工具干渉、プログラムミスなどが発生した場合、制御装置は即座に異常を検知し、緊急停止やアラーム表示を行います。
これにより、機械やワークの破損、さらには人身事故を未然に防ぐことができます。
近年では、AIやIoT技術を活用して加工データを常時モニタリングし、異常の予兆を検出する「予知保全」も実用化されつつあります。
加えて、制御装置は生産効率の最適化にも貢献しています。
例えば、複雑な形状加工では「マクロプログラム」や「サブプログラム」を駆使することで、同一形状の繰り返し加工やパラメトリック制御が容易になります。
また、他の工作機械やロボットとの通信機能を備えた制御装置であれば、FMS(フレキシブル生産システム)やスマートファクトリーへの統合も可能です。
これにより、単なる旋盤加工機ではなく、生産ライン全体の中で高度に連携するシステムの一部として機能するようになっています。
総じて、CNC旋盤の制御装置は、単に機械を動かすための装置にとどまらず、「加工品質」「安全性」「効率性」を同時に担保する極めて重要な要素です。
今後はさらにAIによる自動最適化やクラウド連携が進み、オペレーターの負担を軽減しつつ、高度で安定した加工が実現されていくことが期待されています。
複合加工機の活用分野
航空宇宙分野での活用
航空宇宙分野では、複雑で高精度な部品を効率的に製造する必要があり、複合加工機の導入がますます重要になっています。
航空機や宇宙機器に使用される部品は、極めて高い強度・耐熱性・耐腐食性が求められるため、チタン合金やニッケル基超合金など、加工が難しい材料が多く使用されます。
従来は旋盤やマシニングセンタなど複数の加工機を使い分けて製造していましたが、工程ごとのワーク取り外しや位置決めによる誤差が発生しやすく、寸法精度や表面品質の安定が課題でした。
複合加工機は、旋削・フライス・穴加工などを一台で行えるため、こうした課題を解消し、高精度で複雑な部品の一貫加工を可能にします。
航空機エンジン部品は、代表的な複雑部品の一つです。
タービンブレードやコンプレッサーディスクは、曲線や薄肉構造を持ちながら、高温環境下でも変形しない強度が必要です。
複合加工機は、多軸制御と高剛性構造により、旋削とミーリングを組み合わせた複雑形状の加工を一度のセットアップで完了できます。
これにより、加工精度の向上だけでなく、段取り替えによる誤差や工程時間の削減も実現できます。
また、航空機の燃料系統や油圧系統部品に使われるチタン合金の加工も、複合加工機の高剛性と最適化された切削条件によって、工具摩耗を抑えつつ効率的に加工できます。
さらに、航空宇宙分野では軽量化が不可欠であり、部品には肉抜きや格子構造が施されることが多くあります。
複合加工機は高精度な輪郭加工や穴加工を一貫して行えるため、軽量化部品の製造にも適しています。
例えば、航空機の機体構造部材や宇宙機のフレーム部品など、薄肉かつ複雑形状の部品も安定して加工可能です。
これにより、軽量化と高強度の両立が求められる航空宇宙産業において、複合加工機は不可欠な設備となっています。
航空宇宙分野では、製造後の信頼性も非常に重要です。
複合加工機による一貫加工は、複数工程にわたる位置ずれや寸法誤差を最小限に抑えられるため、品質の安定化や不良品の削減につながります。
また、CAD/CAMデータとの連携により、設計通りの高精度加工を短時間で行える点も航空宇宙産業にとって大きなメリットです。
さらに、最新の複合加工機はIoTや自動化技術と連動できるため、スマートファクトリー環境での活用も進んでおり、航空宇宙産業全体の生産性向上に貢献しています。
総じて、航空宇宙分野における複合加工機の活用は、「高精度加工」「複雑形状への対応」「軽量化部品の製造」「工程短縮による効率化」という複数のメリットを同時に実現する点で非常に価値があります。
今後も航空機の高効率化や宇宙開発の進展に伴い、複合加工機の重要性はさらに高まることが予想されます。
自動車分野での複合加工機活用

自動車産業では、複合加工機の導入が生産効率と部品精度の向上に大きく貢献しています。
自動車部品は多様で複雑な形状を持つものが多く、従来は旋盤やフライス盤など複数の機械を使用して段階的に加工する必要がありました。
例えば、エンジンブロックやトランスミッションケース、クランクシャフト、カムシャフトなどは高精度な寸法管理と表面仕上げが求められ、加工後の検査や再調整が欠かせませんでした。
しかし、複合加工機を導入することで、旋削・フライス・穴加工・ねじ切りといった複数工程を一台で行えるため、工程間の誤差を最小化し、高精度な部品を効率的に生産できるようになりました。
特にクランクシャフトやカムシャフトのような複雑な回転部品は、複数の段取り替えを伴う従来加工では寸法精度の維持が難しく、加工時間も長くかかっていました。
複合加工機では、ワークを一度固定するだけで旋削とミーリング、穴加工を連続的に行えるため、加工精度の向上だけでなく生産リードタイムの大幅な短縮も可能です。
また、自動車産業では大量生産が求められる一方で、近年は電動化やハイブリッド化に伴い多品種少量生産への対応も必要となっています。
複合加工機はプログラム変更や工具交換を迅速に行えるため、従来の専用機よりも柔軟な生産体制を構築でき、試作から量産まで幅広く対応できます。
さらに、自動車の軽量化や燃費向上の観点から、アルミニウムやチタン合金などの難削材を使用した部品の加工が増えています。
複合加工機は高剛性と高精度制御により、これらの難削材でも安定して加工でき、工具摩耗の抑制や加工品質の維持に寄与します。
例えば、モーターケースや電池パック周辺部品、シャシーの一部構造材など、軽量で複雑な形状が要求される部品も複合加工機で効率的に生産可能です。
また、複合加工機による工程集約は、部品組み立て後の不具合削減にも直結します。
従来は別々の機械で加工することで生じやすかった寸法ズレや穴位置の誤差を最小化できるため、組み立て精度の向上や歩留まり改善に貢献します。
これにより、品質保証コストの低減や市場投入までのリードタイム短縮も実現できます。
総じて、自動車分野における複合加工機の導入は、「高精度化」「生産効率化」「多品種少量生産対応」「難削材加工の効率化」といった多方面のメリットをもたらします。
特に電動車両やハイブリッド車の普及に伴い、多様な新部品の短納期対応が求められる現代の自動車産業において、複合加工機は不可欠な設備として広く活用されています。
複合旋盤の加工品の見積り依頼ならアスクへ
試作品や小ロットの加工も大歓迎!
特に手のひらサイズの部品製作を得意としています。
アスクなら、試作品のお見積もりが最短1時間で可能!!
お気軽にお問い合わせください。
試作全国対応!
簡単・最短1時間お見積り
他、ブログ記事もご覧ください♪
動画の投稿もしておりますので良ければご覧ください♪