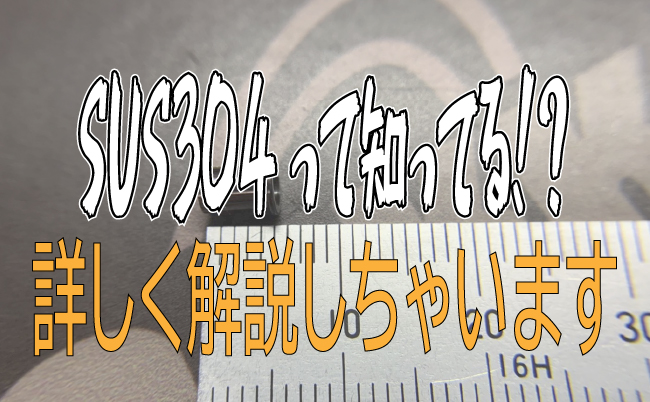SUS304とは?ステンレス鋼のスタンダードを徹底解説
SUS304は、ステンレス鋼の中でも最も広く使用されている代表的な材料です。
正式には「JIS G4303」に規定されたオーステナイト系ステンレス鋼であり、「18Cr-8Niステンレス」とも呼ばれています。
これは、主成分にクロム(Cr)を約18%、ニッケル(Ni)を約8%含むことを意味し、非常にバランスの取れた特性を持っているため、多種多様な産業分野で使用されています。
SUS304とは
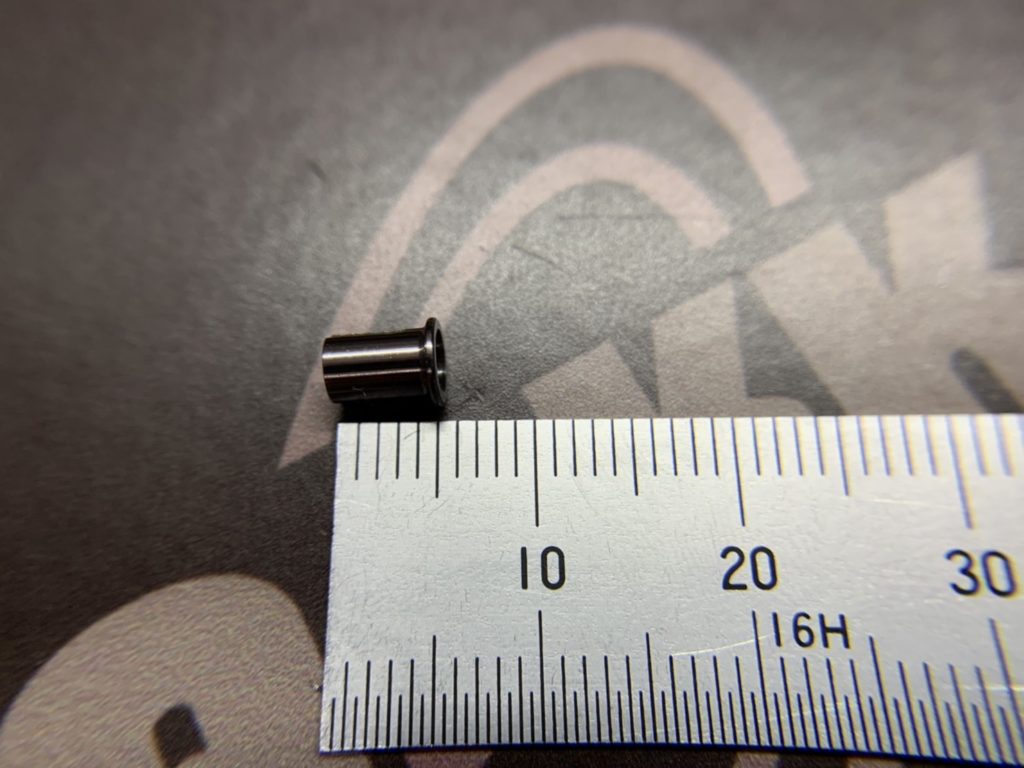
SUS304は、ステンレス鋼の中でも最も広く使用されている代表的な材料です。
正式には「JIS G4303」に規定されたオーステナイト系ステンレス鋼であり、「18Cr-8Niステンレス」とも呼ばれています。
これは、主成分にクロム(Cr)を約18%、ニッケル(Ni)を約8%含むことを意味し、非常にバランスの取れた特性を持っているため、多種多様な産業分野で使用されています。
まず「SUS」とは、「Steel Use Stainless」の略称で、JIS(日本産業規格)で使用されている呼称です。
SUS304の「304」は、アメリカ鉄鋼協会(AISI)が定めた番号と一致しており、国際的にも「AISI 304」として通用します。
海外規格では、ISOやENでは「X5CrNi18-10」などの記号で示されることもあります。
これにより、国内外で同じような性能の材料を選定・利用することが可能になります。
SUS304の最大の特長は、その耐食性と加工性の高さです。
クロムは鋼の表面に非常に薄い酸化皮膜(不働態皮膜)を形成し、これが錆を防ぐ役割を果たします。
また、ニッケルを加えることでオーステナイト組織が安定し、延性や靱性が向上します。
さらに、磁性を帯びにくくなるのもオーステナイト系の特徴です(ただし、加工などでわずかに磁性が出ることがあります)。
産業用途においては、SUS304は建築資材、家庭用品、食品機械、医療器具、化学設備など多岐にわたって使用されています。
一般的な使用環境であれば、そのままで十分な耐食性を持ち、表面処理なしでも外観を維持できます。
一方で、塩分や強酸などにさらされる環境では腐食の可能性があるため、必要に応じてより耐食性の高いSUS316などに置き換える判断が求められます。
また、SUS304は「万能型のステンレス」とも称され、コストと性能のバランスが取れている点でも評価されています。
非常に多くの規格品や部品がSUS304で供給されており、入手性の良さもメリットの一つです。
まとめると、SUS304はその耐食性、加工性、溶接性、機械的強度、意匠性の高さにより、現代の製造業・建築・家庭分野において不可欠な材料となっています。
最初に選定すべきステンレスとして、あるいは基準となる存在として位置付けられているのです。
成分とその役割
SUS304はオーステナイト系ステンレス鋼であり、その優れた特性は主に含有されている化学成分に由来します。
主成分は鉄(Fe)ですが、それに加えてクロム(Cr)とニッケル(Ni)が中心となっており、これらがSUS304の特性を決定づけています。
そのほかにも、マンガン(Mn)やシリコン(Si)、炭素(C)、リン(P)、硫黄(S)などが微量に含まれています。
それぞれの元素がどのような役割を果たしているのかを詳しく見ていきましょう。
クロム(Cr)約18%
クロムは、SUS304の耐食性を決定づける最重要成分です。
鉄にクロムを10.5%以上添加すると、表面に「不働態皮膜」と呼ばれる非常に薄くて安定な酸化被膜が自然に形成されます。
この皮膜が酸素や水分との反応を防ぎ、錆の発生を抑えます。
SUS304ではこのクロムが約18%と比較的多く含まれているため、非常に高い耐食性能を発揮します。
ニッケル(Ni)約8%
ニッケルは、ステンレス鋼の組織をオーステナイト型に安定化させる役割を持ちます。
オーステナイト構造は室温でも安定しており、延性や靱性が高く、常温での加工性が大変良好です。
また、ニッケルの添加によって非磁性が実現されるため、磁気を嫌う用途にも適しています。
さらに、クロムとの相乗効果で耐食性も一層向上します。
炭素(C)最大0.08%
炭素は鋼の硬度を高める要素ですが、SUS304では炭素含有量を低く抑えることで耐粒界腐食性(溶接後の腐食に対する耐性)を確保しています。
炭素が多すぎるとクロムと結びついて「クロム炭化物」を形成し、結果として周囲のクロム量が不足し、耐食性が低下してしまいます。
SUS304ではこの炭化物の生成を抑えるため、炭素は0.08%以下と制限されています。
マンガン(Mn)約2%以下
マンガンは脱酸剤として使用され、鋼中の酸素と結合して不純物を取り除く役割を果たします。
また、オーステナイト相の安定にも多少寄与し、ニッケルの代替として一部機能します。
SUS304では微量添加されていますが、構造への影響は限定的です。
シリコン(Si)約1%以下
シリコンもマンガンと同様、脱酸剤としての役割が主であり、鋼の製造過程で重要です。
また、電気的特性や高温下での酸化抵抗性にもわずかに貢献しています。
リン(P)・硫黄(S)
これらは通常不純物とされ、含有量は極力低く抑えられます。
リンは鋼を脆くする性質があり、硫黄は加工性を高める面もあるものの、耐食性を損なうため、SUS304では基本的に厳しく制限されています。
これらの成分は、厳格な化学組成の管理のもとに製造されており、そのバランスによって高い耐食性、良好な加工性、非磁性、コスト効率の良さといった特性を生み出しています。
また、同じオーステナイト系であっても成分比の違いによってSUS316やSUS310などの派生材が存在し、それぞれ特化した性能を持っています。
SUS304の成分設計は、まさに汎用性と安定性を追求した理想的なステンレス鋼のモデルケースと言えるでしょう。
機械的性質の特徴
SUS304は、その高い耐食性や加工性だけでなく、優れた機械的性質も評価される材料です。
特に、強度、延性、靱性、硬度などのバランスが取れており、幅広い用途で活躍しています。
ここではSUS304の主要な機械的特性について、詳しく解説します。
引張強さ(Tensile Strength)
SUS304の引張強さはおおよそ520~750 MPa(メガパスカル)です。
これは、材料が破断するまでに耐えられる最大の力を示しており、一般的な炭素鋼(例えばSS400が約400MPa)と比較しても十分に高い強度を持っていることが分かります。
また、冷間加工(曲げ加工やプレス成形など)を施すことで、さらに強度を向上させることも可能です。
耐力(Yield Strength)
SUS304の耐力(0.2%耐力)は約205 MPa程度とされており、これは永久変形が始まる点を表します。
一般的にオーステナイト系ステンレスは明確な降伏点がないため、0.2%の塑性変形を基準としています。
この値からもわかるように、SUS304は高い強度と適度な柔軟性を併せ持つ材料です。
伸び(Elongation)
SUS304は伸び率が45%以上と非常に高く、これは材料が破断するまでにどれだけ伸びるかを示す指標です。
高い伸び率は、優れた延性(=加工時に割れにくい)を意味します。
そのため、プレス加工・深絞り加工・曲げ加工など、塑性変形を伴う工程に非常に適しています。
これはSUS304が建材や厨房機器、家庭用品などの成形加工部品に多用される理由のひとつです。
硬度(Hardness)
焼入れを行わないSUS304のビッカース硬度(HV)は、約160~200HV程度です。
これは焼入れ鋼に比べてやや低いものの、冷間加工を加えることで200HVを超えることも可能です。
加工硬化が生じることで表面が硬くなり、耐摩耗性が向上するという利点があります。
一方で、硬度が上がると割れやすくなるため、加工工程では注意が必要です。
靱性(Toughness)
SUS304は低温下でも靱性を保ち、極低温(−196℃程度)でも脆性破壊を起こしにくい特性を持ちます。
これにより、極低温での使用(例えば液体窒素や液化ガスのタンクなど)にも対応できるため、極低温機器や冷凍装置などでも採用されています。
加工硬化性
SUS304は加工硬化性が高い材料です。
つまり、曲げや絞り加工などで塑性変形を加えると、素材が硬化し強度が上がります。
これにより、成形後の強度を高めることができるという利点がありますが、一方で過度な加工をすると割れや亀裂が発生する恐れがあるため、工程設計に注意が必要です。
特に、冷間圧延材ではこの傾向が顕著です。
以上のように、SUS304は強度・延性・靱性・加工性といった機械的性質のバランスが非常に優れており、多目的な汎用材料としての地位を確立しています。
このバランスの良さが、家庭用品から産業機械、建築構造材に至るまで幅広く採用される理由となっているのです。
代表的な使用用途

SUS304は、「最も汎用的なステンレス鋼」と称されるほど、多様な用途に使用されている材料です。
その理由は、高い耐食性・良好な加工性・美しい外観・非磁性など、バランスのとれた特性を持っているからです。
ここでは、SUS304が活躍している代表的な分野をカテゴリ別にご紹介します。
厨房機器・家庭用品
もっとも日常的に目にするSUS304の用途のひとつが、キッチン周りの製品です。
・シンク・調理台・作業台:水回りでの錆に強く、清掃性も高いため、家庭用から業務用まで幅広く使用されます。
・鍋・フライパン・カトラリー類:熱や酸に強く、食材にも影響を与えにくいことから、食品に触れる場面で活躍します。
・魔法瓶・水筒・ケトル:衛生的で、かつ温度変化にも耐えられるため、真空断熱容器の内外装にも最適です。
このように、安全性・清潔性・耐久性が求められる製品に最適な素材です。
建築・インテリア分野
SUS304はその美観性と耐候性から、建築分野でも重宝されています。
・エレベーターの内装パネル
・ビルの手すり・外装材
・室内の金物類(ドアノブ・ヒンジなど)
特に都市部では排ガスや酸性雨による腐食が問題になりますが、SUS304は大気中での耐食性に優れているため、長寿命を実現します。
また、ヘアライン仕上げや鏡面仕上げなど多彩な表面処理が可能なため、意匠性を重視するデザインでも多く採用されています。
医療・化学機器
医療・化学分野では、耐薬品性・非磁性・衛生性が求められます。
・医療用トレー・器具類
・化学実験器具・反応容器
・製薬機械の部品
SUS304は磁性を帯びにくく、生体との相性も悪くないため、直接人体に触れるわけではない部品や器具によく使われています。
ただし、より耐食性や耐薬品性が必要な場合は、SUS316などの高ニッケル材が選ばれることもあります。
自動車・輸送機器分野
・排気系部品(マフラー、触媒カバーなど)
・トレーラーやタンクローリーの容器部分
・内装部品や装飾トリム
SUS304は高温環境にも比較的強く、耐熱性と耐腐食性のバランスが良いため、排気システムや大型輸送機器にも適用されます。
また、鉄道車両の外装材や内部構造材にも使用されており、軽量化と耐久性の両立に貢献しています。
産業機械・装置
産業用設備にも多く用いられています。
・食品加工ラインの機械部品
・化学プラントの配管・タンク
・クリーンルーム機器
食品や医薬品など、異物混入が許されない現場では、洗浄性の高いSUS304が必須です。
また、耐久性が高く長期使用にも耐えるため、ライフサイクルコストの低減にも寄与します。
まとめ
このようにSUS304は、食品、建築、医療、自動車、産業機械といった多岐にわたる分野で活躍しています。
材料の持つ特性が広範囲な要求に応えられるため、「迷ったらSUS304」と言われるほど定番の素材となっているのです。
コストと性能のバランスに優れるこの材料は、今後も変わらず、幅広い産業の基盤を支える存在であり続けるでしょう。
SUS304の加工性と注意点
溶接性とその特徴
SUS304は優れた溶接性を持つ材料として広く知られており、TIG溶接やMAG溶接など、さまざまなアーク溶接法に対応可能です。
この特性は、建築分野や配管、産業機械など、溶接構造物が多用される分野で非常に重宝されます。
ただし、溶接時にはいくつかの注意点も存在し、それらを正しく理解し対応することが、品質の高い製品製作には不可欠です。
溶接性の基本的な特徴
SUS304はオーステナイト系ステンレス鋼であり、結晶構造上、常温でフェライトやマルテンサイトのような脆い相を形成しにくく、割れに対する抵抗性が高いのが特徴です。
これにより、ひび割れ(ホットクラックや冷却割れ)を起こしにくいため、初心者でも比較的溶接しやすい材料として扱われています。
また、炭素量が0.08%以下と低いため、耐粒界腐食性に優れているのも大きな利点です。
さらに、必要に応じて低炭素仕様のSUS304L(炭素量0.03%以下)を使用することで、溶接後の耐食性がさらに向上します。
溶接方法の例
代表的な溶接方法には以下のようなものがあります。
・TIG溶接(アルゴン溶接)
最も一般的に使われる手法で、特に薄板や美観を求められる部品に最適です。
熱影響部が小さく、変形も抑えやすいという利点があります。
・MAG溶接(半自動溶接)
厚板や大量生産に向いた方法で、効率よく施工できるのがメリットです。
ただし、スパッタや仕上がり面の粗さに注意が必要です。
・レーザー溶接や電子ビーム溶接
高精度を求める場面で使用され、熱影響を極限まで小さく抑えることが可能です。
熱影響部とその管理
溶接時に発生する熱影響部(HAZ:Heat Affected Zone)は、母材に近接する部分で、微細構造が変化しやすく、場合によっては腐食しやすくなります。
特に高温にさらされたSUS304ではクロム炭化物の析出(結晶粒界にクロムが偏在)が起こり、粒界腐食の原因となります。
この対策としては以下が挙げられます。
・低炭素鋼(SUS304L)の使用
・溶接後の固溶化熱処理による組織の再均一化
・適切な溶接条件(電流・速度・入熱)の設定
・溶接後の酸洗いやパッシベーション処理で酸化被膜や不純物を除去
これらの対策を講じることで、長期にわたって耐食性の高い溶接構造を実現できます。
応力腐食割れ(SCC)への注意
オーステナイト系ステンレスであるSUS304は、塩化物イオン環境下で応力腐食割れ(SCC)が発生するリスクがあります。
特に溶接によって残留応力が蓄積されやすいため、使用環境が海水・塩分を含む空気・薬品などにさらされる場合には、残留応力の低減措置(例:ショットピーニング、応力除去焼鈍)が推奨されます。
まとめ
SUS304は非常に溶接しやすい材料である一方、熱影響部での腐食リスクや残留応力の管理が重要です。
これらを正しく管理すれば、強度・美観・耐久性を兼ね備えた構造部品を作ることができ、建築、食品、医療、機械分野で長期使用に耐える製品づくりに大きく貢献します。
加工時の注意点(切削・曲げ・深絞り)
SUS304はステンレス鋼の中でも広く利用されており、加工性に優れる材料として認知されていますが、実際の加工現場ではその特性ゆえの注意点や工夫が必要です。
特に切削加工、曲げ加工、深絞り加工といった典型的な加工工程では、材料の硬さや延性、熱伝導性の低さといった性質が大きく影響を及ぼします。
以下に各加工法ごとのポイントを解説します。
切削加工の注意点
SUS304はオーステナイト系ステンレス鋼で、加工硬化性が高く、熱伝導率が低いという特性を持ちます。
このため、切削加工では工具摩耗や切削熱の管理が重要となります。
・工具材質とコーティング:超硬工具やセラミック工具が推奨され、TiAlNなどの耐熱性・潤滑性に優れたコーティングを施すことで寿命が延びます。
・切削条件の最適化:低速・中送りで切り込みをしっかりとることが基本です。軽切削ではなく「食いつかせて切る」スタイルが摩耗抑制につながります。
・切削油の使用:冷却・潤滑・排熱を兼ねた切削油は不可欠です。エマルジョンタイプの水溶性切削液や高性能油性クーラントを選ぶと効果的です。
・バリの発生:バリや焼き付きが発生しやすく、加工後のバリ取り工程も想定しておくことが望まれます。
曲げ加工の注意点
SUS304は比較的高い延性を持ちますが、加工硬化の影響により、曲げ時に割れや反発が起きやすいという一面があります。
・最小曲げ半径の確保:板厚に対して十分な曲げRを取ることが重要です。目安として板厚の1~1.5倍以上の内Rが安全圏です。
・繊維方向の考慮:ロール圧延による素材方向(繊維方向)に対して直角に曲げると割れが生じやすくなります。繊維方向に沿って曲げる方が安全です。
・バネ戻り(スプリングバック)対策:SUS304は加工後にバネ戻りが大きいため、角度や治具設計に補正を加える必要があります。
・割れ防止のための予熱や中間焼鈍:難しい曲げ形状では、事前に中間焼鈍処理を行うことで延性が回復し、割れを防止できます。
深絞り加工の注意点
SUS304は延性があるため、深絞り加工にも対応可能な材料ですが、条件設定や金型設計の良否によって仕上がりが大きく左右されます。
・潤滑管理:深絞りでは高い潤滑性が要求されます。特殊グリースや深絞り専用の油を使用し、摩擦と発熱を最小限に抑えることが成功の鍵です。
・金型クリアランスの最適化:板厚に対して適切なクリアランスを設けることが、しわ・割れの防止に直結します。過小すぎると割れや擦れ、過大すぎるとしわが発生します。
・下工程での加工硬化対策:深絞り途中で材料が加工硬化してしまうと、破断やしわが起きやすくなります。必要に応じて中間焼鈍処理を加え、延性を回復させるのが有効です。
絞り比の制御:1回の絞りでの直径変化率が大きすぎると破断リスクが増します。一般的には絞り比(初径/最小径)を2.0以下に抑え、複数回に分けた工程設計が望まれます。
まとめ
SUS304は多用途に対応できる優れたステンレス鋼ですが、加工工程ではその加工硬化性や低熱伝導性、バネ戻りの大きさなどに注意を払う必要があります。
切削では適切な工具と切削条件、曲げでは方向や半径、深絞りでは潤滑と焼鈍処理が重要です。
これらを理解した上で工程設計すれば、高品質な製品加工が実現できます。
SUS304の機械的性質と使用上の注意

SUS304は、最も代表的なオーステナイト系ステンレス鋼であり、高い強度、延性、耐食性を兼ね備えたバランスの良い素材です。
その機械的特性は、多様な産業分野で活用される要因となっています。
一方で、使用環境や設計上の配慮を怠ると、思わぬトラブルにつながることもあるため、特性と注意点の理解が不可欠です。
機械的性質の概要
SUS304の代表的な機械的性質(焼鈍材)は以下の通りです。
| 性質 | 数値(参考) |
|---|---|
| 引張強さ(MPa) | 520以上 |
| 0.2%耐力(MPa) | 205以上 |
| 伸び(%) | 40以上 |
| 硬さ(HB) | 187以下 |
| 弾性係数(GPa) | 約193 |
これらの数値が示すように、高い延性と靭性を持つ一方で、強度や硬さは中程度です。
特に加工後における「加工硬化」によって強度が著しく向上する特性があります。
冷間加工を加えることで引張強さは600MPa以上に達することもあります。
耐衝撃性と靱性の高さ
SUS304は、低温下でも靱性を保ちやすいという特性があります。
これは、マルテンサイト系やフェライト系ステンレス鋼にはない大きな利点であり、極低温(-196℃)の液体窒素環境などでも破断しにくいという性質を持っています。
このため、極低温タンクや配管、LNG装置などにも採用されています。
また、衝撃を受けた際に割れずに変形して耐える「靭性」にも優れており、圧力容器や建築構造材にも広く使われています。
加工硬化とその対策
SUS304は、加工硬化しやすい材料です。
これは、冷間加工(プレス、曲げ、絞りなど)を加えることで内部組織が変化し、強度が上がる現象です。
この特性を逆に利用して、強度アップが求められる部品では加工硬化状態のまま使用することもあります。
ただし、加工硬化が進むと延性が失われて割れやすくなり、後工程(溶接、再成形など)に悪影響を及ぼす場合もあります。
そのため、必要に応じて中間焼鈍(800~900℃程度)を行い、内部応力を除去し、延性を回復させる処理が重要です。
疲労強度と応力腐食割れの注意点
SUS304は、一般的な機械部品に十分な疲労強度を持ちますが、注意すべきは「応力腐食割れ(SCC)」のリスクです。
・SCCとは:引張応力下で、腐食環境中にあるときに材料が突然割れる現象。
・特に注意が必要な環境:塩化物イオン(Cl⁻)が存在する環境下、60℃以上の高温など。
そのため、高温の塩水環境や温泉水・プール水などでは、耐SCC性の高いSUS316などへの材料変更が推奨されます。
また、部品に残留応力があると割れが進行しやすくなるため、焼鈍処理や応力除去焼鈍を行うことでリスクを軽減できます。
摩耗や衝撃のある用途には工夫が必要
SUS304は耐食性に優れますが、摩耗性や硬さはそれほど高くありません。
したがって、摺動部品や摩耗の激しい箇所で使用する場合は、以下のような対策が必要です。
・表面硬化処理:窒化処理やイオンプレーティングなどで表面硬度を高める。
・硬質コーティングの併用:TiNやDLCなどのコーティングを加えて耐摩耗性を補う。
SUS440Cなど高硬度材への変更:硬さを重視する場合は別種のステンレスに切り替える判断も有効です。
まとめ
SUS304は、高い延性と靭性、優れた加工硬化性、幅広い温度帯での使用可能性など、機械的性質において非常にバランスの取れた素材です。
ただし、加工硬化や応力腐食割れといった固有の弱点もあるため、使用環境や加工条件に応じた工夫が重要です。
これらを踏まえた設計・加工・使用を行うことで、SUS304の性能を最大限に引き出すことができます。
SUS304と他材質の比較
SUS430との比較(フェライト系との違い)
SUS304とSUS430は、どちらも「ステンレス鋼」として広く使われていますが、その組成・特性・用途・価格には大きな違いがあります。
SUS304はオーステナイト系、SUS430はフェライト系に分類され、それぞれの特長が材料選定において重要な判断基準になります。
化学組成の違いとその影響
・SUS304:18%クロム(Cr)+8%ニッケル(Ni)
・SUS430:16〜18%クロムのみ、ニッケルを含まない
SUS430はニッケルが含まれていないため、コストが低く、価格変動にも比較的安定しています。
一方で、SUS304はニッケルを含むことで非磁性・高耐食性・加工性の向上といったメリットがあります。
耐食性の違い
SUS304は、酸性環境や塩分環境にも強く、長期間にわたってサビにくいのが特長です。
これに対してSUS430は、屋内や乾燥環境では問題ありませんが、湿気や塩分の多い環境ではサビやすい傾向にあります。
たとえば、以下のような違いがあります。
| 環境 | SUS304 | SUS430 |
|---|---|---|
| 屋外(海沿い) | ◎(優れた耐食性) | △(腐食リスクあり) |
| キッチン・水回り | ◎(食品衛生適合) | ○(乾燥状態で使用) |
| 高温多湿の工場 | ○ | △(サビが出やすい) |
磁性の違い
・SUS304:基本的に非磁性
・SUS430:強磁性あり
このため、磁石にくっつくかどうかで簡単に判別することも可能です。
磁性の有無は製品の仕様によっては重要です。
たとえば、磁場を避けたい電子機器周辺などではSUS304が好まれます。
加工性・溶接性の違い
SUS304は柔らかく延性に富み、曲げや深絞り加工に向いています。
また、溶接性も高く、熱影響を受けにくい特長があります。
一方、SUS430は硬めで、曲げ加工時に割れやすい傾向があります。
また、溶接性はやや劣り、高温での脆化(475℃脆化)に注意が必要です。
コストと用途の違い
コスト面ではSUS430が有利です。
ニッケルを含まない分、SUS304よりも2〜3割安価で入手可能な場合が多く、以下のような使い分けがされています。
| 用途 | 使用材質 | 理由 |
|---|---|---|
| 家電(裏側、見えない部品) | SUS430 | コスト重視・耐食性は最低限でOK |
| 食品機械、厨房機器 | SUS304 | 衛生性・耐薬品性・加工性が求められる |
| 自動販売機の外装 | SUS430 | 屋外でもある程度の耐食性が必要かつコストを抑えたい |
選定時のポイント
・耐食性や溶接性が重要 → SUS304
・価格を抑えたい、磁性を活かしたい → SUS430
・塩害地域や湿潤環境ではSUS430は不向き
SUS316との比較(モリブデン添加型)
SUS304と並んで広く使用されているステンレス鋼に「SUS316」があります。
両者は非常に似た見た目を持ち、同じオーステナイト系に分類されますが、化学成分と耐食性能に明確な違いがあり、それが用途やコストに直結します。
ここでは、SUS316がどのような場面でSUS304よりも適しているか、比較を通じて詳しく解説します。
化学成分の違い
・SUS304:18% Cr(クロム)、8% Ni(ニッケル)
・SUS316:16% Cr、10% Ni、2〜3% Mo(モリブデン)
このモリブデン(Mo)の添加が、SUS316の大きな特長です。
モリブデンは金属の耐食性を大きく向上させる元素であり、特に塩化物環境(海水や塩化ナトリウムの溶液)に対する耐性が強化されます。
耐食性の比較
・SUS304は日常的な環境や、軽度の酸性条件に対しては十分な耐食性を持ちます。
・SUS316はその上をいき、塩分、化学薬品、海水環境での耐腐食性が極めて高いです。
そのため、以下のような用途で使い分けられます。
| 環境・用途 | 選定材料 | 理由 |
|---|---|---|
| 一般的な屋内設備 | SUS304 | コストと耐久性のバランスが良好 |
| 沿岸地域・海洋設備 | SUS316 | 塩害に強く、長期間腐食しにくい |
| 化学プラント・薬品容器 | SUS316 | 酸やアルカリ、塩化物に対する耐性 |
| 食品工場 | SUS304またはSUS316 | SUS316は過酷な洗浄剤や塩分環境に強い |
機械的性質と加工性の違い
基本的な加工性は両者ともに良好で、溶接や切削、曲げなど一般的な加工が可能です。
ただし、SUS316はモリブデン含有の影響でやや加工硬化が強い傾向にあり、工具の摩耗や加工負荷が大きくなることがあります。
また、機械的強度に関しては大きな差はありませんが、耐孔食性・耐応力腐食割れ性においてはSUS316が優れています。
コストの違い
SUS316はニッケルやモリブデンといった高価な合金元素を含むため、SUS304よりも20〜40%程度価格が高いのが一般的です。
大きな構造物や大量生産品で使用する場合、コスト差が大きな影響を与えます。
そのため、「そこまでの耐食性が本当に必要か」を精査することが重要です。
「304で足りるか、316が必要か」の判断基準
| 判断ポイント | SUS304 | SUS316 |
|---|---|---|
| 海水・塩害環境 | △ | ◎(非常に強い) |
| 酸・アルカリの使用環境 | ○ | ◎(特に塩化物に強い) |
| 高コストが許容されるか | ◎(安価) | △(高価) |
| 一般的な衛生設備 | ◎ | ○(ややオーバースペック) |
まとめ
SUS316は、SUS304の上位互換といえる耐食性を持つ材料です。
ただし、そのぶん価格が高く、加工にもやや注意が必要です。
「過酷な腐食環境かどうか」が、両者の選定の分かれ道となります。
食品や医療分野ではSUS316が求められるケースも多く、品質とコストのバランスをよく見極めて使い分けることが大切です。
アルミや鉄との比較
SUS304はステンレス鋼の中でも代表的なオーステナイト系ステンレスですが、材料選定ではアルミニウムや炭素鋼(鉄)など他の金属との比較も重要です。
重量、強度、耐食性、加工性、コストなどの視点から、SUS304の特徴を他の金属材料と比較し、適材適所の材料選びに役立つ情報を提供します。
1. 重量・比重の違い
・SUS304の比重:約7.9
・アルミニウムの比重:約2.7
・炭素鋼(鉄)の比重:約7.8〜7.9
このため、アルミニウムはSUS304の約3分の1の軽さであり、軽量化が求められる用途では非常に有利です。
一方で、鉄とSUS304はほぼ同じ重量であるため、重量面の違いはほぼありません。
2. 強度と耐久性
SUS304は耐食性に優れ、強度も適度に高いため、多くの構造部材や機械部品に使用されます。
炭素鋼はSUS304より高い引張強度を持つことも多いですが、錆びやすいため表面処理が必須です。
アルミニウムは軽いものの、強度は低く、同じ強度を求めるなら厚みを増やす必要があり、設計次第で不利になることもあります。
3. 耐食性の違い
SUS304は耐食性が高く、特に湿気や食品、医療、化学環境での使用に適しています。
炭素鋼は錆びやすく、特別な塗装やメッキ処理がなければ屋外や湿気の多い環境では腐食が早いです。
アルミニウムも自然に酸化膜を形成し耐食性がありますが、塩水や強酸には弱い傾向があります。
4. 加工性・溶接性
SUS304は加工性・溶接性に優れ、深絞りや曲げ加工が容易で、多様な形状を作ることができます。
炭素鋼も加工性は良いですが、サビ防止のための後処理が必要です。
アルミニウムは軽くて加工しやすい一方、溶接時の熱変形に注意が必要です。
5. コスト面の比較
SUS304はニッケルやクロムを含むため材料費が高めです。
炭素鋼は最も安価で、コスト重視の大量生産に向いています。
アルミニウムは軽量ですが、材料費と加工費がやや高めになる場合があります。
6. 用途の使い分け例
| 用途 | 適した材料 | 理由 |
|---|---|---|
| 食品機械・医療機器 | SUS304 | 衛生的で耐腐食性が高い |
| 建築構造物(屋外) | 炭素鋼(塗装・メッキ付き) | 高強度と低コスト |
| 航空機・輸送機器 | アルミニウム | 軽量化が必須 |
| 一般機械部品 | SUS304または炭素鋼 | 耐食性やコストバランスで選択 |
まとめ
SUS304は耐食性と加工性に優れ、多様な環境で使える優れた材料ですが、重量は鉄とほぼ同じで軽量化が必要な場合はアルミニウムが有利です。
一方、コストを抑えたい場合や高強度が求められる用途では炭素鋼が選ばれます。
材料選定では性能だけでなく、コストや加工性も含めたトータルバランスを考えることが重要です。
試作品や小ロットの加工も大歓迎!
特に手のひらサイズの部品製作を得意としています。
アスクなら、試作品のお見積もりが最短1時間で可能!!
お気軽にお問い合わせください。
試作全国対応!
簡単・最短1時間お見積り
※こちらの記事はAIを参照して記事作成しております。
正しい情報かどうかは保証しかねますので、ご自身でお調べいただくようお願いします。