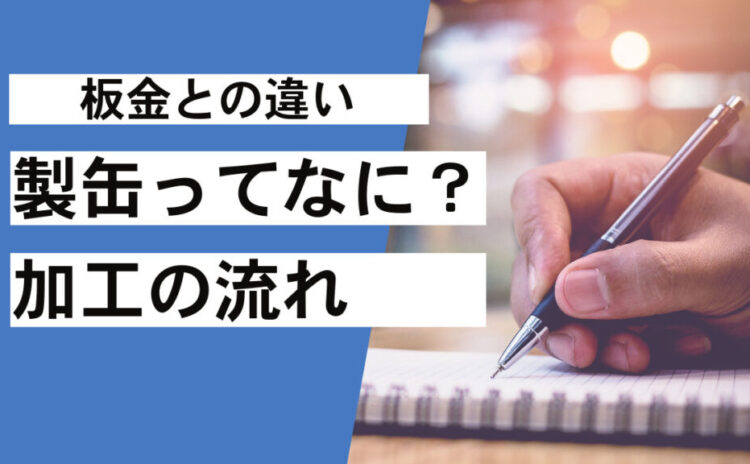製缶加工の基礎知識:金属構造物の設計から製造までの流れと板金加工との違い
製缶加工は、金属板や鋼材を切断・曲げ・溶接などの手法で立体的な構造物を製作する高度な技術です。
この工程では、耐圧性や耐熱性、耐食性が求められるため、使用する材料や加工方法の選定が極めて重要となります。
特に、化学プラントや発電所、建設現場などでは、製缶技術が産業インフラの基盤を支える役割を果たしています。
本記事では、製缶加工の基本的な流れや、板金加工との違いについて詳しく解説します。
製缶加工とは
製缶とは、主に金属の板材や鋼材を切断・曲げ・溶接などの加工を通じて、立体的な構造物や容器を製作する技術・工程を指します。
一般的には「缶」と名前が付いているため、飲料缶や保存缶などの小型容器を想起されることもありますが、産業における製缶はもっと大規模な構造物を対象とします。
例えば、工場設備における大型タンクや配管部材、架台やフレーム、ダクト、圧力容器、サイロなど、多種多様な金属製品が製缶技術によって造られています。
製缶の特徴は、主に鉄やステンレス、アルミニウムなどの金属材料を使用し、平板や形鋼(アングル、チャンネル、H鋼など)を組み合わせて立体構造物に仕上げる点です。
形状は筒状、角形、楕円形など用途に応じて自在に設計され、1点ものの製作も多いため、柔軟な設計対応と熟練した加工技術が要求されます。
製缶の役割は、単なる金属製品の成形にとどまりません。
製造される構造物は、多くの場合で高圧・高温・腐食環境といった厳しい使用条件下に置かれるため、安全性や耐久性の確保が不可欠です。
また、寸法精度や気密性、耐食性なども厳しく求められるため、材料の特性を熟知したうえで、適切な加工技術と品質管理が施されなければなりません。
さらに、製缶は製造業の多くの分野で重要な役割を担っています。
たとえば化学プラントや食品工場ではステンレス製の衛生タンクが不可欠ですし、発電所では耐圧容器や煙道が使用されます。
建設現場では、橋梁や鉄骨構造物の一部として製缶製品が組み込まれることもあり、まさに産業インフラの根幹を支える基盤技術と言えます。
製缶は、大量生産品というよりも、特注・多品種少量生産が中心であり、それぞれの製品が設計図に基づいて一品一様に作られるのが一般的です。
ゆえに、図面読解力、溶接技術、組立技術、検査技術など、幅広い技能が現場で必要とされ、ものづくりの中でも特に高度な職人技が要求される分野でもあります。
このように製缶は、金属の構造物を実際の機能部品や設備として実現するために不可欠な加工技術であり、製造業全体を支える重要なインフラ技術であると言えるのです。
製缶と板金加工・溶接加工の違い
製缶と混同されやすい加工分野として、「板金加工」や「溶接加工」があります。
いずれも金属を対象とする加工技術であり、共通点も多い一方で、それぞれの定義や目的、対象物の規模や役割には明確な違いがあります。
ここでは、製缶とそれらの加工との違いを整理して解説します。
まず「板金加工」は、主に薄板金属(厚さ0.5mm〜3.2mm程度)を対象とした加工を指します。
内容としては、切断・曲げ・穴あけ・プレスなどを施して、比較的小型で精密な部品を作ることが中心です。
自動車のボディ部品、電気筐体、厨房器具、エアコンのカバーなど、量産性の高い製品が多く、プレス機やベンダー、タレットパンチなどの専用設備を使用して効率よく製造されます。
一方、製缶は、比較的厚みのある鋼板(3.2mm以上)や形鋼(H鋼、アングルなど)を材料とし、大型構造物や容器、フレームなどを製作するのが主な目的です。
サイズが大きく重量もあるため、自動化されたラインでの大量生産には向かず、多くは人の手による加工と組立が中心です。
また、立体的な構造体である点や、高度な強度設計・耐圧設計を要する点も、板金加工とは大きく異なります。
次に「溶接加工」は、金属同士を融点近くまで加熱して接合する技術の総称であり、製缶や板金の一部工程として共通して用いられます。
TIG溶接、MAG溶接、アーク溶接、スポット溶接など、目的や材質に応じた多様な溶接法がありますが、これ自体は「製品の形を作る」加工ではなく、「部材を結合する」ための手段に位置づけられます。
このように、溶接加工は製缶や板金に不可欠なサブ技術であり、いわば「共通の部品」ですが、製缶はそれらの技術を駆使して立体構造物を完成させる「総合加工」としての性質が強く、より上流の工程にあたるとも言えます。
また、製缶と板金の違いは、図面の設計思想や製品の耐久要件にも表れます。
板金製品は主に見た目の仕上がりや軽量化、機能性を重視し、製缶製品は構造的な強度、安全性、耐久性が重要視されます。
この点で、設計者が求める製品の「性格」がまったく異なるのです。
結論として、板金加工は主に小型・薄板・量産品向けの精密加工、溶接加工は接合技術、そして製缶はそれらを融合して大型かつ高耐久な構造物を造る技術という位置づけになります。
これらの違いを理解することで、製品設計や発注の際にも、最適な加工方法を選定できるようになるでしょう。
製缶加工の歴史と発展
製缶加工は、古くから存在する金属加工技術の一つであり、時代とともに材料、加工技術、用途が進化してきました。
その起源は産業革命期にさかのぼり、蒸気機関の普及とともにボイラーや圧力容器などの金属容器の需要が増加したことが、製缶という専門的な加工分野の誕生に大きく関与しています。
19世紀の初頭、欧州では鋳鉄や鍛鉄を用いた初期の圧力容器やタンクが作られていましたが、これらは重く加工性に乏しく、また破裂事故の危険性も高いものでした。
やがて、鋼鉄の製造技術(ベッセマー法など)が進化すると、より強度と靭性に優れた素材が製缶用途に使われ始め、産業設備や輸送機器への応用が加速しました。
日本では明治時代以降、西洋技術の導入に伴い、鉄工所や造船所などを中心に製缶技術が発展しました。
特に戦前から戦後にかけては、造船・発電・化学プラントなどの産業インフラ整備により、大型タンク、圧力容器、配管部品などの需要が急増し、製缶は金属加工の中でも専門性の高い分野として確立されていきました。
昭和後期には、CO₂溶接機やTIG溶接機といった近代的な溶接装置の普及、ベンディングマシン・ロール機などの成形設備の導入により、加工精度や生産性が飛躍的に向上します。
また、設計面では2次元図面から3次元CADによる立体設計が主流となり、製品の複雑化・高性能化に対応できる体制が整いました。
さらに2000年代以降、ファイバーレーザー切断機やNCベンダー、溶接ロボットの導入など、製缶加工の自動化・デジタル化が進み、従来は熟練技能者の手作業に頼っていた工程も、標準化と効率化が進んできています。
とはいえ、すべての製缶製品が自動化できるわけではなく、多品種少量・一点物が多い現場では、現在も職人の技術が不可欠です。
また最近では、材料面での進歩も見逃せません。
従来の軟鋼(SS材)に加え、耐熱鋼、高張力鋼、二相ステンレス、チタンなど、より高性能な素材を使った製缶が増えており、それに対応する溶接技術や後処理技術も高度化しています。
こうした歴史の中で、製缶は単なる「金属を組み立てる」技術から、「機能性・安全性・信頼性を担保した構造物を生み出す」高度なエンジニアリング分野へと進化を遂げてきました。
そして現在では、プラント設備、エネルギー分野、医薬・食品業界など、極めて多様な業界で必要不可欠な基盤技術となっています。
製缶に使われる材料と構造

鋼材の種類(SS400・SUS・アルミなど)と特性
製缶加工において使用される材料は、製品の用途や環境条件、強度要件によって多岐にわたります。
その中でも代表的な材料として挙げられるのが、SS400(一般構造用圧延鋼材)、ステンレス鋼(SUSシリーズ)、そしてアルミニウム合金です。
それぞれの材質には特有の特性があり、選定にあたってはそれらの違いを理解しておくことが不可欠です。
まず、もっとも汎用的に使用されているのがSS400です。
これはJIS規格における一般構造用鋼材で、鉄と炭素を主体としたいわゆる「軟鋼」です。
引張強さや靭性に優れ、価格も安価で加工性が高いため、架台・フレーム・機械ベース・ダクト・支持構造など、強度と経済性のバランスが求められる製缶品に広く使われています。
ただし、耐食性には劣るため、屋外や湿潤環境では塗装やメッキによる防錆処理が必要です。
次に重要なのがステンレス鋼(SUS材)です。
代表的な種類としては、SUS304(オーステナイト系)、SUS430(フェライト系)、SUS316(モリブデン添加で耐塩性向上)などがあります。
最大の特長は優れた耐食性であり、薬品、水、塩分などに晒される環境でも長期間腐食せず、食品・化学・医薬などの分野で重宝されています。
特にSUS304は非磁性で溶接性にも優れ、製缶現場では最も多く使われるステンレスの一つです。
ただし、コストがSS材に比べて高いため、用途に応じて慎重な選定が求められます。
もう一つの重要な材料がアルミニウムおよびその合金です。
アルミは鉄やステンレスに比べて圧倒的に軽量でありながら、一定の強度と耐食性を持っています。
特にA5052やA6061などの合金は、製缶分野でも軽量化が求められる機器・設備に使われます。
電解質との反応によって自然に酸化皮膜を形成し、自己防錆性を持つ点も特徴です。
一方で、アルミは熱伝導率が高く、溶接時に歪みが出やすい、強度に限界がある、高温環境には不向きといった注意点もあります。
その他にも、用途に応じて高張力鋼板(ハイテン)、チタン合金、二相ステンレス鋼(SUS329J1など)など、特殊環境や高強度が求められる分野ではさらに高機能な素材が選ばれることもあります。
たとえば、塩害や海洋構造物にはSUS316やチタンが選定され、腐食性ガス環境下ではモネル合金やハステロイが使われる場合もあります。
このように、製缶加工においては材料特性の正しい理解と用途適合が極めて重要です。
単に「使える」だけでなく、「長期間、安全に、コストを抑えて使えるかどうか」を判断し、適切な材料を選定することが、品質の高い製缶製品を実現する鍵となります。
材料選定のポイント(耐食性・強度・コスト)
製缶加工における材料選定は、製品の性能・寿命・安全性、さらにはコストにも大きな影響を及ぼす極めて重要な工程です。
適切な材料を選ぶには、製品が使用される環境や機能要件を的確に把握し、それに応じた「耐食性」「強度」「加工性」「コスト」のバランスを考慮する必要があります。
ここでは、材料選定における3つの主要な評価軸について詳しく解説します。
① 耐食性
製缶品は、屋外・湿潤環境・薬品環境など、腐食が発生しやすい場所で使用されるケースが多いため、耐食性の評価は非常に重要です。
鉄系材料(SS400など)は大気中や水分が多い環境では容易に錆びるため、屋外や湿度の高い場所では塗装や溶融亜鉛メッキなどの防錆処理が不可欠です。
一方、ステンレス鋼(SUS304やSUS316)は、酸化クロム皮膜によって自己防錆性を持つため、長期的に腐食しにくい特性があります。
特にSUS316は塩害や化学薬品にも強いため、海洋設備や薬品タンクに最適です。
また、アルミニウム合金も自然酸化皮膜によって腐食に強く、軽量かつ耐久性を兼ね備えています。
② 強度と構造的性能
構造物としての製缶品においては、一定の荷重に耐えるだけの引張強さ、耐圧性、剛性などの構造的性能が求められます。
SS400は比較的安価ながらも汎用的な強度を有しており、建築用フレームや支持架台などに広く用いられます。
より高い強度が必要な場合は、高張力鋼(ハイテン)や二相ステンレス鋼などの特殊材料が検討されます。
また、圧力容器のように内部からの圧力に常時さらされる構造物では、板厚、補強リブの設計、溶接部の強度なども含めた総合的な強度評価が必要です。
アルミ合金は軽量性に優れる一方で、鋼材ほどの強度はないため、重量よりも強度が優先される場面では慎重な選定が求められます。
③ コストと調達性
材料のコストも、製品の総コストに直結するため、予算や納期を考える上で無視できない要素です。
SS400は流通量が多く価格も安定しており、加工性も高いため、コスト重視の案件では最も選ばれやすい材料です。
ステンレス鋼やアルミニウム合金は耐食性や外観性に優れる反面、価格が高く、厚板や特殊サイズは在庫が少ない場合もあります。
さらに、チタンや特殊合金(インコネル、ハステロイなど)は非常に高価で、入手にも時間がかかることがあります。
そのため、設計段階から「性能を満たす最小限のグレード」で選定する工夫が必要です。
また、材料の切断・溶接・仕上げの加工コストも材料によって異なるため、加工まで含めた「トータルコスト」で評価することが重要です。
以上のように、製缶における材料選定では、耐食性・強度・コストといった要素が複雑に絡み合います。
それぞれの要素に一長一短があるため、単一の判断基準ではなく、「使用環境」「安全性要求」「耐用年数」「メンテナンス性」「経済性」など多角的に検討することが、高品質かつコスト効率の良い製缶製品を実現する鍵となります。
製缶構造の代表例(タンク・架台・ダクトなど)
製缶加工によって製作される製品は非常に多岐にわたりますが、その中でも特に代表的な構造物として「タンク」「架台」「ダクト」の3種類が挙げられます。
これらはいずれも産業設備に不可欠な要素であり、製缶技術の応用範囲の広さと重要性を象徴する存在です。
それぞれの特徴と構造的なポイントを以下に解説します。
① タンク(容器類)
製缶構造物の中で最もポピュラーかつ重要な存在が「タンク」です。
液体や気体、粉体などの保管・輸送・処理を行うための容器で、化学プラントや食品工場、製薬工場、水処理施設など、あらゆる分野で使用されます。
タンクには「常圧タンク」「圧力タンク」「真空タンク」などさまざまなタイプがあり、それぞれ設計基準や材質、溶接仕様が異なります。
例えば、化学薬品を保管するタンクではSUS304やSUS316などの耐薬品性に優れた材料が選定され、内部は電解研磨や酸洗処理によって滑らかな表面に仕上げられます。
液体の種類によっては、内面ライニング(ゴム・フッ素樹脂など)を施すこともあります。
また、耐圧性能を必要とするタンクでは、板厚、補強リブ、圧力逃し弁の設置など、構造強度と安全性を確保する工夫が求められます。
② 架台・フレーム
製缶による「架台」や「フレーム」は、機械装置や配管・タンクなどを支えるための骨組み構造として使用されます。
いわば、設備全体を安定的に支える「基礎」や「土台」の役割を果たしており、振動・荷重・地震などに耐える設計が必要です。
多くの場合、角パイプ、チャンネル鋼、H鋼、アングルなどの形鋼を溶接で組み合わせ、剛性の高い構造体に仕上げます。
また、据付場所や設置機器の仕様に合わせて1品ずつ図面設計されることが多く、柔軟な形状対応が可能です。
架台は、外観よりも機能・剛性・レベル出し(平行精度)が重視されるため、溶接精度や歪み管理、現場での組立作業のしやすさまで含めた設計・加工が求められます。
表面処理としては塗装や溶融亜鉛メッキが施され、耐候性や防錆性を確保します。
③ ダクト・配管構造
製缶分野では、空気・蒸気・粉体・排気などを搬送するためのダクトや配管構造物もよく製作されます。
これらは建物の内部や屋外に設置され、複雑な形状で分岐・曲がり・変径が存在するため、製作には高度な板金・溶接技術が必要です。
材料としては、SS材やSUS材、あるいはアルミ材が使用されることが多く、搬送する物質の性状や温度によって選定されます。
ダクトには、丸型・角型・蛇腹型・フレキシブルタイプなどがあり、接続部にはフランジやスパイラル継手が設けられるのが一般的です。
また、吸引ダクトでは内面の気密性が重視され、丁寧な溶接と仕上げが求められます。
粉塵を扱う場合には、耐摩耗性に配慮して内張りや肉盛り溶接を施すこともあります。
このように、製缶製品は使用目的に応じて形状や構造、材質が大きく異なり、単純な箱物から複雑な圧力容器まで多岐にわたります。
それぞれの構造には安全性・耐久性・経済性を両立させる工夫が込められており、製缶技術の柔軟性と奥深さがそこに表れています。
製缶加工の主要プロセス
材料切断と成形(シャーリング・ベンディング)
製缶加工の最初の工程にあたるのが、「材料の切断」と「成形」です。
これらは製品形状を形作るための基本操作であり、製缶品の品質や精度、加工効率に大きく関わる重要なプロセスです。
この工程では、主に金属の板材や形鋼を対象に、図面通りの寸法・形状に加工するため、専用の機械と熟練の技術が求められます。
ここでは代表的な手法である「シャーリング」と「ベンディング」について詳しく解説します。
■ シャーリング(せん断加工)
シャーリングとは、主に平板の金属を直線的に切断する方法で、シャーリングマシンという専用機械を使用します。
上刃と下刃で金属をはさみ込み、はさみのような動作でせん断する仕組みで、鉄・ステンレス・アルミなどの板材を正確かつスピーディに切断できます。
切断面は比較的きれいで、バリが少ないことが特長です。
シャーリングは特に中厚板(〜6mm程度)の切断に適しており、材料ロスが少ないため、量産性や経済性に優れています。
精度も高く、寸法公差を±0.5mm程度に抑えることが可能です。
ただし、直線切断しかできないため、曲線や複雑形状を切り出す際は、レーザー切断やプラズマ切断といった別の加工法が併用されます。
■ ベンディング(曲げ加工)
ベンディングとは、板材を折り曲げて立体的な形状を作る加工で、代表的な機械としては「ベンダー(ブレーキプレス)」が使用されます。
パンチとダイという上下の金型で板材を押し込み、V字型やコの字型など、さまざまな形に成形します。
製缶では、箱形のフレームや筒状の構造体など、複数の曲げを組み合わせた構造が頻繁に登場します。
ベンディング加工では、板厚や材質に応じて最適な押し込み量や曲げ順序を考慮する必要があり、素材に無理な力を加えると「割れ」や「スプリングバック(反り戻り)」が発生することがあります。
特にステンレス鋼は硬度が高いため、曲げ時の反発が大きく、経験と試し曲げによる調整が重要です。
さらに、曲げ部位の寸法精度が重要な場合、補正係数を用いた精密な曲げ展開が行われます。
また、最近ではNCベンダーや油圧制御式の高精度機械も普及しており、自動位置決めや角度調整が可能になっているため、量産品でも高い再現性と品質が確保されています。
■ 製缶における成形工程の重要性
製缶では「ただ切って曲げる」だけではなく、その後の溶接や組立、仕上げに至るまでの「一貫した精度管理」が求められます。
たとえば、わずかな曲げ誤差が最終製品の歪みや隙間に直結することもあり、初期加工の段階でどれだけ精密に仕上げるかが品質の基礎になります。
また、切断・曲げ工程では作業効率も問われます。
材料取り(ネスティング)の工夫や、機械の段取り作業を減らす方法など、生産性向上のための工夫も多く施されています。
このように、シャーリングやベンディングは製缶の基礎であり、製品の精度・機能・美観に直結する極めて重要な工程です。
近年はこれらの作業を自動化・デジタル制御することで、技能の属人性を軽減しながら品質と効率を両立する取り組みも進んでいます。
溶接工程(TIG・MAG・アーク溶接など)
製缶加工において最も重要な工程のひとつが「溶接」です。
溶接は、金属と金属を接合し、1つの構造物として一体化させるための基本かつ不可欠な作業であり、製品の強度・密閉性・耐久性に直結します。
製缶では板材や形鋼を切断・成形した後、それらを図面通りに組み合わせて溶接し、立体的な構造体を完成させます。
ここでは、代表的な溶接法であるTIG溶接、MAG溶接、アーク溶接について、それぞれの特徴と適用範囲を解説します。
■ TIG溶接(タングステン・イナート・ガス溶接)
TIG溶接は、タングステン電極とアルゴンなどの不活性ガスを使って行う高品質な溶接方法です。
特徴としては、ビード(溶接痕)が美しく、スパッタが少ないこと、また制御性が高く、薄板から厚板まで対応可能であることが挙げられます。
特にステンレスやアルミニウムなど、溶接の難しい金属にも適しており、食品機器や医療機器などの衛生製缶分野で多用されます。
一方で、手動作業が中心となり、溶接速度が遅いという欠点があります。
熟練技能者による正確な操作が求められるため、量産性には向かず、高品質を最優先する部分的な接合に使われることが多いです。
■ MAG溶接(メタル・アクティブ・ガス溶接)
MAG溶接は、CO₂ガスや混合ガス(アルゴン+CO₂)を使用し、ワイヤ送給式の自動装置で連続的に溶接を行う方法です。
特に鉄鋼材料(SS材)との相性が良く、スピーディで作業性に優れるため、製缶業界でも広く採用されています。
半自動・自動化が容易であることから、長距離の溶接や量産品の製造に適しており、架台・フレームなどの大型構造物で多用されます。
MAG溶接の欠点としては、スパッタ(溶接時の飛び散り)が多く、後処理に手間がかかる点や、風のある環境でガスが乱れると品質が不安定になる点があります。
屋外作業や高所では、溶接品質の管理に注意が必要です。
■ アーク溶接(被覆アーク溶接)
アーク溶接は、被覆された金属棒(溶接棒)を使用し、電気アークの熱によって金属同士を接合する最も古典的な溶接方法です。
設備が簡易で取り回しやすく、電源さえあればどこでも施工できるというメリットがあります。
工場内はもちろん、現場施工、屋外の大物構造物、補修作業など、汎用性の高い溶接法として今でも多く使われています。
ただし、作業者の技術に大きく依存し、スピードや外観仕上げにばらつきが出やすい点があり、現代ではMAGやTIGが主流になる中、アーク溶接は用途が限定されつつあります。
それでも厚板の根本溶接や現場での急な対応には強みを持っています。
■ 製缶における溶接工程の管理
製缶では、溶接は単なる接合手段ではなく、「構造の安全性」を左右する重要な要素です。
溶接部の欠陥(ブローホール、クラック、ピットなど)が発生すれば、構造物の破損や事故に直結するため、正確な施工と厳格な検査が必須です。
また、溶接による熱ひずみや変形の抑制も重要な課題です。
溶接順序や仮付け位置、治具の活用、予熱や後熱などの処置を組み合わせて、変形を最小限に抑える技術が求められます。
このように、製缶加工における溶接は、材料や用途に応じた最適な溶接法を選定し、高品質・高強度な接合を実現するための中核的工程です。
近年では溶接ロボットの導入も進んでおり、品質の均一化と技能継承の観点からも注目されています。
組立と仕上げ処理(歪み取り・バリ取り・塗装)
製缶加工における最終工程のひとつが、「組立」と「仕上げ処理」です。
切断・成形・溶接を経て完成に近づいた製品を、精度よく仕上げ、安全かつ美観のある状態に整える工程であり、製品の完成度を決定づける重要なステップです。
ここでは、代表的な処理である「歪み取り」「バリ取り」「塗装」について詳しく解説します。
■ 歪み取り(応力除去)
溶接作業では、局部的な加熱と急冷が繰り返されるため、金属内部に残留応力が発生し、構造物に歪みや反り、ねじれが生じやすくなります。
特に大型のフレームや厚板の構造物では、わずかな歪みでも据付不良や応力集中の原因となり、製品の信頼性を損なう可能性があります。
歪み取りの方法としては、加熱矯正(トーチによる局部加熱)、機械的な押し矯正(プレス機など)、バランス再溶接(対称箇所への補助溶接)などがあり、製品の構造・寸法・使用環境に応じて適切な手法が選ばれます。
また、必要に応じて応力除去焼鈍(熱処理による応力緩和)を施す場合もあります。
歪み取り作業は、熟練工の経験と感覚が大きく影響する分野であり、製品が完成してからでは修正が困難な場合もあるため、溶接前の段取りや仮組の段階からの歪み対策設計が極めて重要です。
■ バリ取り・面取り・研磨
切断や穴あけ、溶接の過程では、エッジ部に「バリ(切削残りや突起)」や「スパッタ(溶接金属の飛散)」が発生します。
これらは怪我の原因になるだけでなく、製品の機能や外観、塗装密着性にも悪影響を及ぼすため、必ず除去する必要があります。
バリ取りや面取りは、グラインダー、ヤスリ、ベルトサンダー、エアツールなどの工具を使って行われ、エッジを滑らかに仕上げます。
特にステンレス製品では、後の電解研磨やパッシベーション処理に備えて、丁寧な前処理が求められます。
また、外観が求められる製品(例:食品機械、装飾カバー)では、溶接ビードの研磨・表面のヘアライン仕上げや鏡面仕上げなど、より高度な研磨作業も行われ、見た目だけでなく清掃性や耐食性向上にも寄与します。
■ 塗装・表面処理
製缶製品は使用環境に応じて、塗装やメッキなどの防錆処理や装飾処理を施します。
鉄鋼製の構造物では、腐食対策としてプライマー(下塗り)+上塗り塗装(ウレタン系・フッ素系など)を行うことが一般的であり、粉体塗装や焼付塗装による高耐久仕上げも採用されます。
また、屋外や海浜地域に使用される製品には、溶融亜鉛メッキ(ドブ付け)が選ばれることが多く、20年以上の耐食性を発揮します。
SUS製品やアルミ製品では、電解研磨・アルマイト処理・パッシベーション処理などの化学的な表面処理を施して、耐久性・衛生性・美観を高めます。
仕上げ処理は製品の最終品質に直結するだけでなく、メンテナンス性や長寿命化にも大きく関与するため、用途とコストのバランスを考えた選定が不可欠です。
このように、組立と仕上げ処理は単なる「後工程」ではなく、製品の性能・見た目・安全性を確保するための仕上げ技術の集大成とも言える重要な工程です。
特に近年は、見た目の美しさや長寿命化、脱炭素に向けたコーティングの見直しも進んでおり、仕上げ処理の価値はますます高まっています。
試作全国対応!
簡単・最短1時間お見積り
※こちらの記事はAIを参照して記事作成しております。
正しい情報かどうかは保証しかねますので、ご自身でお調べいただくようお願いします。