金属加工における脱脂の重要性とその役割
金属加工の現場では、切削や研削、プレス、成形などの各工程で潤滑油や切削油、防錆油などが使用されます。
これらの油分は加工後の金属表面に残留し、次の工程(塗装、メッキ、溶接、接着など)に進む際に密着性や耐久性に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、脱脂は非常に重要な前処理の一つとされています。
脱脂とは
脱脂とは、金属表面に付着した油脂類や不純物、汚れなどを除去する工程のことを指します。
金属加工の現場では、切削、研削、プレス、成形といったさまざまな加工工程で潤滑油や切削油、防錆油などの油分が使用されますが、これらは加工後の金属表面に残留します。
この残留物がある状態で次の工程(塗装、メッキ、溶接、接着など)に進むと、密着性や耐久性に重大な悪影響を及ぼすことがあるため、脱脂は非常に重要な前処理の一つとされています。
たとえば、塗装工程では、表面に油が残っていると塗膜が均一に広がらず、はがれやすくなったり、気泡やクレーターが発生したりします。
メッキにおいても同様で、金属イオンが均一に析出しないため、膜厚が不均一になり、耐食性や見た目に問題が生じます。
さらに、溶接や接着では、接合部に油があると強度が著しく低下し、構造体としての信頼性を損なうおそれがあります。
脱脂の目的は、単に美観を良くするためではなく、こうした後工程の品質や製品の耐久性、安全性を確保するために不可欠なものであり、工程管理上でも重要な意味を持ちます。
特に、自動車、航空機、医療機器、電子部品といった高い信頼性が要求される分野では、脱脂工程の適切な管理が製品全体の品質保証に直結することになります。
また、脱脂は品質だけでなく、工程全体の効率化やトラブルの予防にも関わっています。
たとえば、塗装不良によって再処理が発生すると、大きなコスト増や納期遅れを招くことになります。
脱脂の段階で汚れを完全に除去できていれば、後の工程がスムーズに進み、歩留まり向上にもつながります。
逆にいえば、脱脂不良が一連の生産ライン全体に影響を及ぼすリスクがあるという点で、その重要性は非常に高いといえます。
このように、脱脂は金属加工の補助的な工程と思われがちですが、製品の最終品質を大きく左右する基盤的な役割を担っており、「見えない品質管理」として非常に注目されている工程です。
油脂・汚れの種類と発生源
金属加工において脱脂を必要とする最大の理由は、加工工程中に金属表面にさまざまな油脂や汚れが付着するからです。
これらの汚れは単一の成分ではなく、複数の物質が混在しており、それぞれに適した除去方法が必要となるため、汚れの種類や発生源を正しく理解することは、適切な脱脂処理の第一歩となります。
最も代表的な汚れは、加工油(潤滑油・切削油・防錆油)です。
これらは金属の加工性を高めるために不可欠で、摩擦の低減、発熱の抑制、工具の保護など多くの役割を果たしていますが、加工後に表面に残留します。
これらの油分は、ミネラルオイル(鉱物油)系、合成油系、エマルジョン(乳化)タイプなど多様で、それぞれに異なる脱脂剤や洗浄条件が求められます。
次に、人為的な皮脂汚れや指紋などの有機性汚れも見逃せません。
これは作業者が素手でワークを触った際に付着するもので、微量であっても後工程(塗装・めっき等)に悪影響を及ぼすため、重要な管理対象です。
さらに、研磨剤の残留物や粉塵・酸化皮膜などの無機質な汚れもあります。
たとえばバフ研磨やショットブラストを行った後には、研磨剤や金属粉が微細に付着しており、これらが残ると表面の粗さが変化し、後の被膜形成に悪影響を及ぼします。
これらの無機汚れは、単なる油除去だけでは取れないため、別途アルカリ洗浄や物理的な洗浄工程が併用されることが多いです。
また、加工中に混入した外部汚染物質(ホコリ、グリース、機械油の飛散)もあり、特に一貫生産ラインではさまざまな要因で予期せぬ汚れが金属表面に付着する可能性があるため、包括的な管理が求められます。
これらの汚れの発生源は主に以下のように分類されます。
・加工工程由来:切削油、成形潤滑剤、防錆油、冷却液など
・作業環境由来:粉塵、浮遊油分、作業者の皮脂など
・前処理工程由来:未洗浄の機械部品、使い回された治具など
このように、金属加工における油脂や汚れは非常に多様であり、単一の洗浄法ですべてをカバーするのは難しいのが現実です。
したがって、どのような汚れが、どの工程で、なぜ発生したのかを把握し、それに対応する洗浄方法を選定することが、効率的かつ高品質な脱脂処理を実現するカギとなります。
脱脂工程が必要な主な加工工程・分野
脱脂工程は、金属加工のあらゆる分野で不可欠な前処理として位置付けられています。
とくに、表面の清浄度がその後の工程や製品の品質に直接影響を及ぼすような加工分野では、脱脂の有無が工程成否の鍵を握ることも少なくありません。
ここでは、脱脂が重要視される代表的な加工工程と分野について解説します。
まず第一に挙げられるのが塗装工程です。
自動車部品、建材、家電製品などでは、外観と防錆を兼ねた塗装が一般的に行われます。
金属表面に油分や汚れが残っていると、塗料が均一に塗布されず、密着性が低下して塗膜剥離や発泡、ピンホールなどの不具合が生じます。
そのため、塗装前には必ず脱脂処理を行い、油分を完全に除去してからプライマーやトップコートを塗布します。
次にメッキ(電気めっき・無電解めっき)においても、脱脂は不可欠です。
メッキ処理は、金属表面に薄く均一な金属被膜を形成する工程ですが、基材に油分が残っていると電解作用や化学反応が阻害され、膜厚が均一にならなかったり、密着性の悪い被膜が生成されてしまいます。
これにより、耐食性や外観、導電性が大きく損なわれるため、メッキ前の脱脂工程は極めて重要です。
また、溶接工程も脱脂処理が重視される分野の一つです。
金属表面に油があると、加熱時に発煙やススの発生、さらには溶接欠陥(ブローホール、ピット、未融合など)を引き起こす要因になります。
とくに高強度構造物や精密溶接が求められる分野では、前もって溶接部を完全に脱脂することが、構造信頼性の確保につながります。
さらに、接着工程においても脱脂の有無は決定的な意味を持ちます。
金属と樹脂、金属同士を接着剤で固定する場合、油分や汚れがあると接着界面が滑って密着せず、剥離やずれが発生しやすくなります。
電子機器、医療機器、航空宇宙部品など高精度が要求される場面では、洗浄および脱脂処理の徹底が品質を大きく左右します。
さらに忘れてはならないのが精密機械加工・組立工程です。
精密部品の組立や測定、組込みの際に、表面に汚れや油分があると寸法精度や摩擦特性に影響を与えることがあります。
また、潤滑油や切削油の成分によっては樹脂部品との相性が悪く、化学的な劣化を招くこともあるため、脱脂を経てクリーンな状態で組み立てることが重要です。
このように、脱脂は金属の「前処理」でありながら、後工程の品質確保とトラブル予防に直結する重要工程です。
自動車、家電、建築、精密機械、航空・宇宙、医療といった多岐にわたる分野で求められており、今や金属加工の品質管理における基本中の基本といえる存在です。
脱脂の方法と種類
溶剤による脱脂(有機溶剤・炭化水素系)
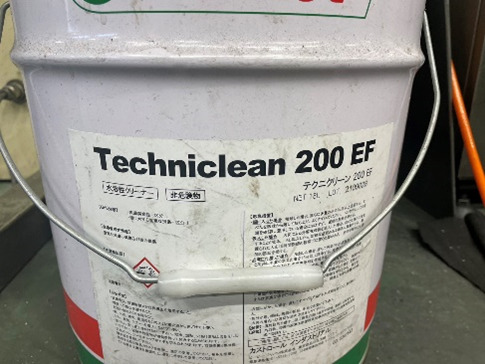
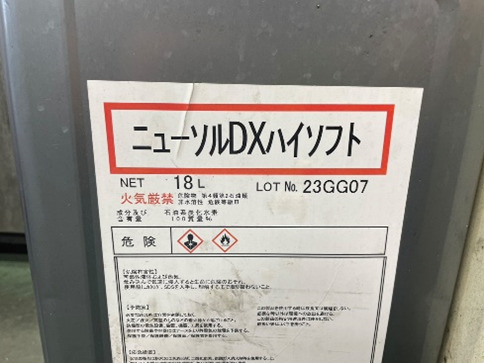
溶剤による脱脂は、金属加工において最も古くから使われている代表的な脱脂手法の一つです。
特に有機溶剤や炭化水素系溶剤は、金属表面に付着した油脂類を迅速かつ効率的に溶解・除去できるという特長があり、現在でも多くの現場で使用されています。
ここでは、それぞれの特徴と用途、安全性や環境対応の観点を含めて詳しく解説します。
有機溶剤による脱脂
有機溶剤とは、油脂やグリースなどの有機物質を化学的に溶かす能力を持つ化合物で、トリクロロエチレン(TCE)、パークロロエチレン(PCE)、アセトン、メタノールなどが代表例です。
特にTCEやPCEは、優れた脱脂力と速乾性を兼ね備え、金属加工現場では長年スタンダードな洗浄剤として使われてきました。
有機溶剤脱脂は、浸漬やスプレー洗浄、さらには真空洗浄装置による密閉式処理など、さまざまな形で応用されています。
短時間で高い洗浄効果が得られるため、特に微細な機械部品や複雑な形状の部品の洗浄に向いています。
また、水を使用しないため、乾燥工程が不要、または非常に短く済むという利点もあります。
しかしながら、有機溶剤の多くは揮発性が高く、作業者の健康リスクや火災・爆発の危険性、さらに大気汚染や地下水汚染の原因となることから、近年ではその使用が厳しく制限される傾向にあります。
特にトリクロロエチレンやパークロロエチレンはPRTR法や大気汚染防止法の対象物質とされ、多くの企業が代替手法への移行を進めています。
炭化水素系溶剤による脱脂
炭化水素系溶剤は、石油から得られるアルカンやシクロアルカン、芳香族化合物などをベースとした脱脂剤で、トルエン、キシレン、ヘキサンなどが代表的です。
これらは有機溶剤に比べて毒性が比較的低く、臭気も抑えられており、人体への影響を抑えた形で使用できます。
近年では、安全性と環境性能を両立させた「低臭・高精製」の炭化水素系脱脂剤も登場しており、ノンハロゲン・ノンVOC(揮発性有機化合物)対応型製品への移行が進んでいます。
炭化水素系脱脂剤は、引火性があるため、取り扱いには依然として注意が必要ですが、有機溶剤のような強い環境負荷を避けつつ、十分な脱脂性能を得られることから、溶剤洗浄の新たなスタンダードになりつつあります。
特に、自動車部品や精密部品の脱脂処理に多く採用されています。
活用と課題
溶剤脱脂は、油脂溶解力の高さと作業効率の良さが魅力ですが、廃液処理や作業環境改善への配慮が不可欠です。
各国で環境規制が強化されている中、脱臭装置や再生装置との組み合わせによるクローズドシステム化が進んでおり、環境対応と洗浄力の両立が求められています。
アルカリ脱脂・酸性脱脂の原理と使い分け
溶剤を使わない水系脱脂法の中で、最も広く利用されているのが「アルカリ脱脂」と「酸性脱脂」です。
これらはそれぞれ異なる化学的性質を活用して油脂や汚れを除去するもので、対象物や汚れの種類、後工程の内容に応じて適切に使い分けることが求められます。
以下ではその原理、特徴、そして使い分けのポイントについて詳しく解説します。
アルカリ脱脂の原理と特徴
アルカリ脱脂は、水に溶けたアルカリ性薬品(苛性ソーダ:NaOH、炭酸ナトリウム:Na₂CO₃、リン酸塩など)を使用し、油分を加水分解または乳化分散させて除去する方法です。
アルカリ成分は脂肪酸と反応して「石けん(脂肪酸ナトリウム)」を生成し、それによって油分が水中に溶け込むようになります。
これは「けん化反応」と呼ばれ、界面活性剤のような効果を発揮します。
この方法は特に鉱物油や動植物性油脂、指紋、皮脂汚れなどに強く、また無機物(スケールやサビ)の一部も軟化させる効果があるため、広範な汚れに対応できます。
洗浄後は水洗いが必要ですが、水との親和性が高いため工程としての扱いやすさもあり、大量処理や自動洗浄装置との相性が良好です。
一方で、アルミニウムや銅など非鉄金属には腐食性があるため、処理時間や濃度、pH管理には細心の注意が必要です。
これらの金属に対してはアルカリ度を抑えた専用洗浄剤や、腐食抑制剤を添加した処方が求められます。
酸性脱脂の原理と特徴
酸性脱脂は、リン酸や硫酸、塩酸などを成分とした酸性の液により、金属表面の酸化被膜やサビを除去しつつ、軽度の油分を洗浄する方法です。
主に酸化汚れ、金属スケール、軽微なグリース残留などに有効で、特に鉄鋼系の素材でサビ落としと脱脂を同時に行いたい場合に活用されます。
酸による洗浄は、金属表面に軽いエッチング(化学的腐食)をもたらし、メッキや塗装前の表面活性を高める効果もあるため、下地処理としての役割が大きい点が特長です。
ただし、酸性処理は脱脂力そのものはアルカリほど高くなく、油が多い場合は予備脱脂(アルカリ処理)を行ってから酸処理するといった多段階処理が必要になることがあります。
また、酸性溶液はガス発生(HClやH₂)を伴うことがあり、換気や防錆対策、作業者の安全確保が重要です。
特に塩酸系は揮発性が高く、ステンレスや設備の腐食の原因になるため、使用環境に応じた管理が不可欠です。
使い分けのポイント
アルカリ脱脂と酸性脱脂は、その性質上、相互補完的な役割を持っています。
油脂汚れが主であればアルカリ脱脂が基本となり、表面スケールや酸化膜を除去する目的がある場合には酸性処理を補助的に使うのが一般的です。
例えば、
・アルミニウム部品の脱脂・表面処理 → 中性〜弱アルカリ性の脱脂剤+酸性エッチング
・鉄鋼部品の塗装前処理 → アルカリ脱脂 → 酸洗い → パッシベート処理
・サビ落とし+軽脱脂 → 酸性脱脂(リン酸系推奨)
このように、素材や汚れ、後工程に応じた処方設計が非常に重要であり、現場での経験や試験による最適条件の選定が成功のカギを握ります。
超音波脱脂・高圧ジェット洗浄などの物理的方法

脱脂といえば化学的な洗浄剤の使用が中心と思われがちですが、物理的な力を利用して金属表面の油分や汚れを取り除く方法も広く用いられています。
これらは「物理脱脂」と総称され、特に化学薬品への依存を減らしたい場合や、複雑形状・微細部の洗浄が必要な部品で重宝されます。
ここでは、代表的な「超音波脱脂」と「高圧ジェット洗浄」を中心に解説します。
超音波脱脂の仕組みと特徴
超音波脱脂は、液体中に高周波の音波(通常20kHz〜40kHz)を照射し、発生するキャビテーション(空洞現象)によって洗浄力を得る方法です。
キャビテーションとは、液体中に無数の微細な気泡が形成され、これが瞬間的に破裂することで局所的に高温・高圧の衝撃が発生する現象です。
この衝撃波が、金属表面に付着した油脂や微粒子、汚れを浮かせて剥離させるというのが洗浄の原理です。
この方式の最大の強みは、極めて小さな隙間や複雑な形状の内部まで洗浄が届くことです。
たとえば、微細な穴のある部品、コネクタ端子、ベアリング、精密部品など、人手やブラシでは洗えない箇所においても効果を発揮します。
また、超音波脱脂は薬剤濃度や温度との相乗効果が大きく、弱アルカリ性洗浄剤や水ベースの洗浄液と併用することで脱脂性能を高めることが可能です。
一方で、金属表面に過度なキャビテーションが当たるとマイクロピット(微細な凹み)が生じるリスクがあり、特に軟質金属(アルミや銅)には注意が必要です。
また、振動子や洗浄槽の保守が必要で、装置の初期導入コストも比較的高めです。
高圧ジェット洗浄の概要と適用例
高圧ジェット洗浄は、水や水溶性洗浄剤をノズルから高圧で噴射し、物理的な衝撃によって汚れを吹き飛ばす洗浄方法です。
使用される圧力は0.5〜5MPa(5〜50気圧)程度が一般的で、圧力と流量を調整することで洗浄力をコントロールします。
機械加工後の部品表面や、表面が比較的平滑なワークに対して有効であり、短時間で広範囲を処理できる高効率な方法です。
この方式の大きな利点は、研磨剤や薬剤を使用せずに高い脱脂効果を得られる点にあります。
溶剤を使用できない現場や、環境負荷を下げたい現場では特に重宝されます。
また、洗浄と同時に冷却や異物排出ができるため、自動車エンジン部品や大型構造物の中間処理として活用されることもあります。
ただし、高圧が当たらない陰部や内面には洗浄が届きにくいという特性があり、複雑形状のワークには不向きな面もあります。
また、使用する水量が多く、排水処理や乾燥工程を併設する必要があるため、設備設計やレイアウトに工夫が求められます。
その他の物理的方法
その他にも以下のような物理脱脂法があります。
・スチーム洗浄:高温蒸気を吹き付けて油分を浮かせる。軽汚染や衛生管理に有効。
・ブラスト洗浄:微細粒子を吹き付けて表面処理と脱脂を兼ねる。前処理向き。
・真空洗浄:真空環境で溶剤や超音波を併用。高精度部品や電子部品に。
物理脱脂は「環境負荷の低減」や「難洗浄部位の処理」といった目的に対して非常に有効であり、化学処理の代替または補完手段として注目される技術です。
ただし、物理的な力のみでは完全脱脂が難しいケースも多く、他の脱脂方法との併用が実用上の最適解となることが多いです。
各脱脂方法の特徴と選定ポイント
材質別の適正な脱脂方法
金属加工における脱脂は、対象となる素材の種類によって最適な方法が異なります。
材質ごとに化学的な耐性や反応性、表面状態が異なるため、適切な脱脂手法を選ばなければ腐食や変色などの不具合を招くおそれがあります。
ここでは、主要な金属材料(鉄鋼、アルミニウム、銅、ステンレス鋼など)について、それぞれに適した脱脂方法と注意点を解説します。
鉄・炭素鋼(普通鋼)
鉄鋼材料は、脱脂処理において比較的扱いやすい素材です。
油脂類が付着しやすい一方で、化学的な耐性が高く、強めのアルカリ洗浄や溶剤脱脂にも十分耐えることができます。
・推奨脱脂法:アルカリ脱脂、有機溶剤、炭化水素系溶剤、高圧ジェット洗浄
・注意点:鉄は大気中で容易に酸化しやすいため、脱脂後はなるべく早く次工程(防錆、塗装など)に進む必要があります。
また、酸性脱脂を併用することでサビやスケールの除去も可能ですが、過度な酸洗いはピット腐食の原因になることもあります。
アルミニウム・アルミ合金
アルミは軽量で耐食性に優れる一方、化学薬品に対しては繊細な面があります。
特に強アルカリによって表面が激しく侵され、白濁や腐食の原因となることがあるため注意が必要です。
・推奨脱脂法:中性〜弱アルカリ性洗浄剤、炭化水素系溶剤、超音波洗浄
・注意点:pH10以上の高濃度アルカリ洗浄は避けるべきで、専用のアルミ対応脱脂剤を用いることが推奨されます。
また、脱脂後の水洗や乾燥不良によるシミや水跡が品質不良につながるため、脱水処理や乾燥条件の最適化も重要です。
銅・銅合金(真鍮など)
銅系材料は油脂とのなじみが良く、比較的汚れが落としやすい素材です。
ただし、酸化されやすく、洗浄液中の酸素や酸によって黒変や変色を起こすことがあります。
・推奨脱脂法:中性洗浄剤、炭化水素系溶剤、超音波脱脂
・注意点:酸性脱脂は黒変のリスクがあり、必要な場合は防止剤(例:チオ尿素系添加剤)を併用します。
アルカリ洗浄もpH管理が重要で、腐食を防ぐためには脱脂後の中和処理や迅速な乾燥が不可欠です。
ステンレス鋼(SUS304, 316など)
ステンレスは耐食性が高く、比較的安定した金属ですが、表面に残った油脂やスケールがその特性を損なうことがあります。
特に医療機器や食品機械など、極めて高い清浄度が求められる分野では、脱脂の品質が製品の信頼性に直結します。
・推奨脱脂法:中性〜弱アルカリ性脱脂剤、超音波洗浄、有機溶剤、酸性処理(パッシベーション)
・注意点:ステンレスは表面に不動態被膜を持つため、脱脂後に酸処理(硝酸やクエン酸)で再パッシベーションを行うことがあります。
また、塩素系溶剤を使用する場合は、残留塩素が応力腐食割れを引き起こすリスクがあるため完全除去が必要です。
亜鉛メッキ鋼板・めっき素材
めっきされた素材は、ベース金属とめっき層の双方の性質を考慮する必要があります。
たとえば亜鉛はアルカリにも酸にも弱く、洗浄剤選定を誤るとめっき剥離や曇りが生じます。
・推奨脱脂法:中性脱脂剤、炭化水素系溶剤、スチーム洗浄
・注意点:強アルカリによる「白濁」や酸性薬品による「黒変」は避けるべきで、低刺激性かつめっき対応の洗浄剤を選択する必要があります。
材質別に適切な脱脂方法を選ぶことは、単なる洗浄工程の品質向上だけでなく、後工程(塗装・めっき・接合など)の信頼性向上にも直結します。
実際の現場では、材質に応じたテスト洗浄や専用のレシピ設定が重要であり、「一律処理」は失敗の元となりやすい点に注意が必要です。
環境・安全面を考慮した方法の選定
脱脂工程は金属加工の中でも重要な前処理ですが、同時に環境負荷・作業者の安全・法令遵守といった側面も常に意識する必要があります。
かつては揮発性有機溶剤(VOC)や有害な洗浄剤が広く使われてきましたが、近年では環境保全の観点から規制が強化され、安全で持続可能な処理方法への移行が進んでいます。
本項では、脱脂における環境・安全性を考慮した方法選定のポイントを解説します。
揮発性有機化合物(VOC)規制と対応策
VOCとは、大気中で容易に気化する有機化合物の総称で、環境中では光化学スモッグや地球温暖化の原因となります。
日本を含め多くの国では、トリクロロエチレン(TCE)やジクロロメタン(MC)などの使用が厳しく制限されており、代替技術の導入が進んでいます。
対応策の一つが、低VOC型またはノンVOC型の洗浄剤への切り替えです。
たとえば炭化水素系溶剤はVOCを含むものの、回収・再利用が可能で、密閉式の装置と組み合わせれば排出量を最小限に抑えることが可能です。
また、水系洗浄剤(中性〜弱アルカリ性)は環境に優しく、再利用や排水処理も比較的容易なため、多くの現場で主流となりつつあります。
廃液・排水処理と中和対策
脱脂工程で使用される洗浄剤は、使用後に廃液として処理が必要です。
特にアルカリ脱脂や酸洗いでは、pHが極端に偏った排水が生じ、中和処理を行わないと下水規制に抵触する恐れがあります。
また、油分を含む排水は環境汚染の原因となるため、油水分離槽や凝集沈殿処理などの前処理設備が必要となります。
近年では、ろ過・膜処理・イオン交換などを組み合わせたクローズドシステム(循環再利用型洗浄)の導入も進んでおり、廃液量を大幅に削減しつつ処理コストを抑える事例も見られます。
初期投資は高額ですが、中長期的には環境とコストの両立が可能となります。
作業者の健康と安全への配慮
脱脂に使われる薬品の多くは、皮膚・粘膜への刺激性があり、場合によっては毒性や発がん性の懸念もあります。
特に塩素系溶剤(TCE、PCEなど)は吸引や皮膚接触により神経系や肝機能に影響を及ぼすため、作業環境管理・防護具着用・換気設備の設置が不可欠です。
推奨される対策は以下の通りです。
・密閉型洗浄装置の導入:薬品の揮発や飛散を防ぐ
・自動投入・排出システム:作業者の薬品接触を最小限に
・適切なPPE(個人用保護具)着用:手袋、保護眼鏡、防毒マスクなど
・作業マニュアルと教育の徹底:異常時対応の訓練を含む
また、GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づいたSDS(安全データシート)の整備と周知も重要です。
作業者が取り扱う化学物質のリスクを正しく理解することで、事故や健康被害を未然に防ぐことができます。
法令・規格への対応
脱脂処理に関しては、以下のような法令や業界規格が関係します。
・労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防規則など)
・PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)
・下水道法・水質汚濁防止法
・RoHS、REACHなどの国際規制
・JIS Q 9100(航空宇宙)やISO 14001(環境)との整合
これらに適合した処理方法の選定・管理体制の整備は、企業の社会的責任(CSR)やサステナビリティへの貢献にも直結します。
近年では、脱脂剤の選定基準に「環境負荷指標(LCA)」や「カーボンフットプリント」が含まれるケースも増えています。
総じて、脱脂方法を選定する際には、脱脂性能だけでなく「環境・安全・法規制・コスト」を総合的に評価することが求められます。
これにより、持続可能かつ信頼性の高いものづくりを実現できるのです。
アスクでは脱脂洗浄を行った後に、検査、出荷まで行っております。
試作全国対応!
簡単・最短1時間お見積り
※こちらの記事はAIを参照して記事作成しております。
正しい情報かどうかは保証しかねますので、ご自身でお調べいただくようお願いします。


