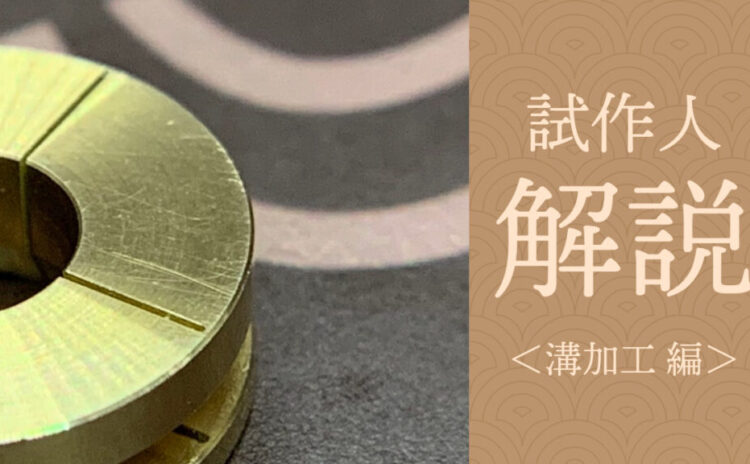「溝加工の基礎と応用:精密な溝加工技術の解説
溝加工は、機械部品や金型、木工製品などの製造において、部品同士の組み合わせや機能性を高めるために不可欠な技術です。
この加工方法では、材料に対して特定の形状の溝を形成することで、組み合わせ精度の向上や機能性の追加が可能となります。
本ページでは、溝加工の基本的な概念から、代表的な加工方法や使用される工具、さらには実際の応用例に至るまで、詳細に解説します。
これにより、溝加工の理解を深め、実務での活用に役立てていただけることを目的としています。
溝加工とは
溝加工とは、金属や樹脂などの素材に対し、特定の形状の「溝(ミゾ)」を形成するための切削加工を指します。
溝は、部品の機能や組立にとって極めて重要な役割を果たしており、トルク伝達や位置決め、シーリング(密閉)、止め構造など、さまざまな機械的・機能的ニーズに応じた形状が存在します。
たとえば、軸と歯車を連結するためのキー溝、油漏れ防止に用いられるOリング溝、固定用のスナップリング溝などがその代表例です。
このような溝の形状や寸法は、JIS(日本産業規格)やISOなどの規格で定められていることが多く、設計図に明示された寸法公差を厳密に満たす必要があります。
一般的な切削加工と比較して、溝加工は「狭く」「深く」「正確に」削るという性質を持つため、使用する工具や機械、加工条件の選定には高度な知識と技術が求められます。
加工方法には、フライス盤による側面切削、旋盤による円周方向への溝入れ、マシニングセンタによる複雑な輪郭形成、さらには放電加工やワイヤーカットといった非接触加工まで、多様な手法があります。
それぞれの手法には得意分野があり、たとえばフライス加工は直線的な溝に、旋盤加工は円筒形部品の溝に、マシニングセンタは3D形状や異形の溝加工に適しています。
使用される工具も、エンドミル、溝入れバイト、スロットカッター、Tスロットミルなど、目的に応じて選択されます。
溝の形状もさまざまで、単純な矩形(四角)断面だけでなく、V字型、U字型、T型、段付き形状などがあります。
特にT溝などは工具のアンダーカットが必要であり、専用のTスロットカッターを使用する必要があります。
また、深く狭い溝では、切りくずの排出やビビリ振動の抑制、工具折損のリスク管理など、加工上の課題が多く発生します。
加えて、溝加工は「機能の基礎」となるケースが多く、失敗や寸法不良が許されにくい工程でもあります。
例えば、Oリング溝が正確でなければ液体の漏れにつながり、キー溝の精度が不十分であればトルクが正しく伝達されず、機械の破損や故障の原因にもなり得ます。
このため、加工前には十分な図面確認や工程設計が行われ、加工中には寸法測定や試し嵌めなどの品質確認が欠かせません。
さらに、最近ではCAD/CAMの進化により、複雑形状の溝でも高精度に加工できる環境が整ってきています。
3DモデルをベースにしたCAMプログラムによって、工具経路の自動生成や干渉チェックが行えるようになり、以前よりも短時間かつ高精度な溝加工が可能となっています。
また、難削材(チタン、インコネルなど)においても、最新の超硬工具や高圧クーラントの活用によって、安定した溝加工が行えるようになっています。
総じて、溝加工とは「ただの凹形状をつくる作業」ではなく、設計機能・性能・安全性に直結する重要工程であり、高度な加工技術と精密な品質管理が要求される分野です。
工作機械と工具の進化とともに、今後もさらに多様なニーズに応える溝加工技術が求められていくことでしょう。
代表的な溝加工の種類
キー溝加工
キー溝加工は、回転する軸と歯車、プーリー、カップリングなどの機械要素を確実に結合し、トルク(ねじり力)を伝達するための溝を形成する加工です。
主に軸方向に平行な溝を軸または穴に設け、そこにキー(金属製の棒状部品)を挿入することで、軸と回転体の相対回転を防ぎます。
これにより、駆動力のロスなく動力が伝わる構造が構築されます。
キー溝には、主に2種類の加工対象があります。
一つは「軸側(外径側)」のキー溝で、これは主に旋盤またはキーシーターによって加工されます。
もう一つは「穴側(内径側)」のキー溝で、こちらはブローチ盤による加工が一般的です。
内径のキー溝加工は、工具の進入が制限されるため難易度が高く、専用の工具と機械が必要となるケースが多くあります。
キーの形状には平行キー、すり割りキー、ウッドラフキーなどがあり、それぞれに適した溝加工の形状と寸法が存在します。
これらはJIS B1301などの工業規格により、キー幅やキー深さ、溝の長さなどが細かく規定されています。
設計通りに加工されていない場合、締結力不足やガタつきによる異常振動、過度の摩耗、最悪の場合はキーの破損や軸の空回りといった重大なトラブルを引き起こす可能性もあるため、非常に厳格な寸法管理が求められます。
近年では、マシニングセンタを用いてポケット加工としてキー溝を削り出すケースや、ワイヤーカット放電加工によって高精度な内径キー溝を形成する例も増えています。
特にマシニングによるキー溝加工は、穴あけ→スロットミル加工と進めることで、段取りを少なく一体化した高精度加工が可能となります。
また、キーが不要な「スプライン」などの代替構造が選ばれることもあり、設計者はその用途や機能に応じた選択が必要です。
Oリング溝加工

Oリング溝加工は、液体や気体の漏れを防止するためのシーリング機構として、Oリングを正しく機能させるための凹形状の溝を設ける加工です。
Oリングは、断面が円形をした弾性体で、溝に圧縮された状態で装着されることで、密封効果を発揮します。
この密封性能を最大限に発揮させるには、溝の寸法精度と表面状態が非常に重要となります。
Oリング溝は大きく分けて、円筒形状の内径または外径に設けられる「円周溝」と、平面上に設けられる「面溝」に分類されます。
円筒部品に設けられる場合は旋盤加工が、平面部品の場合はマシニングセンタによるエンドミル加工が主に用いられます。
近年は3D CADとCAMによるプログラムで、溝深さや位置精度を高いレベルで制御できるようになっており、複雑な形状のシール部品にも対応が可能です。
Oリング溝の設計においては、Oリング自体の断面径(線径)と材質に加え、使用圧力、流体の種類、温度などを考慮した寸法が求められます。
一般に、Oリングの断面径に対して約10〜30%の圧縮率になるように設計されており、溝が浅すぎると圧縮過多による早期摩耗や破損が、深すぎるとシール不足による漏れが発生します。
JIS B2401などの規格に基づいた設計が一般的です。
また、用途によっては標準的な丸溝以外にも、D型断面に対応したD溝や、後加工で既存部品にOリングを組み込むためのレトロフィット溝など、さまざまなバリエーションがあります。
これらは特定の設計要求やスペース制約に対応するために採用されるもので、加工にも一層の精度と工夫が求められます。
最終的には、Oリングの座りや圧縮状態が均一であること、表面粗さが適切(通常Ra3.2以下)であること、バリや面取りが適切に施されていることが、漏れのない信頼性の高いシール構造につながります。
ゆえに、Oリング溝加工は単なる「溝を削る」作業ではなく、精密機械の耐久性や安全性を支える重要な要素と言えます。
スナップリング溝加工
スナップリング溝加工は、スナップリング(止め輪)と呼ばれる弾性部品を取り付けるために、軸または穴の所定位置に溝を形成する加工です。
スナップリングは軸方向の動きを規制するための部品で、組立品の一部が抜け落ちないように機械的に止める役割を果たします。
構造はシンプルですが、適切な位置と精度での溝加工が製品の性能や安全性を大きく左右します。
スナップリングには、外径側に取り付ける「軸用」と、内径側に取り付ける「穴用」があります。
それぞれに対応する溝形状がJIS B2804などの規格により細かく定義されており、溝幅、溝深さ、エッジの面取り寸法、さらにはリングの拡張・圧縮時に必要な逃げ寸法まで規定されています。
特に溝幅はリングの厚みに対してごくわずかなクリアランスで設計されるため、加工公差±0.02mm以内の精度が求められることも少なくありません。
加工には主に旋盤が使用されます。
溝入れバイトや突っ切りバイトと似た形状の専用チップを使い、外周または内周に所定の幅と深さで溝を形成します。
CNC旋盤であれば、位置決めや深さ制御が高精度に行えるため、量産品においても安定した加工が可能です。
一方、マシニングセンタを用いて内径側の溝を加工する場合には、専用の溝入れ工具を用い、軸方向からの切削が行われることがあります。
スナップリング溝加工では、以下のような点が非常に重要です。
・底面の面粗度:リングがしっかりと座るよう、底部の加工面は平滑である必要があります。通常Ra1.6以下が望ましいとされます。
・面取り・バリ除去:リングを挿入・取り外しする際の損傷を防ぐため、エッジ部の面取りやバリ取りは必須です。加工後のバリ残りは、リングの変形や取り付け不良の原因となります。
・リングの耐荷重に見合った加工強度:高回転・高負荷の環境では、リングの脱落や変形が致命的な故障につながるため、素材の強度や熱処理、リングの嵌合強度も考慮した設計・加工が求められます。
このように、スナップリング溝は部品同士を保持するという「最終防壁」のような役割を担っており、目立たない存在でありながら製品全体の信頼性を支える重要な加工といえるのです。
加工方法による分類
旋盤加工による溝加工
旋盤加工による溝加工は、円筒形状の部品に対して、外径または内径に同心円状の溝を形成する加工方法であり、特に軸や筒状の部品において極めて重要な工程のひとつです。
回転するワークにバイト(切削工具)を当て、所定の位置に軸方向または端面方向に切り込みを入れることで、精密な溝を効率よく形成することができます。
この加工法で対応できる溝の種類は非常に多様で、たとえば「スナップリング溝」「Oリング溝」「Cリング溝」「シール溝」「段付き溝」「ねじ下穴溝」などが挙げられます。
特に量産される回転部品では、これらの溝が規格通りに配置されていることが、組立精度や機能性に直結します。
旋盤で溝加工を行う際には、主に次の2種類の工具が使われます。
・突っ切りバイト(または溝入れバイト):細く、突き出し量の少ない刃先形状を持ち、正確に溝幅をコントロール可能。切れ味が良く、バリの少ない仕上げが可能です。
・インサート式のスローアウェイチップ:量産向けに適した高耐久性の工具で、溝幅のバリエーションも豊富。チップ交換により常に安定した品質を保てます。
加工方法としては、まずセンターを基準としたワークの芯出しを行い、その後、X軸(径方向)とZ軸(長手方向)の位置決めを行って、目的の位置にバイトを送り込みます。
切り込みは段階的に行い、最終的な溝幅・溝深さに到達させます。
高精度な機械では、NC旋盤によって自動的に工具の位置と送り速度を制御することで、±0.01mm単位の精度で溝加工が可能です。
溝の精度を確保するうえで重要な要素は次のとおりです。
・溝幅の均一性:例えばスナップリング溝では、リングがしっかりと座るために一定の溝幅が求められます。溝幅が不均一だと、リングが浮いたり、動いてしまうリスクがあります。
・面粗度:Oリングやシール溝などの場合、溝底の面粗度がシール性に大きく影響します。Ra1.6〜3.2程度が求められることが多く、仕上げ切削や研削が必要な場合もあります。
・バリやエッジ処理:切削後のバリや鋭角なエッジは、組付け時の部品損傷やOリングの破損の原因になります。面取りやバリ取りを適切に施す必要があります。
また、溝の形状や配置によっては、旋盤に対する工夫も必要です。
たとえば内径側に溝を設ける「内径溝加工」では、内径用の細長いバイトを使用することになり、工具の剛性低下によるビビリ(振動)が起こりやすくなります。
このような場合、切削条件の最適化(回転数を下げる、送りを緩める)や工具形状の最適化が求められます。
さらに、複数の溝を連続的に加工する場合や、複雑な形状の組み合わせがある場合には、CNC旋盤(コンピュータ制御)や複合加工機を使用することで、段取り替えなしに高精度な加工を効率的に行うことが可能です。
これにより、工程数削減とコストダウンにも寄与します。
旋盤による溝加工は一見シンプルに見える工程ですが、設計意図を正確に理解し、寸法、精度、表面状態などをすべて満たす必要がある、非常に奥の深い加工です。
特にシール性や強度、安全性に関わる溝では、わずかなズレが全体の性能に大きな影響を及ぼすため、熟練の技能と高度な設備の両方が求められる工程といえるでしょう。
マシニングセンタによる溝加工

マシニングセンタによる溝加工は、NC制御(数値制御)された多軸機械を用いて、高精度・高効率で多様な溝形状を加工する方法です。
フライス盤に似た構造を持ちながらも、自動工具交換(ATC)機能、同時多軸制御、3次元加工能力などを備えており、複雑な形状や複数の溝加工を一台で連続的に実施できるのが最大の特長です。
近年の溝加工現場において、マシニングセンタは欠かせない存在となっています。
多様な溝形状に対応できる柔軟性
マシニングセンタでは、直線溝や段付き溝はもちろん、曲線溝、ポケット状の溝、T溝、アンダーカット溝など、従来の汎用フライス盤では困難だった複雑な形状にも対応できます。
特に3軸~5軸の同時制御が可能な機種では、斜め方向や球面上に溝を設けるような3次元的な加工にも対応できるため、航空機部品や金型部品など、要求精度と複雑性の高い分野で重宝されています。
工具の選択と自動交換
溝加工には通常、エンドミル(スクエア・ボール・ラフィングなど)やTスロットカッター、溝用特殊バイトなどが使用されます。
マシニングセンタでは、工具交換がプログラムによって自動で行われるため、溝の幅や深さ、形状に応じて最適な工具を瞬時に切り替えて加工を続行できます。
これにより、作業効率が大幅に向上し、ヒューマンエラーも削減できます。
プログラムによる精密制御
CAMソフトと連携することで、CADデータから自動で加工経路(ツールパス)を生成できるため、手作業での寸法入力や位置合わせが不要になります。
これにより、加工精度の安定化と、段取り時間の短縮が図れます。
また、複数の溝を一つのプログラムで一貫して加工することができ、位置ズレや工程間の誤差が発生しにくいのも大きな利点です。
加工精度はミクロン単位で管理可能であり、直線性、平行度、溝深さの均一性など、設計通りの形状を再現することが可能です。
特に、深く狭い溝や、形状が連続する溝(連結スロットなど)では、その真価を発揮します。
加工の安定性と自動化への展開
マシニングセンタの高剛性構造と精密な送り制御により、工具の振れやビビリが少なく、溝底の面粗度も高い水準で仕上げることができます。
また、高圧クーラントやチップブロー装置を備えた機種では、深い溝でも切りくず詰まりを防ぎ、加工の安定性が保たれます。
さらに、ロボットによるワーク供給、自動測定プローブによる加工寸法のフィードバック制御、IoTによる加工状態のリアルタイム監視など、マシニングセンタはスマートファクトリー化との相性も良く、溝加工の無人化・自動化が可能です。
注意点と課題
一方で、マシニングセンタによる溝加工にはいくつかの課題も存在します。
例えば、アンダーカット溝や底面に凹みがあるような形状は、工具の形状制限により一発での加工が困難な場合があります。
そのような場合は専用の特殊工具を設計したり、ワークの向きを変えて複数方向から加工する必要があります。
また、機械そのもののコストが高額であること、複雑なNCプログラムの作成と検証に時間がかかることもあり、少量生産や簡易な溝加工では逆に非効率となる場合もあります。
総じて、マシニングセンタによる溝加工は、「高精度」「高効率」「高柔軟性」を兼ね備えた非常に優れた加工方法です。
特に複雑な部品形状や多品種少量生産の現場では、その真価を存分に発揮します。
今後、AIやIoTと連携したスマートマシン化がさらに進めば、より高度で自律的な溝加工が実現されていくことでしょう。
放電加工による溝加工
放電加工(EDM:Electrical Discharge Machining)による溝加工は、電気エネルギーを用いて金属表面を選択的に溶融・蒸発させて形状を削り出す特殊加工法です。
主に導電性を持つ材料が対象で、機械的な切削では加工困難な形状や高硬度材に対して、高精度かつ非接触で溝を形成できるという特長があります。
溝加工の中でも特に微細で複雑な形状、または深くて細い溝を形成する場合に非常に有効です。
放電加工には主に2つの方式があります。
・型彫り放電加工(Die-sinking EDM)
電極を型として使用し、ワークに対してその形状を焼き付けるように加工する方法。
深さ方向の制御に優れており、複雑な三次元形状や封じられた溝にも対応できます。
・ワイヤーカット放電加工(Wire-cut EDM)
直径0.1~0.3mm程度の細いワイヤーを電極として用い、ワークをスライスするように切削する方式。
高精度なスリット溝や矩形溝、曲線溝などの加工に適しています。
特徴とメリット
放電加工による溝加工の最大の利点は、「非接触加工」である点です。
切削加工のように工具が物理的にワークに触れないため、以下のようなメリットがあります。
・高硬度材料に対応
超硬合金、焼入れ鋼、インコネル、チタンなど、従来の工具では切削困難な材質にも容易に加工可能。
・工具摩耗が少ない
ワイヤーや電極の消耗はあるものの、切削工具のような急激な摩耗は発生せず、安定した精度を維持できます。
・微細形状が可能
0.1mm以下の細溝や、交差部のある複雑な輪郭など、マシニングセンタでは不可能な形状の再現が可能。
・応力・変形が少ない
切削時に発生する切削力や熱による歪みが少なく、薄肉部品や微細部品でも変形のない加工が可能。
これらの特徴から、金型、医療機器、電子部品、航空宇宙分野など、超高精度を必要とする分野で活用されています。
溝加工への応用例
・キー溝やスリットの微細加工
ワイヤーカット放電加工では、0.1~0.2mmの超細幅の溝を直線または曲線状に加工可能。
切削工具では不可能な極小Rや鋭角も実現できます。
・アンダーカット構造の形成
型彫り放電加工では、複雑な陰形(凹形状)の溝を専用電極で彫り込むことができ、たとえば逆テーパーや多段構造の溝加工が可能です。
・深溝・細溝の加工
深さに対して幅が非常に狭いような形状(たとえば深さ10mmで幅0.2mmの溝など)は、機械加工では工具が入らず困難ですが、放電加工では比較的容易に対応可能です。
注意点・制限
一方で、放電加工にはいくつかの制限や注意点も存在します。
・加工時間が長い
加工速度は切削に比べて遅く、特に深い溝や広範囲の加工では長時間を要します。
そのため、量産品や粗加工には不向きです。
・電極の設計が必要(型彫り放電の場合)
電極は消耗品であり、形状によっては精密に加工された専用電極を用意しなければならず、段取りにコストと時間がかかります。
・加工面に白層が発生する
加工によって生成された再凝固層(白層)は、材料によっては脆く、後工程で研磨や除去処理が必要となることがあります。
・導電性のある材料に限定される
樹脂やセラミックなど、電気を通さない材料には使用できません。
放電加工による溝加工は、他の加工法では実現困難な形状や精度を可能にする革新的な技術です。
時間とコストの面では制約がありますが、微細・複雑・高硬度という加工の3大課題に対しては、非常に有効な選択肢であるといえるでしょう。
特に精密部品や試作、特殊用途の部品においては、放電加工の溝加工技術が不可欠なものとなっています。
ブローチ加工による溝加工
ブローチ加工は、特殊な多刃工具(ブローチ)を用いてワークに連続的に切削力を加えることで、精密な形状を一工程で仕上げる加工法です。
溝加工においては、特に内径側のキー溝加工やスプライン溝加工に用いられ、高精度かつ安定した量産性が求められる場面で活躍します。
ブローチ盤という専用機を使用し、ワークに対してブローチ工具を直線的に押し込む、あるいは引き抜くことで加工を行います。
ブローチ加工の構造と原理
ブローチ工具は、先端から順に「粗削り部」「中仕上げ部」「仕上げ部」と段階的に刃が並んでおり、1回のストロークで粗加工から仕上げ加工まで完了します。
この段階的な構成により、工具の一部が削るごとに少しずつ切込み量が増加していき、最終的に目標寸法・形状に仕上がるという仕組みです。
この一連の加工は極めて再現性が高く、同一形状の溝加工を多数製作する必要がある場合に非常に適しています。
また、寸法のばらつきが少なく、加工面も高品位に仕上がることから、量産品に多用されています。
主な用途と特徴
ブローチ加工は、以下のような用途で溝加工に活用されます。
・内径キー溝
モーターシャフトやギアボックス内部など、部品の中心部にキーを通してトルクを伝えるための溝。
キー溝の幅、深さ、位置精度を高いレベルで維持でき、JIS規格にも完全に準拠可能。
・スプライン溝
軸とハブを高トルクで連結する際に必要な多条のキー溝。
ブローチ加工では、複数の溝を一工程で同時に高精度に成形できます。
・角形、星形、六角などの穴形状
ブローチ工具の形状に応じて、回転防止のための特殊内径形状を一発加工できるのも特長です。
・冷間鍛造やプレス成形品の仕上げ加工
前工程で成形された粗形状に対して、寸法仕上げや表面品質向上の目的で用いることもあります。
・加工精度と生産性
ブローチ加工は非常に高い寸法再現性と面粗度を実現可能です。
一般に、±0.01mm程度の公差管理が可能で、表面粗さもRa0.8以下まで仕上げられるケースもあります。
さらに、1ストロークで1個の加工が完了するため、サイクルタイムも短く、大量生産に最適です。
また、ブローチ工具の刃数が多いため、1回の加工で段差の少ない均質な切削ができ、加工面にむらが出にくいのも利点です。
量産性と加工品質を両立できる点が、他の溝加工法と比較した際の最大の強みといえるでしょう。
注意点・課題
一方、ブローチ加工にはいくつかの注意点や制約があります。
・専用工具のコストが高い
ブローチはワーク形状に応じた専用設計であるため、初期費用が非常に高額です。
形状変更があると、工具を再設計・再製作する必要があり、小ロットには不向きです。
・専用機が必要
ブローチ加工には通常、専用のブローチ盤が必要です。
横型・縦型・プッシュ式・プル式などがありますが、汎用設備では対応できないため、設備投資が求められます。
・加工材質に制限あり
加工に耐えるだけの靱性や延性を持つ素材でないと、クラックや欠けが発生するリスクがあり、材質選定にも注意が必要です。
・加工範囲の制限
ワークサイズ、穴径、溝長さに応じて適切なブローチサイズが必要であり、大型・複雑形状には不向きな場合があります。
総じて、ブローチ加工による溝加工は「量産性」「再現性」「精度」に優れ、特に内径側の溝において他の追随を許さない強力な加工法です。
ただし、その高い加工能力を引き出すには、専用工具と機械、設計段階からの綿密な計画が必要です。
大量生産向けの戦略的な加工方法として、現在も多くの製造業で活躍し続けています。
T溝加工
T溝(ティースロット)加工は、工作機械のテーブルや治具、金型ベースなどにおいて、ボルトやナットを嵌合・締結するために使用される特殊な溝形状を形成する加工法です。
溝の断面がT字のような形状をしていることからその名がついており、主に「上部に開口した直線溝」と「下部に広がったアンカー状の空間」を組み合わせた構造です。
T溝は、締結具を自由にスライドさせながら所定の位置に固定できるという特性があり、工作物のクランプや治具の可変設計に大きく貢献します。
実用性・メンテナンス性に優れ、強固な締結力を確保しながらも作業性を高められるため、多くの産業機械や治具で採用されています。
T溝の基本構造と用途
T溝は、一般に以下のような構成要素から成ります。
・上部開口部(ストレート溝):ワーク表面からアクセスする部分で、締結具が自由に移動できるように直線状の開口が設けられています。
・下部広がり部(T形状部):ボルトの頭やTナットなどを収納し、引き上げたときに力が安定的に伝わる形状です。
代表的な用途は以下の通りです。
・工作機械のテーブル(例:フライステーブル)
・溶接治具や検査治具
・金型ベースの部品固定用
・モジュール組立ラインのスライドガイド
T溝の加工手順と使用工具
T溝加工は、通常、以下の手順で段階的に行われます。
・直線溝の荒加工
エンドミルやスロッターを使って、T溝の上部直線部分を所定の幅と深さに荒削りします。
・Tスロットカッターによる下部加工
T字の下部にあたる広がり部分は、専用のTスロットカッター(T溝カッター)を使って切削されます。
この工具は首の細い形状で、切削部分が横に広がった特殊な構造をしています。
・仕上げとバリ取り
精度が求められる箇所では仕上げ加工を施し、バリやエッジ部の処理を行います。
精度管理と注意点
T溝の寸法にはJIS B 6025などの規格が定められており、ナットの嵌合状態やボルトの走行性に影響するため、以下の項目に特に注意が必要です。
・溝幅・深さ・底面幅の精度
・上部と下部の同心度(芯ズレ)
・面粗さ(ボルト摺動部での摩擦低減)
また、Tスロットカッターは折れやすく、無理な切込みや送り速度は厳禁です。
特に下部の広がり部分は切りくず排出性が悪いため、クーラントやエアブローによる切粉処理も重要となります。
U溝・V溝加工

U溝・V溝加工は、それぞれ「半円形」や「V字形」の断面形状をもつ溝を形成する加工であり、用途や目的に応じて様々な部品や治具、構造体に活用されます。
どちらも滑りや誘導、シール保持、位置決め、圧力分散など、多様な機能を果たすため、設計上の選択肢として重要な位置を占めます。
U溝加工の特徴と用途
U溝は、滑らかな半円形状の断面を持つ溝で、主に以下のような用途に使われます。
・Oリング・ゴムパッキン保持用溝
シール性を高めるため、円形断面のOリングが収まるように、接触面積が最大となるU溝形状が選ばれます。
これにより圧縮率と漏れ防止性能のバランスが最適化されます。
・ガイドローラーやボールの案内溝
転がり案内機構では、ローラーや球体を滑らかに転がすために、U字形状のレールや案内部品が多用されます。
・ドレンや流体誘導の溝
液体の排出経路や誘導路において、流体抵抗を最小限に抑えるために半円形状が好まれることがあります。
U溝の加工には、専用のU溝カッター(ボールエンドミルやラジアスカッターなど)が使用されます。
工具のR形状が溝形状と一致するよう設計されており、等高線切削や円弧補間によって精密な加工が可能です。
V溝加工の特徴と用途
V溝は、文字通り「V字形」の鋭角な断面形状を持つ溝で、以下のような応用例があります。
・ベルトのガイドレール
Vベルトやタイミングベルトを案内するための溝形状として、滑り止めとセンター保持の機能を果たします。
・センター位置決め用
丸棒などをV溝上に置くことで、自然にセンターへ位置決めされる構造に。
計測治具や工作機械の芯出しに利用されます。
・装飾・彫刻加工
シャープなV字形状を用いたデザインや彫刻加工、またはアルミ建材やパネルの折り曲げ前加工などにも用いられます。
V溝加工には、Vカッターやチップ交換式のV型エンドミルなどを用い、角度や深さを高精度にコントロールします。
一般的には60度、90度など一定の角度が用いられ、用途に応じて形状設計が求められます。
加工上の注意点
U溝・V溝は見た目は単純ですが、次のような点に注意する必要があります。
・R部・角部の加工精度と工具選定
工具形状がそのまま加工結果に反映されるため、工具摩耗や取り付け精度が仕上がりに直結します。
・切りくずの排出性
特に深溝では切粉が詰まりやすく、加工面の荒れや工具破損の原因になります。
・溝底面の面粗度と仕上がり
シール用途では特に重要で、過剰な粗さや段差は漏れや摩耗の原因になります。
これらの溝加工は、部品設計や機能要求に対して重要な役割を果たしており、精度・工具選定・加工条件の最適化によって、信頼性と耐久性の高い製品へとつながります。
試作全国対応!
簡単・最短1時間お見積り
※こちらの記事はAIを参照して記事作成しております。
正しい情報かどうかは保証しかねますので、ご自身でお調べいただくようお願いします。