S10C:加工性とコストパフォーマンスに優れた低炭素鋼の基本特性
S10Cは、日本工業規格(JIS G 4051)で規定される機械構造用炭素鋼鋼材の代表的な低炭素鋼であり、炭素含有量が約0.07〜0.13%と低く抑えられている点が最大の特徴です。
この炭素含有量の低さによって、S10Cは他の炭素鋼と比較して加工性と靱性(粘り強さ)に優れ、切削や塑性加工といった機械加工用途において高いコストパフォーマンスを発揮します。
さらに、S10Cは熱処理による硬化性が低いという特性を持つ一方で、変形や割れが生じにくい材料特性として幅広い産業分野で利用されている汎用的な鋼材です。
本稿では、S10Cの基本特性と加工上の注意点、他鋼材との比較を通じて、その選定・活用におけるポイントを解説します。
S10Cとは
S10Cは、日本工業規格(JIS)に基づく炭素鋼の一種で、正式には「機械構造用炭素鋼鋼材(JIS G 4051)」に分類される材料です。
「S10C」の名称は、JIS規格の命名ルールに従っており、「S」は「Steel(鋼)」を、「10」は炭素含有量をおおよそ0.10%程度含むことを示し、「C」は「Carbon(炭素鋼)」を意味しています。
このように、S10Cは炭素量が比較的低く、軟らかく加工性に優れた構造用鋼として広く利用されています。
S10Cの最大の特徴は「低炭素鋼」であるという点です。
一般に、鋼材は含有する炭素量によって性質が大きく変わりますが、S10Cは炭素含有量が0.08~0.13%程度と少ないため、硬さや強度よりも、加工性や靱性(粘り強さ)に優れた材料です。
このため、切削加工や塑性加工(プレスや鍛造)に適しており、複雑な形状を加工する部品にも向いています。
また、S10Cは熱処理による硬化性が低いため、焼入れによる強化には適していません。
しかし、逆にこの性質は変形や割れが起こりにくいという利点でもあります。
そのため、機械的強度よりも成形性や加工後の安定性が重視される用途において、非常に有効な材料とされています。
さらに、S10Cは安価で入手性が良いため、試作部品や治具、あるいは製造工程の仮部品などにもよく使われます。
また、製品寿命よりもコストが重視される大量生産品の一部にも採用されることがあります。
工業分野では「軟鋼」と呼ばれるグループに属し、SS400などの一般構造用圧延鋼材と用途が重なる場面もありますが、S10Cはより機械加工を前提とした設計に適しているという違いがあります。
特に旋盤やフライス盤による切削加工、冷間鍛造などとの相性が良く、一定の寸法精度や表面仕上げが求められる製品に対しても対応可能です。
まとめると、S10Cは低炭素・低強度・高加工性という特性を活かし、機械構造用のベーシックな材料として広く使用されている汎用的な炭素鋼です。
用途の幅も広く、設計や製造の入門的素材としても重宝される存在です。
成分組成と特徴
S10Cは、JIS G 4051に規定される機械構造用炭素鋼の中で、炭素含有量が最も少ないグレードの一つです。
その成分組成は非常にシンプルで、炭素(C)と鉄(Fe)を主成分とし、ごく微量のマンガン(Mn)やリン(P)、硫黄(S)などを含んでいます。
以下に、JIS規格におけるS10Cの代表的な化学成分範囲を示します。
| 元素 | 含有量(質量%) |
|---|---|
| C(炭素) | 0.07~0.13 |
| Si(ケイ素) | 0.10~0.35 |
| Mn(マンガン) | 0.30~0.60 |
| P(リン) | 0.030以下 |
| S(硫黄) | 0.035以下 |
このように、S10Cは低炭素鋼に分類され、C量が少ないことで特徴づけられます。
炭素は鋼の硬さと引張強さを決定づける重要な元素ですが、S10Cではあえてその量を抑えることで、「やわらかさ」「粘り強さ」「加工のしやすさ」といった性質を強調しています。
加えて、SiやMnの量も控えめに設定されています。
Siは脱酸剤としての役割が主で、Mnは熱処理や鍛造時の変形を抑え、靱性を高める効果がありますが、S10Cではこれらの元素も中程度に抑えられており、全体として“素直で加工しやすい”性質となっています。
一方で、PやSは基本的に有害元素とされ、鋼の脆性を高めたり、溶接性を悪化させたりするため、規格で上限値が設けられています。
これらの不純物の含有量が低いことも、S10Cの安定した品質と加工性を支える重要なポイントです。
S10Cの物理的な特徴としては、引張強さはおおよそ350~450MPa程度、降伏点は200MPa前後、伸びは30%以上とされており、これらは非常に“軟らかい鋼”という印象を与える数値です。
また、焼入れによる硬化が難しく、熱処理後の高硬度化を期待する場合には他の中~高炭素鋼(例:S45C、S50C)を選択する必要があります。
なお、炭素量が低いため、常温での延性(伸びやすさ)や靱性(粘り強さ)が高く、衝撃に対する抵抗性もある程度備えています。
これにより、折損や割れが生じにくい部品に仕上げることが可能です。
反面、表面硬度が欲しい場合には、高周波焼入れや浸炭処理などの表面熱処理を併用する必要があります。
S10Cは、このようなシンプルな成分と性質を持つことから、品質が安定しており、加工現場においても取り扱いやすい素材です。
特に、形状が複雑だったり、加工工程が多段階にわたる場合でも、素材そのものが柔軟に対応できるという点で高く評価されています。
JIS規格における位置づけ
S10Cは、日本工業規格(JIS)のうち、JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」に分類される代表的な材料です。
このJIS G 4051は、炭素鋼のうち機械部品などの構造用途に使用される鋼材を対象としており、主に炭素含有量によって分類されています。
その中で、S10Cは炭素量が最も少ないグレードであり、低強度ながらも高い延性や加工性を特徴としています。
JIS規格における機械構造用炭素鋼の分類は、炭素量の違いによってS10CからS58Cまで多くのグレードが存在します。
例えば、S10C、S25C、S45C、S55Cなどは炭素量の増加に伴って強度や硬度が高まりますが、それに反比例する形で靭性や加工性、溶接性が低下していきます。
そのため、使用目的や加工方法に応じて適切なグレードが選定されます。
以下は、JIS G 4051におけるS10Cの代表的な位置づけを示す簡易的な表です。
| 鋼種名 | 炭素量(%) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| S10C | 0.07〜0.13 | 加工性・溶接性に優れる、低強度 |
| S25C | 0.22〜0.28 | バランス型、一般機械部品向け |
| S45C | 0.42〜0.48 | 高強度・熱処理性が良好 |
| S55C | 0.52〜0.58 | 高硬度、工具や金型部品向け |
S10Cは、このようなグレード体系の中で「軟鋼(mild steel)」としての役割を果たしており、他の炭素鋼よりも構造的な強度は劣りますが、コストパフォーマンスと加工のしやすさにおいて優れた選択肢とされています。
また、JIS G 4051は製品の形状ごとに適用される範囲が決まっており、S10Cは主に「熱間圧延材」「鍛造材」「引抜材」などの形で供給されます。
加えて、板材ではなく「棒鋼」や「丸棒」として使用されることが一般的です。
これにより、旋盤加工やフライス加工などの機械加工に適した材料形状が提供されており、加工現場での扱いやすさが確保されています。
さらに、S10Cは国際規格との比較においても位置づけが明確で、たとえばISOやDIN、ASTMなどの海外規格における類似材と照らし合わせることで、グローバル調達や設計時の互換性も検討可能です。
具体的には、ISO 683-1では「C10E」、DIN規格では「1.1121」や「C10」、ASTMでは「A29/A29M SAE 1010」などが近い材質に該当します。
このように、JIS G 4051におけるS10Cは「構造用低炭素鋼」としての明確なポジションを持っており、設計者や製造現場においても「低強度だが加工性重視の鋼材」という共通認識のもとで広く活用されています。
その使いやすさと規格の明確さから、多くの機械部品設計でベース材料として重宝されているのです。
加工性と使用上の注意点
被削性と加工時の工夫
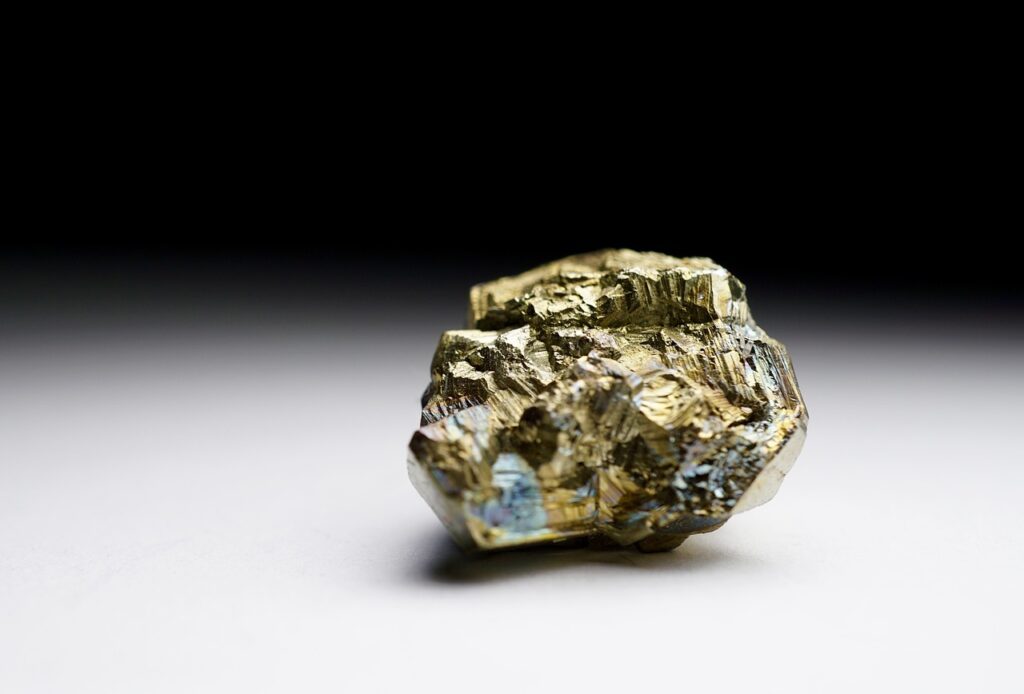
S10Cは、低炭素鋼であることから、一般的に被削性に優れた鋼材とされています。
炭素量が少ないため硬さが低く、刃物への負担が少ないことから、旋削、フライス、穴あけ、ねじ切りなどの機械加工において比較的容易に切削加工が行えます。
また、加工中にバリが出にくく、寸法精度の管理もしやすい点で、多くの加工業者にとって扱いやすい素材とされています。
しかしながら、S10Cの被削性が高いとはいえ、注意すべき点もいくつかあります。
一つは、材料が柔らかいために「切りくず(チップ)」が細かくならず、長くつながって排出される傾向があることです。
これにより、工具やワークへの巻き付きが発生しやすく、工具破損や加工不良の原因になることがあります。
したがって、切削条件の最適化(送り速度や切削深さの調整)や、切りくずを効率よく分断できる工具(ブレーカー付きチップなど)の選定が重要です。
さらに、S10Cは硬度が低いため、表面仕上げに注意が必要です。
加工面にビビリ(チャタリング)が出やすく、仕上げ面が粗くなることがあります。
これを防ぐためには、工具の刃先状態の管理(摩耗が少ない状態で使用する)、適切な刃物材質の選定(HSSまたはコーティング超硬など)、切削油の使用などが推奨されます。
とくに高精度が求められる面に対しては、研削加工やバフ研磨による二次仕上げも効果的です。
また、S10Cは引張強さが低いため、切削中にワークが変形しやすいという側面もあります。
長尺材の加工時や、固定が不十分な場合には、加工後に反りが生じることがあるため、加工の順番や固定方法に工夫が求められます。
加工歪みを抑えるためには、加工前に材料を焼なましする、荒加工と仕上げ加工の間に応力除去処理を入れる、といった工程管理も有効です。
まとめると、S10Cは被削性に優れ、初期加工には非常に向いている鋼材ですが、柔らかさゆえの切りくず処理や変形への配慮、表面仕上げへの注意が必要です。
こうした点を理解し、工具・条件・工程の最適化を図ることで、効率的かつ高品質な加工が可能となります。
溶接性とその課題
S10Cは低炭素鋼であるため、炭素量が少なく、割れにくく、比較的良好な溶接性を持つ鋼材です。
炭素含有量が0.10%前後という低さにより、炭素による硬化や脆化が起こりにくく、アーク溶接・TIG溶接・スポット溶接など、さまざまな溶接方法に対応可能です。
特に、炭素含有量の高さにより溶接性が低下するS45Cなどに比べ、S10Cは溶接に適した材料と言えるでしょう。
しかしながら、S10Cの溶接にはいくつかの注意点も存在します。
まず、材料が比較的柔らかいため、溶接熱による歪みや変形が起こりやすい点が挙げられます。
とくに薄肉部品や長尺の構造物では、溶接後に熱による曲がりが顕著になることがあり、適切な治具を使った固定や、対称的な溶接工程の設計など、事前の工夫が求められます。
また、S10Cはリン(P)や硫黄(S)の含有量が低く抑えられているとはいえ、これらの不純物が残っている場合には、溶接熱によって脆化(ホットクラック)が発生するリスクがあります。
このような現象を防ぐために、適切な溶接棒やワイヤーの選定、予熱や後熱処理の導入が効果的です。
とくに厚板や拘束力の高い構造物では、これらの管理を怠ると、割れの発生原因となります。
さらに、S10Cは耐候性や耐食性に優れた鋼材ではないため、溶接部を含めた表面に酸化皮膜や腐食が生じやすくなります。
屋外での使用や湿度の高い環境で使う場合には、溶接後の防錆処理(塗装やメッキなど)を施すことが望ましいです。
溶接焼けを防ぐために、溶接直後にスケーリング除去や洗浄処理を行うことも、品質維持には不可欠です。
S10Cは溶接性が比較的良好で、設備の簡易な現場でも対応可能ですが、使用環境や精度要件によっては、熱影響による変形や脆化に十分配慮する必要があります。
溶接前の前処理、溶接条件の管理、後処理まで含めたトータルな対応が、高品質な製品を実現する鍵となります。
表面処理の適性(浸炭・メッキなど)

S10Cは低炭素鋼であるため、芯部は硬化性に乏しく、耐摩耗性や耐衝撃性に限界があります。
そのため、耐久性が求められる部品として使用する場合には、表面処理を施して硬度や耐食性を補う必要があります。
特に、表面硬化処理や防錆処理の適性が高く、浸炭処理、窒化処理、メッキ処理などが広く行われています。
代表的な表面処理の一つが「浸炭処理」です。
S10Cのような低炭素鋼は、炭素拡散によって表面を硬化させる浸炭処理に非常に適しており、表面は高硬度・芯部は靭性保持という二重性を持つ材料特性が実現できます。
自動車部品や機械の摺動部品などに多く使われる理由の一つがこれです。
処理後の表面硬度はHRC55程度まで達することもあり、摩耗性の改善に非常に有効です。
また、窒化処理も選択肢の一つです。
窒素を拡散させて表面を硬化させる処理であり、処理温度が比較的低いため、変形が少なく、寸法精度が求められる部品にも適しています。
ただし、S10Cは窒化処理における合金元素が少ないため、窒化層の形成は限定的となり、より高い効果を求める場合には合金鋼(例:SCM材)への変更が推奨されます。
一方、防錆目的では、亜鉛メッキ(溶融・電気)、ニッケルメッキ、クロムメッキなどがよく施されます。
特に屋外や湿気の多い環境では、S10Cは腐食しやすいため、表面コーティングが不可欠です。
メッキ処理に対する密着性も良好で、適切な前処理(脱脂・酸洗い)を行えば、均一で美しい仕上がりが得られます。
また、リン酸塩皮膜処理(パーカライジング)なども適用されており、塗装前の下地処理や摩擦低減を目的とした処理として活用されています。
こうした処理によって、S10Cは機能的にも外観的にも大きな付加価値を持たせることが可能になります。
要するに、S10Cは熱処理性には限界があるものの、表面処理との組み合わせによって非常に広い用途に対応できる鋼材です。
特に、耐摩耗性・耐食性の向上が求められる場面では、適切な表面処理の選定と工程管理が重要となります。
他鋼材との比較と選定ポイント
S45Cとの比較(炭素量と強度)
S10CとS45Cは、いずれもJIS G 4051に規定される機械構造用炭素鋼鋼材ですが、その性質は炭素含有量の違いによって大きく異なります。
S10Cが「低炭素鋼」に分類されるのに対し、S45Cは「中炭素鋼」に分類され、引張強さ・硬さ・焼入れ性などに明確な差があります。
まず、炭素含有量の違いを確認すると、S10Cは約0.07~0.13%、S45Cは約0.42~0.48%と、約3〜4倍の炭素を含んでいます。
炭素は鋼の硬さや強度を左右する主要元素であり、この差が両者の物性を決定づけています。
S45Cの引張強さはおおよそ570〜735MPa、硬度は焼入れ前でHB170〜220程度、焼入れ後はHRC50以上に達することもあります。
一方、S10Cは引張強さで約350〜450MPa、焼入れ効果はほとんど見られず、表面硬化などが必要です。このように、S45Cは高強度・高硬度を得られる鋼材であり、荷重や摩耗のかかる部品に適しています。
ただし、強度の高さは一方で、加工性の低下にもつながります。
S45CはS10Cに比べて切削時の工具摩耗が激しく、応力集中や加工歪みも生じやすいため、熟練した加工技術や高性能工具を要します。
また、溶接性もS10Cに比べて劣り、割れやすくなるため、予熱や後熱処理が必要です。
したがって、選定の基準としては「部品の求める強度・耐久性」が最も大きなポイントとなります。
寸法精度が必要で加工性を重視するならS10C、機械的強度や表面硬度が求められる用途にはS45C、という使い分けが基本です。
また、コスト面でもS10Cは安価で入手性も高いため、数量が多く、強度要件がさほど高くない部品に適しています。
強度が過剰にならないよう、製品仕様に応じた材料選定が重要です。
SS400との比較(構造用鋼材との違い)
S10CとSS400は、どちらも低炭素鋼に分類されますが、適用される規格や用途が異なるため、材料としての性格にも違いがあります。
S10Cは「機械構造用炭素鋼(JIS G 4051)」、SS400は「一般構造用圧延鋼材(JIS G 3101)」に該当し、設計や使用目的によって選定基準が変わります。
SS400は「Steel Structure」の略称で、橋梁、ビル、機械架台、建築部材などの構造物に多用される鋼材です。
その最大の特徴は「加工性と溶接性に優れ、構造強度も確保されていること」で、引張強さは400〜510MPa程度と、S10Cと大きくは変わりません。
しかし、SS400は強度や成分が比較的幅広く許容されており、「材質よりも形状や構造に基づいて使う」という設計思想が前提となっています。
一方、S10Cは機械加工用を主目的とした材料です。
SS400が溶接構造物などの製缶部材に向いているのに対し、S10Cは旋盤やフライスなどによる切削加工を前提とした設計に向いています。
成分もより厳密に管理されており、寸法精度や表面品質が求められる場面での使用が前提となっています。
また、供給形態にも違いがあります。
SS400はH形鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、板材などの定尺品として多く流通しており、建築材料としての汎用性が高い一方で、S10Cは丸棒や六角棒、鍛造材など、機械加工向けに適した形状で供給されます。
溶接性に関しては両者とも優れていますが、S10Cの方が不純物が少なく、炭素量もわずかに低めであることから、より安定した溶接品質が得られます。
反面、SS400は溶接後の熱影響部の性質変化が大きく、特に寒冷地などでは割れに注意が必要です。
選定の目安としては、「加工して使う部品」にはS10C、「構造物やフレームとしての使用」にはSS400という使い分けが基本です。
また、S10Cの方が材料ばらつきが少なく、精密加工に適している点も設計上の重要な要素となります。
SCM鋼との比較(合金鋼との選定基準)
S10CとSCM鋼(例えばSCM420やSCM435など)は、用途や特性が大きく異なる材料です。
S10Cは炭素鋼であり、SCM鋼はクロムモリブデン鋼に代表される合金鋼で、主に機械部品や構造体における高強度・耐久性が求められる場面で選定されます。
JIS規格ではSCMはJIS G 4105「合金構造用鋼」に属します。
成分面で比較すると、S10Cは炭素以外の合金元素をほとんど含まず、非常にシンプルな構成です。
一方、SCM鋼はクロム(Cr)やモリブデン(Mo)を含み、これにより焼入れ性・耐摩耗性・引張強さ・耐熱性など、多くの性能が向上しています。
たとえばSCM435は、焼入れ後の引張強さが1000MPaを超えることもあり、自動車のギアやシャフトなど、過酷な条件下での使用に耐える材料です。
加工性については、S10Cは被削性が良好であり、あらゆる加工に対応可能です。
一方、SCM鋼は強度が高いため、加工硬化しやすく、切削加工では高性能な工具や十分な冷却が必要です。
また、熱処理も複雑で、焼入れ・焼戻しの条件管理が要求される点で、製造工程の難易度が上がります。
コスト面でも両者は大きく異なります。
S10Cは安価で入手性が良いため、コストを抑えたい大量生産品や試作に適しています。
一方、SCM鋼は高価であり、材料費や加工コストも高くなりますが、耐久性を重視する部品においてはトータルでのコストパフォーマンスに優れることもあります。
用途の観点では、S10Cは軽負荷部品、仮部品、試作など、汎用的な使用に適し、SCM鋼はギア・シャフト・ピストンピンなど、高荷重や繰返し応力がかかる部品で本領を発揮します。
耐久性や信頼性が設計要件の中心となる場合は、SCM鋼の選定が妥当です。
つまり、S10CとSCM鋼の選定における基準は、「求める機械的特性」と「許容される加工コスト・工程の複雑さ」にあります。
過剰な強度が不要な場合にはS10Cで十分な性能を発揮し、必要に応じて表面処理で補強すればコスト効率の高い設計が可能です。
試作全国対応!
簡単・最短1時間お見積り
※こちらの記事はAIを参照して記事作成しております。
正しい情報かどうかは保証しかねますので、ご自身でお調べいただくようお願いします。


