SS400とは:日本の構造用鋼材のスタンダード
SS400は、日本工業規格(JIS G 3101)に基づく「一般構造用圧延鋼材」の一種であり、引張強さが約400MPa程度であることからその名称が付けられています。
この鋼材は、建築、土木、機械部品、車両など、幅広い分野で使用されており、強度、靱性、溶接性に優れたバランスの取れた特性を持っています。
特に、過剰な機能性が求められない場面では、コストパフォーマンスに優れた材料として重宝されています。
SS400とは
SS400は、JIS(日本産業規格)において定められた「一般構造用圧延鋼材(JIS G 3101)」の中で最も一般的に使用される鋼材の一つです。
名称の「SS」は“Steel Structure”を意味し、構造用鋼材であることを表しています。
続く「400」は、引張強さの下限が400N/mm²(メガパスカル)程度であることを示しています。
SS400は、機械的性質と加工性のバランスが良く、強度・靱性(じんせい)・溶接性に優れていることから、建築、土木、機械部品、車両など幅広い分野で使用されています。
特に、強度や耐久性が求められるが、高級な合金鋼やステンレスほどの耐食性や耐熱性は必要ないといった場面において、非常にコストパフォーマンスに優れた材料とされています。
JIS G 3101の中で、SS400は熱間圧延鋼材(Hot Rolled Steel)に分類されており、鋼板(plate)、鋼棒(bar)、形鋼(H形鋼やアングル鋼など)などさまざまな形状で供給されます。
この規格は、鋼材の製造方法や化学成分に厳密な制限を課していない点も特徴的です。
つまり、製造メーカーごとに若干の成分や物性の違いはあっても、引張強さや降伏点などの「機械的性質」が規格内であればSS400として流通するのです。
また、SS400は「低炭素鋼(ミディアムカーボンスチール)」に分類されることが多く、熱処理(焼入れや焼戻し)をしなくてもある程度の強度を保つことができます。
その一方で、熱処理による硬化性は限定的であり、耐摩耗性が求められる部品には不向きです。
特徴をまとめると、以下のようになります。
・機械的性質が安定している(引張強さ・降伏点が明確)
・加工性に優れる(切削・曲げ・溶接がしやすい)
・流通量が多く、価格も安定している
・耐食性には乏しく、表面処理が必要(塗装・メッキなど)
特に重要なのは、「強度とコストのバランスが非常に良い」という点です。
ステンレス鋼や高張力鋼などの高機能材に比べて性能は劣りますが、過剰品質となる場面ではSS400の方が合理的な選択肢となります。
SS400は、過不足のない標準的な性質を持った鋼材として、多くのエンジニアや設計者にとって“基準となる材料”のひとつといえるでしょう。
SS400の化学成分と機械的性質
SS400は、その名称にある通り引張強さが約400N/mm²(MPa)程度の構造用鋼材であり、JIS G 3101にて規定されています。
化学成分については、他の合金鋼のように厳密な成分配合が定められているわけではありません。
SS400は機械的性質によって等級を定める鋼材であるため、一定の強度と靱性を備えていれば、多少の成分のばらつきが許容されている点が特徴です。
化学成分の目安
以下は、一般的に市販されているSS400の代表的な化学成分の範囲(参考値)です。
| 元素 | 含有量(参考値) |
|---|---|
| C(炭素) | ≦0.25% |
| Si(ケイ素) | ≦0.35% |
| Mn(マンガン) | ≦1.60% |
| P(リン) | ≦0.050% |
| S(硫黄) | ≦0.050% |
SS400は炭素含有量が比較的少なく、軟鋼(mild steel)に分類されます。
これにより、加工性や溶接性に優れており、加熱せずに曲げたり切断したりできるため、現場での加工にも適しています。
機械的性質
SS400の機械的性質は以下の通り、板厚によって若干の違いがあります。
| 材料厚さ | 引張強さ(N/mm²) | 降伏点(N/mm²) | 伸び(%) |
|---|---|---|---|
| ≦16mm | 400~510 | ≧245 | ≧21 |
| >16~40mm | 400~510 | ≧235 | ≧21 |
| >40mm | 400~510 | ≧215 | ≧17 |
ここで注目すべきは、厚さが増すごとに降伏点が低下することです。
これは鋼材内部まで均質な冷却・圧延が難しくなるためであり、設計時には板厚に応じた強度設計が必要です。
また、引張強さに一定の幅があることから、用途によっては材料試験を通じて実測値を確認する場合もあります。
機械的性質が優れている理由
SS400は特別な合金元素を加えているわけではありませんが、製造時の圧延技術によって材料内部の組織が整えられ、均一な力学特性が得られています。
また、微量に含まれるマンガン(Mn)は、炭素との相乗効果によって引張強さや靭性を向上させる働きがあります。
使用上の注意点
SS400は低炭素鋼であるがゆえに、熱処理(焼入れ)による硬化性は低いという特性があります。
そのため、耐摩耗性や高強度を要求される用途には不向きです。
また、耐食性も高くないため、屋外や湿度の高い環境で使用する場合は防錆処理が不可欠です。
溶接性には優れていますが、厚板同士の溶接には適切な前処理(予熱)を行うことで、溶接割れなどのリスクを軽減できます。
SS400の加工性と取り扱い

SS400の切削・溶接性
SS400は、一般構造用鋼材として広く使用されている理由の一つに、「加工のしやすさ」があります。
とくに、切削加工や溶接加工においてその扱いやすさが際立っており、現場の作業者や機械加工業者から高い評価を得ています。
ここでは、SS400の切削性・溶接性について詳しく解説します。
切削性について
SS400は低炭素鋼(C≦0.25%)であるため、金属としての硬さがそれほど高くなく、切削工具に対しての抵抗が小さい点が特徴です。
そのため、フライス加工・旋盤加工・穴あけ・タップ加工など、さまざまな加工に適しています。
ただし、切削時に注意すべき点として以下が挙げられます。
・加工硬化が起こりにくいため、仕上げ精度を安定して出しやすい。
・工具摩耗は比較的少ないが、硫黄(S)含有量が高い個体では工具寿命に影響を及ぼすことがある。
・表面仕上げ品質を重視する場合は、切削油の使用や適切な送り速度・回転数の設定が求められる。
また、一般的な超硬工具やハイス鋼(HSS)工具で問題なく加工でき、NC旋盤やマシニングセンタでも扱いやすい材質です。
そのため、量産品の加工にも向いています。
溶接性について
SS400の溶接性は非常に良好です。
炭素量が少なく、合金元素の含有量も限定的なため、溶接熱による割れ(ホットクラック)や焼き割れのリスクが低いのが大きな利点です。
被覆アーク溶接(手溶接)、CO₂溶接、MAG/MIG溶接、TIG溶接など、あらゆる溶接方法に対応可能であり、現場作業や製造ラインでの汎用性も高いです。
ただし、板厚や使用環境によっては以下の点に注意が必要です。
・厚板や複雑な構造物の溶接時には予熱が必要な場合があります(特に20mm以上の厚板)。
・溶接後の応力除去焼鈍(SR処理)を行うことで、溶接部の残留応力を緩和でき、後工程での変形を抑制できます。
・溶接熱影響部(HAZ)の硬化や脆化が発生しにくいため、焼きなまし処理を行わなくても問題が起きにくいという点もSS400の長所です。
また、耐食性に劣る点には留意する必要があります。
溶接部は酸化スケールが発生しやすく、未処理のまま屋外にさらすと腐食が進行するため、溶接後の塗装やメッキなどの表面処理が推奨されます。
SS400の切削性・溶接性は、加工現場での柔軟性を確保できる重要な要素です。
コスト面でも優れており、小ロット試作から量産製品、建築現場での即席加工まで、あらゆる場面で信頼できる鋼材と言えるでしょう。
曲げ・プレス加工時の注意点
SS400は構造用鋼材として幅広く使用されており、その加工のしやすさは高く評価されています。
特に曲げ加工やプレス加工においては、材料の延性や靭性のバランスが良好なため、さまざまな形状へと成形することが可能です。
ただし、適切な加工を行うには、材料特性を踏まえたうえでの注意点がいくつか存在します。
SS400の曲げ特性
SS400は低炭素鋼で延性が高く、割れにくいため、板金の曲げ加工に適しています。
曲げ加工とは、材料を一定の角度に折り曲げる加工で、ベンダー(プレスブレーキ)やロール曲げ機を用いるのが一般的です。
加工時におけるポイントは以下の通りです。
・曲げ内R(曲げ半径)は、材料厚の1倍〜1.5倍を基準に設定することで、割れや変形を抑制できます。
・繊維方向(圧延方向)と直交する方向に曲げると、割れやすくなることがあるため、繊維方向を考慮した曲げ方向を選ぶのが望ましいです。
・板厚が増すほど反発力(スプリングバック)が大きくなり、狙った角度よりも戻ってしまうため、角度補正が必要です。
また、曲げ加工では曲げ中心部に引張応力と圧縮応力が同時に作用します。
これにより、表面に微細なクラック(割れ)が生じることもあるため、加工前の表面傷チェックやバリ取りも重要です。
プレス加工における注意点
プレス加工では、金型を使ってSS400に圧力を加え、打ち抜き・曲げ・絞りなどの形状変化を加えます。
SS400は硬度が比較的低いため、金型への負担が少なく、耐久性の面でもメリットがあります。
ただし、以下の点に注意が必要です。
・打ち抜き加工時にはバリが発生しやすいため、後工程でのバリ取りが前提となります。
・シャー角やクリアランスの適正化が重要で、適切でない場合は材料のカエリや金型の早期摩耗につながります。
・材料の厚みや大きさに応じて、プレス機のトン数の選定が重要です。過小トン数では成形不良、過大トン数では金型損傷の原因になります。
また、SS400は冷間加工硬化が起こりにくいため、連続加工にも適していますが、複数工程の連携が必要な絞り加工では、潤滑油の使用や中間焼きなまし処理を挟むことで加工性を維持できます。
加工後の対応
曲げ・プレス加工後には以下のような処理が推奨されます。
・ショットブラストやバリ取り処理で表面の異物除去
・塗装やメッキによる防錆処理
・寸法精度を確保するための再測定と検査
また、最終用途に応じては、SS400の代替材としてSPHCやSPCCが選ばれることもあります。
より高い精度が求められる場合や、表面仕上げ品質が重視される製品では、素材選定段階での比較が重要になります。
SS400加工における表面処理の必要性
SS400はコストパフォーマンスに優れた一般構造用鋼材として広く用いられていますが、表面処理なしでは耐食性に乏しいという大きな弱点があります。
これは、SS400が炭素鋼であり、合金元素(クロムやニッケルなど)を含まないため、空気中の酸素や水分と反応しやすい性質を持っているからです。
そのため、屋外や湿度の高い環境、あるいは化学薬品が飛散する場所での使用には、何らかの表面処理が必要不可欠です。
ここでは、SS400に施される代表的な表面処理と、それぞれの特徴・適用シーンについて解説します。
塗装処理
最も一般的で経済的な表面処理方法が塗装処理です。
加工後に脱脂・防錆プライマー・上塗りの工程を経て、酸化や腐食を防ぐ膜を形成します。
メリット:設備コストが低く、さまざまな色や質感に対応できる。補修も容易。
デメリット:物理的な衝撃や摩擦によって塗膜がはがれやすく、再塗装が必要になることがある。
用途例:建築部材、機械フレーム、手すり、屋内構造物など。
塗装前にはブラスト処理や脱脂工程をしっかり行うことで、塗膜の密着性を高めることができます。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
SS400を耐食性の高い材料に変える表面処理として広く採用されているのが、溶融亜鉛メッキ(HDZ55など)です。
鋼材を溶融した亜鉛槽に浸すことで、表面に厚い亜鉛層を形成します。
メリット:屋外使用や海辺などの過酷な環境でも10年以上の防錆効果が期待できる。
デメリット:メッキ層が厚く寸法変化が出ることがあり、寸法精度が求められる部品には不向き。
用途例:屋外階段、フェンス、送電鉄塔、橋梁部材、港湾施設など。
また、溶融亜鉛メッキは「犠牲防食作用」により、亜鉛が先に腐食することで鋼材本体を守る仕組みとなっています。
電気メッキ(電気亜鉛メッキなど)
より薄く、美観に優れたメッキ処理として電気メッキも選択肢となります。
電解液中で亜鉛やニッケルを鋼材表面に析出させて皮膜を作ります。
メリット:仕上がりが美しく、薄膜でも一定の耐食性を得られる。寸法変化が少ない。
デメリット:厚膜メッキに比べ耐食寿命は短く、屋外や水回りには不向き。
用途例:自動車部品、機械カバー、室内配電盤、家具フレームなど。
見た目の美しさが重要な場合に選ばれることが多い処理方法です。
黒染め処理(四三酸化鉄皮膜)
表面を黒く仕上げる目的で黒染め処理(ブラックオキサイド処理)が用いられることもあります。
これは装飾性や反射防止、軽防錆を目的とした処理です。
メリット:艶消しの美観と軽い防錆性能が得られる。寸法変化がない。
デメリット:耐食性は他の処理よりも劣る。湿気の多い環境ではすぐに錆が発生する。
用途例:工具、治具、装飾部品、内装品など。
黒染めはあくまで軽防錆処理であり、屋外使用には向きません。
表面処理の選定ポイント
SS400にどの表面処理を施すかは、以下のような要素で選定されます。
・使用環境(屋内・屋外、湿度、薬品)
・コストと仕上がりのバランス
・寸法精度の許容範囲
・耐久性の要求レベル
最適な処理を選定することで、SS400の性能を最大限に引き出し、製品寿命の延長やトラブルの低減につながるのです。
SS400と他材料との比較
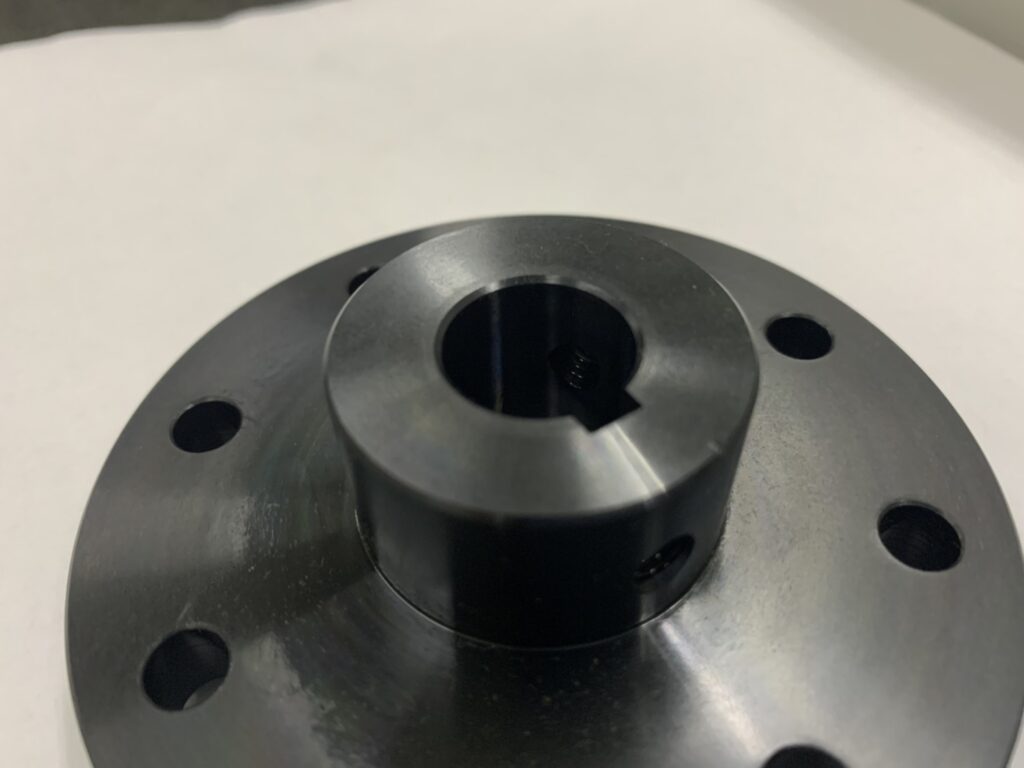
炭素鋼(S45Cなど)との比較
SS400とS45Cは、いずれもJIS規格に準拠した鋼材ですが、用途・特性・加工性に明確な違いがあります。
SS400は一般構造用圧延鋼材(JIS G 3101)、S45Cは機械構造用炭素鋼鋼材(JIS G 4051)に分類され、目的とする性能が異なるため、適切に使い分けることが重要です。
基本的な違い:構造材と機械部品材
| 項目 | SS400 | S45C |
|---|---|---|
| 分類 | 一般構造用圧延鋼材 | 機械構造用炭素鋼鋼材 |
| 引張強さ(MPa) | 400~510 | 約570~700(焼入れ前) |
| 用途 | 建築構造、フレーム、土台 | シャフト、ギア、ピンなど機械部品 |
| 熱処理 | 基本はなし(焼入れ不可) | 焼入れ・焼戻しで硬化可能 |
| 溶接性 | 優れている | やや注意が必要(割れリスク) |
SS400は構造物の骨組みや支持部に用いられ、溶接や曲げ加工などがしやすいのが特長です。
一方、S45Cは比較的高い炭素含有量(約0.45%)を持ち、熱処理による硬化や強度向上が可能であるため、回転軸や摺動部など機械的応力を受ける部品の製作に最適です。
加工性・溶接性の違い
SS400は低炭素鋼に分類され、柔らかくて加工性・溶接性に優れており、初期加工に適した鋼材です。
溶接後の割れも起きにくいため、比較的ラフな施工条件でも安定した仕上がりになります。
一方で、S45Cは炭素量が多いため、切削時にバイトの摩耗が早まったり、焼入れによって硬化するために工具選定に注意が必要です。
また、炭素が多いぶん溶接時には熱影響部に割れが発生しやすくなるため、予熱・後熱などの管理が不可欠です。
機械的強度と耐摩耗性の違い
S45Cは、焼入れ処理を施すことで表面硬度を50HRC以上にまで高めることができ、耐摩耗性や機械的強度が求められる箇所に最適です。
例えば以下のような用途があります。
・自動車や工作機械のシャフト類
・金型の構成部品(ピン・プレートなど)
・プーリーやギアなど、回転や荷重が加わる部品
一方、SS400はこうした高強度や耐摩耗性は持ちません。
変形しやすく、部品としての使用には限界があり、特に高精度な寸法維持が必要な用途には不向きです。
適材適所の選び方
SS400とS45Cを混同してしまうと、強度不足や加工トラブルの原因になります。
たとえば、「SS400でピンを作ったが、すぐに摩耗してしまった」「S45Cを溶接したらひび割れた」といった失敗は少なくありません。
用途に応じた選定の目安は以下の通りです。
・SS400:構造材やフレーム、非可動部(コスト重視・加工性優先)
・S45C:駆動部品、摩耗部、熱処理対象部品(性能重視・耐久性必要)
このように、見た目が似ていても性能は大きく異なるため、材質名の確認と目的に合った選定が不可欠です。
ステンレス鋼(SUS304など)との比較
SS400とSUS304は、外観や材質の光沢感が似て見える場合もありますが、成分・性能・用途が大きく異なる鋼材です。
SS400は炭素鋼、SUS304はオーステナイト系ステンレス鋼に分類され、耐食性や加工特性に根本的な違いがあります。
この項目では、両者の特徴を明確に比較し、選定時のポイントを解説します。
材質の根本的な違い
| 項目 | SS400 | SUS304 |
|---|---|---|
| 種類 | 一般構造用圧延鋼材(炭素鋼) | オーステナイト系ステンレス鋼 |
| 主成分 | Fe(鉄)+C(炭素) | Fe+Cr(18%前後)+Ni(8%前後) |
| 耐食性 | 低い(サビやすい) | 非常に高い(耐候性・耐薬品性あり) |
| 価格帯 | 低コスト | 高コスト(約3〜5倍) |
| 溶接性 | 良好 | 良好だが歪みに注意 |
| 加工性 | 良好 | 良好だがやや硬めで工具摩耗あり |
SS400は炭素鋼に分類されるため、空気中でも錆びやすく、防錆処理が必須です。
塗装・メッキなどで表面保護されない限り、屋外や水回りでは腐食が急速に進みます。
一方で、SUS304は高い耐食性を持ち、食品機器、医療器具、屋外構造物など幅広い分野で使用されています。
特にクロムとニッケルの含有により、錆びにくく清潔感を保ちやすいのが最大の利点です。
使用環境と用途の違い
・SS400の代表用途
建築の骨組み、工場の架台、車両部品、溶接構造物など。コスト重視・屋内使用が多い。
・SUS304の代表用途
キッチン機器、食品工場の配管、屋外看板、建築の外装材、病院設備など。
耐食性・清潔性重視の現場に適す。
両者は、同じ「鋼材」でもまったく異なる性能と得意分野を持つため、「とりあえずSS400でいい」という判断は危険です。
たとえば、水分の多い環境や屋外用途でSS400を使うと、数か月で赤サビが発生し、強度や美観に悪影響を及ぼします。
溶接・加工の観点からの違い
どちらも溶接性は良好ですが、SUS304は熱膨張が大きいため溶接後に歪みが生じやすいという注意点があります。
さらに、切削加工ではSUS304の方がバリが出やすく、工具摩耗が早いため、刃物や加工条件に工夫が必要です。
逆にSS400は比較的軟らかく、切削・曲げ・穴あけなどあらゆる加工がスムーズに行えます。
量産や試作での扱いやすさでは、SS400に分があります。
材料選定のポイント
| 環境条件 | 推奨材質 |
|---|---|
| 屋内、乾燥環境、コスト重視 → | SS400 |
| 屋外、湿気・水まわり、清潔性重視 → | SUS304 |
耐食性や見た目の美しさが必要な用途では迷わずSUS304を選ぶべきですが、コストや加工性を優先するならSS400が適している場面も多々あります。
用途ごとに「必要な性能」を明確化し、材料選定を行うことが、トラブル防止とコスト最適化の鍵です。
SS400の加工と取り扱い
SS400の加工方法と注意点
SS400は「一般構造用圧延鋼材」として非常に広く利用されており、その最大の特長のひとつが加工性の高さです。
溶接、切削、曲げ、穴あけ、切断といった幅広い加工が容易に行えるため、建築・機械・車両などさまざまな分野で重宝されています。
ただし、SS400の加工にはいくつかの留意点もあります。
以下では、代表的な加工方法と注意点について解説します。
1. 切削加工(旋盤・フライス・ドリルなど)
SS400は炭素含有量が低めで軟らかいため、切削抵抗が小さく加工しやすい鋼材です。
標準的な工具でも十分に対応可能で、工具摩耗も少なく、長時間安定して加工できます。
ただし、焼入れなどの熱処理が施されていない場合、切削面にバリが出やすいため、仕上げ加工やバリ取りを丁寧に行う必要があります。
工具条件としては、一般的なハイス(HSS)工具で対応可能ですが、生産性や仕上げ面の品質向上を目指す場合は超硬工具を用いるのが効果的です。
2. 溶接加工
SS400は非常に溶接性の高い鋼材で、アーク溶接・CO₂溶接・TIG溶接など、さまざまな溶接方法に対応できます。
組立構造やフレームなどに広く使用される理由のひとつです。
注意点としては、板厚が大きい場合に割れを防止する予熱の必要性があることです。
特に10mm以上の厚板では、予熱(100〜150℃程度)を行うことで冷却時の応力集中や割れを防ぐことができます。
また、溶接後は酸化被膜やスパッタの除去、必要に応じた塗装処理が推奨されます。
3. 曲げ加工・プレス加工
SS400は曲げやプレスにも適しており、特に中厚板までであれば割れやすさは少ないのが特徴です。
ただし、冷間加工を行う場合には、曲げ半径(R)を適切に確保しないと、表面にクラック(微細な割れ)が生じるリスクがあります。
冷間曲げでは、板厚の1.5〜3倍程度の曲げ内Rを確保することが一般的な目安です。
また、厚板や低温環境での加工では、材料が脆くなっている場合があるため、加熱して曲げる「熱間曲げ」も検討されます。
4. 切断加工(ガス・レーザー・機械)
SS400は酸素によるガス切断(溶断)に非常に適しており、厚板の切断にも強みがあります。
また、レーザー切断やプラズマ切断との相性も良く、精密な輪郭加工も可能です。
ただし、切断面には酸化皮膜やスラグが残ることがあるため、切断後のバリ取りや面取り処理を行っておくと後工程がスムーズになります。
5. 表面処理の必要性
SS400は耐食性が高くないため、屋外や水気のある場所で使用する場合は、塗装・メッキ・黒染め処理などの防錆対策が必須です。
加工直後は鉄が露出しており、早ければ数日で赤サビが発生することもあるため、工程間の保管方法(防錆油の塗布など)にも注意が必要です。
まとめ
SS400はあらゆる加工に対して高い適応性を持つ汎用性の高い鋼材です。
コストと加工性のバランスが良いため、試作から量産、構造材まで多用途に活用されます。
ただし、その弱点は耐食性の低さにあるため、加工後の防錆処理を怠らないことが、トラブル防止のポイントとなります。
SS400の熱処理と溶接特性
SS400は炭素鋼(Carbon Steel)の一種でありながら、比較的軟らかく延性にも優れているため、熱処理や溶接などの加工においても取り扱いやすい材料とされています。
しかし、合金鋼のような熱処理特性や、高強度が求められる構造材と同等には扱えない点もあり、用途と目的に応じた適切な処理方法の選定が重要です。
本項では、SS400の熱処理と溶接に関する特性と注意点について詳しく解説します。
1. 熱処理の基本:焼入れ・焼戻しには不向き
SS400はその組成から見て、熱処理による硬化(焼入れ)には不向きな鋼材です。
炭素含有量が約0.05〜0.25%程度と低く、マルテンサイト変態を起こしにくいため、焼入れによる顕著な硬度向上は期待できません。
そのため、SS400の熱処理は主に応力除去や軟化を目的とした焼鈍し・焼戻し処理が中心となります。
焼鈍し(アニール)では、加工や溶接によって発生した内部応力を除去し、加工性の向上や歪みの抑制を図ることができます。
特に厚板加工後や冷間曲げ後に歪みが残っている場合などに有効です。
2. 溶接性に優れる理由と基本的な特性
SS400が構造用鋼材として広く普及している理由の一つに、優れた溶接性が挙げられます。
これは、低炭素・低合金で構成されており、溶接時に熱影響部(HAZ)での割れが発生しにくいためです。
代表的な溶接方法としては以下が挙げられます。
・アーク溶接(手溶接)
・CO₂溶接(半自動)
・TIG溶接(高品質な仕上がりが必要な場面)
・サブマージアーク溶接(大型構造物向け)
これらの溶接方法のいずれでも良好な接合が可能であり、事前の特別な処理が不要なことも多いです。
3. 厚板の溶接と予熱・後熱の重要性
板厚が大きくなると、溶接時の急冷によって接合部や熱影響部に割れが発生するリスクが高まるため、予熱や後熱が必要となるケースがあります。
これは急激な温度変化による内部応力や、溶接金属と母材との熱収縮差によって亀裂が発生するのを防ぐためです。
・予熱温度の目安:100〜150℃
・後熱処理(低温焼戻し)を行うことで、溶接応力を緩和し、変形や割れの抑制が可能になります。
・溶接施工前には、板厚や形状、接合方法に応じて適切な予熱条件を設計しておくことが大切です。
4. 溶接後の変形と歪み管理
SS400は溶接後に熱膨張と収縮による歪みが発生しやすいため、溶接順序や治具による拘束、対称溶接などによる歪み抑制の工夫が不可欠です。
特に長尺材や薄板構造では注意が必要です。
また、必要に応じて、以下のような後工程での歪み取り作業も考慮されます。
・ガス加熱による局所的な歪み修正
・機械的な矯正加工(プレスなど)
これらを適切に行うことで、製品精度を確保し、後工程での不具合を防止できます。
5. 耐熱性と使用温度範囲
SS400の使用温度範囲は、常温から300℃程度までが目安とされています。
それ以上の高温環境では、強度低下や酸化スケールの発生などにより、耐久性が大きく損なわれる可能性があります。
また、極低温環境においても脆性破壊(靭性の低下)が起こりやすくなるため、-10℃以下での使用には材質変更(低温用鋼材:SN材など)が推奨されます。
まとめ
SS400は、一般構造用鋼材として非常に汎用性が高く、溶接性にも優れた特性を持ちます。
ただし、熱処理による硬化は望めないため、機械的特性を必要とする場合には別材質の選定が必要です。
溶接作業においては、板厚や応力の影響を考慮して、予熱や後熱、歪み管理の工程を丁寧に設計することが重要です。
SS400を使用した部品加工の見積り依頼ならアスクへ
試作品や小ロットの加工も大歓迎!
特に手のひらサイズの部品製作を得意としています。
アスクなら、試作品のお見積もりが最短1時間で可能!!
お気軽にお問い合わせください。
試作全国対応!
簡単・最短1時間お見積り
※こちらの記事はAIを参照して記事作成しております。
正しい情報かどうかは保証しかねますので、ご自身でお調べいただくようお願いします。


