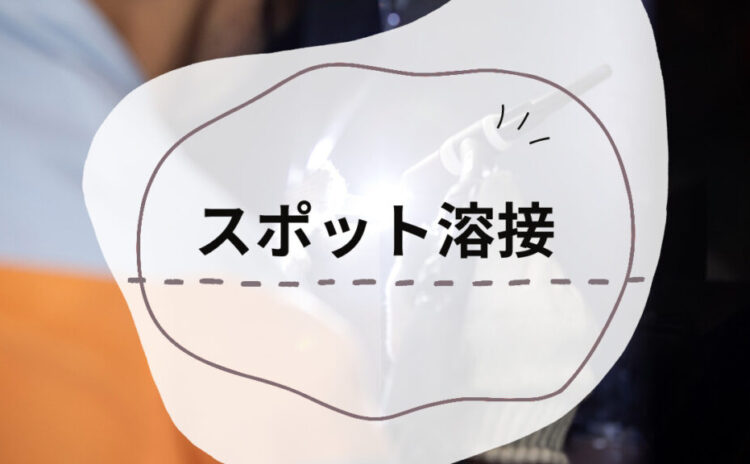スポット溶接とは?自動車から家電まで広がる接合技術の基本と特徴
スポット溶接は、電気抵抗を利用して金属を接合する「抵抗溶接」の一種で、特に薄板金属の接合に広く用いられています。
自動車のボディや家電製品の筐体など、量産工程において欠かせない技術として、製造業の現場で高い信頼性を誇ります。
スポット溶接とは
スポット溶接とは、電気抵抗を利用して金属を接合する「抵抗溶接(resistance welding)」の一種であり、特に2枚の金属薄板を点状に接合するための工法として広く普及しています。
この工法は、自動車ボディの製造や家電製品の筐体加工など、薄板金属の量産工程において不可欠な接合手段とされています。
溶接の基本原理
スポット溶接は、まず2枚の金属板を重ね合わせ、上と下から電極(通常は銅系材料で構成)で強く挟み込みます。
この状態で、瞬間的に高電流(数千アンペア〜数万アンペア)を短時間(通常0.1~0.5秒程度)流します。
電流が流れると、金属の接合面で「電気抵抗」による発熱(ジュール熱)が起こり、接触面が急速に加熱されます。
その結果、局所的に金属が溶融し、通電終了後に加圧を継続することで、溶融部が凝固して強固な接合点(ナゲット)を形成します。
この「ナゲット(nugget)」と呼ばれる溶接点は、直径3〜10mm程度で、複数のナゲットを一定の間隔で打点することで、部材全体を接合していくのがスポット溶接の基本的な構造です。
抵抗加熱の仕組み
スポット溶接で用いられるジュール熱の発生量は、以下の式で表されます。
Q = I² × R × t
ここで、
Q:発熱量(ジュール)
I:通電電流(アンペア)
R:電気抵抗(オーム)
t:通電時間(秒)
特に注目すべきは、電流が二乗されて影響するため、電流値が少し上がるだけでも発熱量が急増するという点です。
このため、溶接条件の設定においては電流値が非常に重要なファクターとなります。
また、接触面での抵抗(インターフェース抵抗)と、電極〜材料間の抵抗のコントロールが溶接品質を左右します。
加圧の役割
電極による加圧は、単に材料を挟むだけでなく、以下の目的でも重要です。
・接触抵抗の確保:適度な圧力で接触点の抵抗を最適化し、発熱を集中させる。
・材料の密着:ガタつきを防ぎ、均一な溶融を促す。
・溶融後の凝固を制御:溶融金属を押さえつけて、内部に空洞(ボイド)や割れができるのを防ぐ。
・加圧不足や過加圧は、いずれもナゲットの形成不良やスプラッシュ(飛散)などの欠陥を引き起こす要因となります。
特徴と利点
スポット溶接は、アーク溶接やTIG溶接とは異なり、溶接材やガスを必要とせず、短時間で接合が可能です。
そのため、以下のような利点があります。
・極めて高速な作業:1秒以内で1点の接合が可能
・自動化に適する:ロボットアームとの組み合わせでライン化が容易
・熱影響が狭い:構造材の変形や焼けが比較的小さい
・省スペース:溶接トーチが小型で、狭所でも加工できる
制限と留意点
一方で、以下のような課題や制限もあります。
・厚板同士の接合には不向き(板厚合計が3〜4mm以下が望ましい)
・接合強度が点状のため、せん断荷重や引張荷重に注意が必要
・鉄系材料は得意だが、アルミなど低抵抗金属は困難(後述)
このように、スポット溶接は特定の条件下において非常に優れた性能を発揮する工法であり、その適用には材料特性や溶接条件の十分な理解が必要となります。
スポット溶接の装置と構成
電極と電極材の選定
スポット溶接において、電極は非常に重要な役割を果たします。
電極は単に電流を供給するだけでなく、加圧力を加え、材料表面との接触を通じて発熱を誘導し、ナゲット形成を支える主要な要素です。
適切な電極設計と材質選定がなされていなければ、溶接品質の低下や電極寿命の短縮、設備トラブルの原因となるため、その選定は極めて重要です。
電極の役割と要求性能
スポット溶接用電極には、以下のような性能が要求されます。
・高い電気伝導性:大電流をロスなく通すため
・高い熱伝導性:熱の集中をコントロールし、過加熱やスプラッシュを防ぐ
・高温硬度・耐摩耗性:ナゲット形成時の加圧で摩耗・変形を抑える
・安定した接触性:繰り返しの加圧と通電に耐え、表面状態を一定に保つ
これらを満たすために、電極材には主に銅をベースとした合金が用いられます。
純銅は導電性には優れていますが、軟らかくて摩耗しやすいため、耐久性の観点から合金化が一般的です。
主な電極材料と特徴
国際的には、RWMA(Resistance Welding Manufacturers Association)規格で電極材料が分類されています。
以下に代表的な電極材とその用途を紹介します。
■ クラス2:クロム銅(Cu-Cr)
特徴:電気伝導率・熱伝導率ともに高く、機械的強度も良好
用途:軟鋼や亜鉛めっき鋼板のスポット溶接に多用
利点:バランスが良く、一般用途での標準材
注意点:高電流での長時間運転では摩耗が早まる可能性
■ クラス3:ベリリウム銅(Cu-Be)
特徴:硬度が非常に高く、摩耗に強い
用途:高強度鋼板や高張力鋼板などの接合に有効
利点:型崩れしにくく、高精度なナゲット形成が可能
注意点:加工性がやや低く、価格も高価
■ クラス11:タングステン・銅(W-Cu)
特徴:高融点・高硬度のタングステンを含み、極めて耐熱性が高い
用途:アルミニウムなどの低抵抗金属のスポット溶接
利点:スプラッシュを抑え、寿命が長い
注意点:導電率がやや低いため、通電制御が必要
電極の形状と冷却
電極の形状は、溶接品質に大きな影響を与えます。
標準的な形状には「円錐形」「ドーム形」「フラット形」などがあり、用途や部材の形状に合わせて選定されます。
特にドーム形は電流集中性と加圧均一性に優れ、広く使われています。
さらに、スポット溶接においては電極の冷却も非常に重要です。
冷却が不十分だと電極先端が過熱し、摩耗や変形、さらには母材の過加熱による溶接不良につながります。
多くの装置では水冷式の冷却機構が採用されており、電極の内部を冷却水が循環する構造になっています。
電極のメンテナンスと寿命管理
スポット溶接の生産現場では、電極の寿命とメンテナンス管理が溶接品質の安定化に直結します。
以下のような管理が行われます。
・電極の摩耗チェックと定期的なドレッシング(先端整形)
・使用回数や溶接点数に基づく交換周期の設定
・ナゲット径のモニタリングによる品質管理
溶接回数が進むと、電極先端が摩耗し、接触面積が増加するため、同じ電流では十分な発熱が得られなくなり、ナゲットが小さくなります。
このため、先端の摩耗状態を定期的に修正することで、一定品質のナゲットを安定して得ることが可能です。
溶接電源と制御装置の仕組み

スポット溶接における品質の良否は、溶接電源とその制御装置によって大きく左右されます。
これらの機器は、材料と電極の間に適切な電流を、必要な時間だけ、望ましい波形で流すことを目的とし、溶接の安定性・再現性・安全性を確保するための中枢とも言える存在です。
溶接電源の役割と種類
溶接電源は、工場で一般的に使用されている商用電源(AC100Vまたは200V、場合によっては400V)を、スポット溶接に適した大電流・低電圧の出力に変換する装置です。
スポット溶接に必要な電流は数千アンペア〜数万アンペアに及ぶため、その供給源には高い性能と信頼性が求められます。
主な溶接電源には以下の2種類があります。
■ 工頻トランス式(ACタイプ)
・交流(50Hzまたは60Hz)を直接トランスで降圧して電流を供給する方式
・シンプルな構造で安価、整備が容易
・電流波形が滑らかでなく、微細な制御が難しい
・通電開始から安定状態までの立ち上がり時間が長め
主に鉄系材料や一般的な薄板溶接で用いられます。
現在では、コスト重視の大量生産ラインなどに限定される傾向です。
■ インバータ式直流電源(DCタイプ)
・商用電源をいったん直流に変換し、高周波インバータ(例:1kHz〜4kHz)で再び交流化、その後トランスを通して降圧・整流して直流電流を供給
・電流波形が安定し、立ち上がりが早く、短時間で高精度な加熱が可能
・制御性に優れ、アルミや高張力鋼などの難溶接材に対応可能
・高価で構造が複雑だが、省エネ性や生産性に優れる
近年のスポット溶接現場では、インバータ式直流電源が主流となっており、特に自動車のアルミ車体や超高張力鋼板のスポット溶接では不可欠な技術となっています。
溶接制御装置の構成と機能
制御装置は、電源から供給される電流の大きさ(電流値)・時間(通電時間)・立ち上がり速度などを正確に制御します。
また、加圧タイミングや冷却時間など、溶接サイクル全体の統括管理を担っています。
典型的な溶接サイクルには以下のステージがあります。
・加圧時間(Squeeze Time)
材料を電極で挟んで加圧する時間。接触状態を安定させ、過剰なスパークを防止。
・通電時間(Weld Time)
設定電流を流し、材料界面にナゲットを形成させる。
・保持時間(Hold Time)
通電を停止しても電極加圧を継続し、溶融部を凝固・冷却させる。
・休止時間(Off Time)
次の溶接までの待機時間。冷却水循環や電極温度管理に活用。
最新の制御装置では、これらの各工程をミリ秒単位で制御し、個々の溶接点ごとに記録・モニタリングが可能です。
特に「電流フィードバック制御」や「ナゲット成長モニタリング」などの機能により、品質のばらつき低減と不良防止が実現できます。
波形制御と高機能制御技術
スポット溶接の電流波形には以下の種類があり、用途に応じて使い分けられます。
・矩形波制御:高精度な電流制御が可能。ナゲットサイズのばらつきが少ない。
・ステップ制御:電流を段階的に上げ、母材の過熱を抑える。
・パルス制御:短い通電を繰り返すことで熱量を細かく調整できる。
また、AIやセンサ技術と連携したスマート溶接制御も進化しています。
ナゲットサイズのリアルタイム検出や、材料厚みのばらつき補正、電極摩耗の自動補正など、高度なフィードバック制御が導入されつつあります。
安全性とトラブル防止
大電流を扱うスポット溶接では、感電防止・漏電対策・異常発熱の監視なども重要です。
制御装置には以下のような安全機能が組み込まれることが一般的です。
・漏電検出と停止機能
・水冷不足アラーム
・過電流・過負荷検出
・不完全通電時のエラー表示
特にインバータ式電源では、トランス過熱や制御基板の異常にも敏感なため、定期的な点検と温度管理が求められます。
加圧機構と溶接力の重要性
スポット溶接では、加圧は電流と並ぶもう一つの重要な要素です。
適切な加圧力がなければ、溶接点(ナゲット)の形成が不安定になり、品質のばらつきや強度不足、さらにはスパッタや母材変形などの不具合を引き起こす恐れがあります。
溶接における「加圧」は、単なる補助動作ではなく、接合を成立させる根幹のプロセスです。
加圧機構の種類と構造
スポット溶接装置において、加圧機構は主に上部電極を移動させる構造に組み込まれています。
以下のような駆動方式があります。
■ 空圧式(エアシリンダ駆動)
・最も一般的に使用される方式
・圧縮空気の供給によってピストンを上下させる
・加圧力の調整が比較的容易で、メンテナンス性も高い
・高速運転や大量生産に適している
■ 油圧式
・重量物や厚板材の加圧に用いられる
・加圧力が非常に高く、力の立ち上がりが安定している
・制御装置が大きく、エネルギー効率は空圧より劣る
■ サーボモータ式(電動加圧)
・高精度な位置制御・力制御が可能
・立ち上がりや停止時の動作が滑らか
・プログラム制御との相性がよく、近年の自動化設備で採用増加
・高価だが繰返し性に優れ、データ記録が容易
これらの方式は、用途・設備規模・要求精度によって適切に選定されます。
加圧力の設定とその影響
溶接圧力(電極加圧力)は、一般的に数百ニュートン(N)から数千N程度で設定され、以下のような役割を果たします。
・材料の密着性向上:接合面を密着させ、電気抵抗が集中するよう制御
・ナゲット形成の安定化:材料が滑ったり浮いたりすることを防止
・スパッタの抑制:過剰な溶融金属の飛散を防ぎ、外観を改善
・溶接後の凝固制御:溶融部を押さえながら冷却・固化を促す
圧力が低すぎると、接触不良により電流が広がってしまい、局所的な加熱ができず、ナゲットが形成されない、または小さすぎて強度不足になります。
反対に圧力が高すぎると、材料が押しつぶされて薄くなり、過剰に発熱が抑制され、結果として溶接が不完全になる可能性があります。
適正な圧力は、材料の種類・板厚・電極形状・電流条件などによって変動するため、事前の条件出しと試験溶接が不可欠です。
溶接力と電極先端の関係
電極の先端形状と接触面積は、溶接力の効果に大きく影響します。
例えば、同じ加圧力でも、接触面積が狭ければ圧力は集中し、局所加熱が促進されます。
逆に、接触面積が広いと、圧力が分散してしまい、発熱効率が低下します。
したがって、加圧力 × 接触面積のバランスが非常に重要です。
先端形状が摩耗した場合、見た目には同じ加圧でも、実際には材料にかかる圧力が弱くなり、溶接不良の原因になります。
これを防ぐために、定期的な電極のドレッシング(先端再加工)が必要です。
ナゲット形成との関係性
ナゲットは、電流・時間・加圧力の3要素のバランスで決まります。
特に加圧力が不足している場合、溶融した金属が材料間に広がらず、中心部だけが溶ける「偏心ナゲット」となり、せん断強度や引張強度が低下します。
加圧力が適切であると、材料の界面に均一な密着が起こり、安定したナゲットの形成が実現します。
これは、スポット溶接の接合強度だけでなく、製品全体の信頼性にも直結する重要なポイントです。
自動化ラインにおける加圧制御
ロボットによるスポット溶接が一般化した現在、加圧力の再現性が大きな課題となっています。
サーボ制御により動作の個体差を最小限に抑え、加圧時間・速度・保持時間まで細かく設定できる制御技術が求められています。
また、製造ラインでは加圧力センサを内蔵し、リアルタイムで圧力を測定・記録することで、溶接品質のトレーサビリティを確保する動きも強まっています。
スポット溶接の利点と課題
短時間・高効率な接合のメリット

スポット溶接は、非常に短時間で強固な金属接合を実現できることが最大の利点です。
溶接そのものは、一般的に0.1〜0.5秒程度の通電と1秒未満の加圧保持で完結します。
この短時間での接合が可能であることは、生産現場において以下のような具体的なメリットをもたらします。
⬛ 圧倒的な生産性の高さ
スポット溶接は一連の動作が高速で、しかも連続して打点(スポット)可能なため、自動車ボディや家電、事務機器など大量生産に適した溶接方式です。
1分間に数十打点を実現することも難しくなく、産業ロボットや自動溶接機との組み合わせによって、24時間稼働可能な無人ラインの構築も容易です。
この効率性は、TIG溶接やアーク溶接などの溶融型接合と比較して段違いであり、量産におけるトータルコスト削減、工程短縮、設備の稼働率向上に大きく寄与します。
⬛ 熱影響の最小化と変形の抑制
スポット溶接では、電流をごく狭い接触点に集中させて発熱するため、溶融範囲(ナゲット)が非常に小さく、周囲への熱影響(HAZ)が最小限に抑えられます。
これにより、母材の歪み・反り・変形が少なく、部品精度を損なうことなく接合が可能です。
この特徴は、特に薄板材や精密板金の分野で重宝されており、後工程での補正作業を最小限に抑えることにもつながります。
⬛ 消耗品や周辺装置が不要
スポット溶接では、通常のアーク溶接のように溶接棒・シールドガス・フラックスなどの消耗資材を必要としません。
使用するのは主に「電極」と「冷却水」であり、消耗品コストが低く、補充や管理の手間も少ない点が利点です。
この簡便性は、運用の安定性とメンテナンス負担の軽減にもつながります。
⬛ 自動化・ロボット化への適応性
電極で材料を挟む構造上、位置決め精度と電極の可動制御さえ確保できれば、スポット溶接は極めて自動化に適した工法です。
多関節ロボットに溶接ガンを搭載し、CAD/CAMとの連携によって高速かつ高精度な溶接が実現されており、自動車産業ではほぼ標準となっています。
スポット構造による接合強度の注意点
スポット溶接では、接合が「点」で構成されるため、連続的・面全体での接合に比べて強度的に制約があります。
とくに構造物や荷重を受ける部品においては、スポット構造特有の問題に注意が必要です。
⬛ 荷重方向に対する脆弱性
スポット溶接は、せん断方向(面と平行方向)の荷重には比較的強い傾向があります。
一方で、引張荷重(垂直方向)や剥離荷重に対しては弱く、ナゲットごとに荷重が集中しやすいため、割れや剥がれが発生しやすくなります。
そのため、設計時にはスポットの数・配置・間隔を考慮し、荷重分散ができるように最適な打点パターンを設計することが重要です。
⬛ ナゲットのバラツキによる強度低下
スポット溶接の品質は、電流・加圧・通電時間・電極状態など多くの因子によって影響されます。
ナゲット径や深さが均一でないと、同じ見た目でも強度が不安定になります。
そのため、生産工程では定期的な破壊試験(ピール試験、せん断試験)やナゲット径の確認、さらにはリアルタイムモニタリング機能付きの制御装置が品質管理において重要です。
⬛ ナゲット間の間隔とレイアウト
ナゲット同士が近すぎると、熱の干渉によって母材が軟化し、局所的な強度低下や変形が生じる場合があります。
逆に間隔が広すぎると、荷重が一点に集中してしまい、割れの原因となることもあります。
一般的に、ナゲット間距離(ピッチ)はナゲット径の10倍以上が推奨される場合が多いですが、材料や設計強度によって調整が必要です。
薄板以外の適用限界と対処法
スポット溶接は主に1〜3mm程度の金属薄板の接合に最適化された工法です。
しかし、近年の材料多様化や構造高度化により、厚板材や異種材料への適用も求められるようになっています。
このとき、従来のスポット溶接では対応が難しくなる場面があります。
⬛ 厚板溶接の限界とその理由
板厚が増えると、以下のような問題が発生します。
・電流の浸透が不十分になる(ナゲットが形成されない)
・加熱に時間がかかるため、母材が過熱・変形しやすくなる
・溶接力の不足により、加圧だけでナゲットが収縮・消失する
厚板では、接合部の熱容量が大きく、短時間では十分な発熱が得られません。
そのため、スポット溶接で接合できる板厚は両板合計で4〜5mm程度が上限とされます。
⬛ 異種金属の溶接への対応
例えば、鉄とアルミなど電気抵抗や熱伝導率の異なる金属同士では、発熱量の分布が偏り、ナゲットの形成が極めて不安定になります。
また、溶接時に金属間化合物(IMC)が生成し、接合部が脆くなるリスクもあります。
対処法としては以下のような技術が挙げられます。
・インバータDC方式+パルス制御による精密な電流制御
・中間層(インサート材)の挿入による接合性の改善
・機械的支援接合(例:リベットやボルト併用)とのハイブリッド化
⬛ 非鉄金属(特にアルミ)への対応
アルミニウムは抵抗が低く熱伝導が高いため、スポット溶接が難しい代表的な材料です。
加えて、酸化膜が接合の障害になりやすいという問題もあります。
この対策としては
・高出力インバータ電源による高電流の瞬間供給
・電極形状の最適化(先端を細く)
・電極加圧力の微調整とリアルタイムモニタリング
が実用化されており、近年ではアルミ車体の量産にもスポット溶接が用いられるようになっています(例:テスラやホンダのアルミフレーム車体)。
このように、スポット溶接は「短時間・高効率」である反面、「点接合の強度制限」や「厚板・異種材への対応」という課題があります。
ただし、これらは制御技術の進化によって徐々に克服されつつあり、正確な設計とプロセス管理によって適用範囲を拡張することが可能です。
試作全国対応!
簡単・最短1時間お見積り
※こちらの記事はAIを参照して記事作成しております。
正しい情報かどうかは保証しかねますので、ご自身でお調べいただくようお願いします。